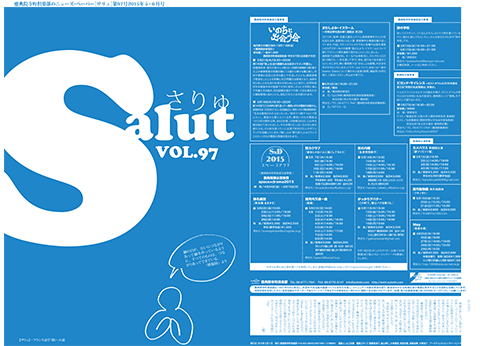
サリュ 第97号2015年5・6月号
目次
レポート「まわしよみ・イスラーム」
コラム 白波瀬達也さん(関西学院大学社会学部准教授)
インタビュー 島薗進さん(上智大学神学部特任教授・グリーフケア研究所 所長)
アトセツ
冒頭文
report「感」共に苦しみをわかちあう場
「まわしよみ・イスラーム」
自分の世界を広げるために
浄土宗寺院を拠点に多彩な活動を行っているのが應典院寺町倶楽部です。宗教への「入信」ではなく、開かれた組織への「入会」により、いのちの文化を共に育んでいきたい、そう願って取り組みを重ねてきています。1614年創建の應典院が1997年に再建されて間もなく20年ということもあり、應典院寺町倶楽部も設立20年を控えていることになります。当時はNPOという言葉も新しく、営利の追求を目的にしない「こころざし」の共同体への支援を多方面からいただいて参りました。
このたび、應典院寺町倶楽部では「まわしよみ・イスラーム」という企画を実施することにいたしました。浄土真宗本願寺派如来寺の住職で相愛大学教授の釈徹宗先生が阪急曽根駅近くに開かれた「練心庵」を拠点とする、NPO「そーね」との協働の企画です。既に皆さんご承知のとおり、2015年当初から相次いで報道されているイスラム過激派による事件をきっかけに構想が練られることになりました。悲しみの知らせが届けられた季節、應典院では折しもコモンズフェスタの開催中ということもあり、仏教と当事者研究プロジェクトなどでご一緒してきた「そーね」の方々と共に何かしようと議論を重ねてきました。
この「まわしよみ・イスラーム」は、その名のとおり「まわしよみ新聞」という手法をもとに、イスラームについて理解をしようという取り組みです。「まわしよみ新聞」は2012年度のコモンズフェスタにて生まれました。新聞離れが指摘される中、個人ではなく集団で読むことで毎日届けられる媒体の意味が見いだされるだろう、と狙いが定められたのです。企画者の陸奥賢さんは、その後『まわしよみ新聞のスゝメ』と題した書籍を出版されましたが、そこでは新聞をまわしよむことに「自分の世界を広げる可能性」があると記されています。
無知の知への扉を開く
そこで2015年度のコモンズフェスタまで、偶数月の3日の夜、19時から應典院の研修室Bにて、それぞれに新聞や一部雑誌記事を持ち寄り、イスラームについて深める機会を設けることにいたしました。通常「まわしよみ新聞」は特定のテーマが掲げられることはないのですが、あえてイスラームを軸に紙面や記事を見てみよう、という趣向です。ちょうど蛍光ペンでなぞるような感覚で、「なぜそうなんだろう?」という部分を切り抜き、互いに気になった点を語り合い、関心が重ねられた記事に、短い言葉を疑問系の形で添え、スクラップブックのような壁新聞に仕上げていきました。こうした手順を重ねることで、〈わからない〉ということがわかる、問いを掘り下げる場となりました。
結果として6枚の新聞が出来上がりました。そこには、地域の文化、時代の背景、信をもとに行動する集団の属性など、これまでわかっているようでわかっていなかった参加者の素朴な問いが示されています。今後、偶数月には應典院にて「まわしよみ・イスラーム」を行い、問いを掘り起こす場を、奇数月には「そーね」にて、掘り起こされた問いを『イスラーム概説』(黒田美代子・訳、書肆心水・刊)により深めて参ります。違いを前提に他者を思う、共感を鍛錬する場にどうぞご参加ください。
小レポート
看取りの共同体へ
協働の可能性を探る
去る3月15日、本堂ホールにて應典院の共催で「現代“臨終”事情-自分らしい在宅死を実現するために」が開催されました。仏教看護・ビハーラ学会が主催する本企画は、日本的な生き方や死の迎え方を多様な角度から見直すものでした。
前半、上智大学の島薗進先生による基調講演では、かつての日本に「いのちの循環から生まれ出て、死んでそこに帰っていく」という死生観があったことが指摘されました。それを失った現代においては、「死者を尊ぶ方法を取り戻したい」という想いが臨床宗教師養成などの背景にあるといいます。
また後半は、医師の波江野茂彦さん、看護師の慶松真弓さん、應典院の秋田光彦住職を加えてのシンポジウムでした。医療者の死生観を育むことの重要性が確認されると同時に、仏教者と医療者がどのように協働することができるかが、今後の課題とされました。
小レポート
新スタッフ入職
2015年4月より、新たなスタッフが事務局に参加しています。富山県に生まれた小塚佳子は、福島県の大学で教育を学び、20年以上に渡り横浜市の小学校に勤務していました。小学校教諭時代は担任を受け持つ他、学校図書課司書教諭として、図書室での絵本の読み語りの活動や、和太鼓の指導等も行っていました。発達障害の子どもを受け持つ個別支援学級の担当をした折に、「学校」という枠組以外の可能性や活動にも関心が広がり、コモンズフェスタ2015にインターンとして参加したことが入職の契機となりました。どうぞお見知りおきください。
小レポート
幼稚園新園舎完成、更なる連携へ
2013年度より、應典院寺町倶楽部では大蓮寺とパドマ幼稚園との連携のもと、まちとお寺と幼稚園の新たな可能性に迫る「キッズ・ミート・アート」を展開して参りました。こどもたちの言葉にならない思いを、単に幼児性で括るのではなく、芸術家の方々と共に多彩な手法で表現する企画で、城南学園の支援も頂戴して参りました。
この3月、2年間にわたるパドマ幼稚園の改修工事が竣工しました。現在、装いも新たな園舎を舞台に、おとなと子どもがアートに出会う夏の事業を検討中です。劇場寺院の経験を活かした、秋に開催予定の小学生対象の演劇ワークショップにもご期待ください。
コラム「越」
対話が生み出す知
私が應典院に関わることになったきっかけは、2010年におこなわれたBBA関西「20年後、あなたはお坊さん、してますか?」と第1回お寺MEETING「ネット世代は、寺院を変えるか。」という催しである。そこで同世代の意欲的な僧侶たちの存在を知り、刺激を受けた。私はキリスト教の社会活動を中心に研究してきたが、應典院との出会いを通じて仏教の動向にも興味を抱くようになった。
当時、私は文字通り「應典院ビギナー」であったが、秋田光彦住職からの依頼で前述の催しの評論を『サリュ・スピリチュアル』に執筆することになった。これを機に、現在まで深いご縁をいただくようになった。別の言い方をすれば、應典院に本格的に「巻き込まれる」ようになったわけだ。
常に時代の最前線を取り上げ、その社会的意義をクリティカルに問う應典院の催しは新たな学びの宝庫だ。また、應典院は宗教者、表現者、高感度な市民など、多様な属性をもった人々との出会いの場でもある。この「場所の力」を活かすべく、3月から「ビヨンド・サイレンス:ポストオウムの20年を語る」という連続企画を立ち上げた。
現代宗教の旬の部分を扱うこの催しでは各回で発題者をフィーチャーするが、力点を置いているのは「対話」。そのため参加者も20人程度に限っている。専門家が一方的に語るのではなく、特定の話題について参加者同士で深く語り合う。秋田住職と私は発題者と参加者の触媒役を担いつつ議論にも参加する。このように主客関係をできるだけフラットにして「対話によって創発される知」の生成を目指している。
3月20日に開催した第1回では「マスメディアにおける宗教報道」について語り合った。今後は「宗教の社会貢献」「聖地巡礼」などを取り上げる予定だ。本紙の読者が自身の専門や立場を超えて「ビヨンド・サイレンス」に巻き込まれることを期待している。
白波瀬達也(関西学院大学社会学部准教授)
1979年奈良県生まれ。関西学院大学社会学部卒業、同大学大学院社会学研究科博士課程後期課程単位取得満期退学。博士(社会学)。大阪市立大学都市研究プラザGCOE特別研究員等を経て現職。専攻は宗教社会学・福祉社会学。貧困問題や多文化共生に取り組む宗教者の活動を社会学の立場から研究している。著作に『釜ヶ崎のススメ』(共編著、洛北出版、2011年)、『宗教の社会貢献を問い直す―ホームレス支援の現場から』(単著、ナカニシヤ出版、2015年)などがある。2015年3月から應典院の催し「ビヨンド・サイレンス」のホスト役を秋田光彦住職と共に担当。
interview「精」
島薗進さん(上智大学神学部特任教授・グリーフケア研究所 所長)
日本を代表する宗教学者は、ポストオウムの
20年をどう見るか。スピリチュアリティに
関わる人々の抱える「弱さ」とは。
1995年の地下鉄サリン事件から20年となる今年、應典院では「ビヨンド・サイレンス」など、ポストオウムにおける宗教と社会の関係を見つめ直す場がはじまっている。宗教学者の島薗進さんに、オウム真理教とその後の20年をどのように捉えておられるかお話を伺った。
「70年代に、いわゆる『新新宗教』の活動が盛んになりました。それらの宗教は瞑想やヨガなど、一人でできる修行を大事にする傾向があり、その徹底した形としてオウム真理教が登場した。家族も仕事も捨てて一般社会とは別の世界をつくる、世の中との関係を絶って閉じこもる、その根本には、この世で富を得て幸せになるという成長志向への懐疑がありました。オウムの場合は極端に誤った方向に向かってしまいましたが、伝統宗教が本来持っていたはずの、現世的価値に対して精神的価値を尊ぶという方向性の奪還を目指した面があります。」
日本宗教が大きく変動する一方で、精神性、スピリチュアリティに付随する価値観も変容をつづけてきた。「別の見方をしますと、70年代以降は精神世界の時代で、宗教は嫌うけれども個人で精神性を追求するという傾向が見られました。アメリカでは『ニューエイジ運動』と呼ばれましたが、若者の希望とむすびついて、社会全体を変えていくユートピア主義的な思想を持っていた。サリン事件の直後、そういったものはガクンと力を失いましたが、実は95年はスピリチュアル・カウンセラーの江原啓之が登場した年で、霊界を感じることを通して本当の幸せとは何かを探求する動きがそちらに流れていきました。また、70年代からの課題ですが、医療現場において死と向き合う人々にとってのスピリチュアリティへの関心が広く理解されてくるなど、若者のユートピア的希望からひとりひとりの生を静かに見直すものへと、精神性の性格もまた変わってきています。」
ポストオウムのこういった流れの中で、伝統教団と一般社会の双方に気づきがあらわれた。「伝統教団の内部でも、特定の教団に所属することが宗教の本質ではない、と次第に理解されてきました。つまり、宗教はそれぞれの人の中で生きるものであるから、必ずしも同じ儀礼をし、同じ思想を分け持つという形でなくてもいいのではないか、という考えを持つようになったのです。逆に一般社会の側は、伝統教団が持つ形式の重要性に気がついていきました。あらゆる形式が解体される現代において、スピリチュアリティに関する課題、たとえば震災犠牲者の慰霊にどう対処すればいいのか分からない。そうした時にはじめて、伝統的な形式が存在することへの有り難さを感じるでしょう。それら両極の動きが、95年以降の展開には見られると思います。」
ご自身は、「一緒に祈りましょう」と言われると困ってしまうタイプだという。「私のように、特定の宗教を信じられない、きちんと信仰が身についていない、そんな人間でもスピリチュアルなものに関わることができるはずです。ただ、そこには形式が存在しないがゆえの『弱さ』がある、という自覚を持つべき。そのような弱い人間が何かが足りないと、宗教的なもの、スピリチュアルなものとの調和を求めている。そういう時代なんです。」
〈アトセツ〉
時候のあいさつに悩むことが多い。パソコンのワープロソフトには挨拶文ウィザードなどが導入されているものもある程だから、困る人も多いのだろう。ちなみにウィザードとは魔法使いを意味する。季節の変化に対する言葉の魔術師なのかもしれない。
應典院とご縁をいただいた方々は全国はもとより世界に広がっている。実際、このサリュの送呈先は632件である。それゆえ時候のあいさつに困るのだ。なぜなら、大阪で桜が咲いたとしても、届く先もそうとは限らないからだ。
実は昨年末、サリュ送付のあいさつ文が毎日新聞大阪版のコラム「毎日ぽこあぽこ」で話題とされた。書き手は神戸学院大学の金益見さんで、「定型句でないところ」に関心が向けられ、「ふんわり季節を実感できる」と興味が示されたのだ。ちなみにpoco a pocoとはイタリア語で「少しずつ」を意味する。「情報だけならネットで調べればいいのだけれど」と前置きし、「無難さ」を優先しない書き出しに、あいさつに重ねる相手への気持ちが見られると評価をいただけたのだ。
離れた場所を思うことの大切さを、フランスの社会学者リュック・ボルタンスキーが説いている。1999年に出版の『distant suffering』がそれだ。情報社会においては、多様なメディアで取り上げられる他者を、まるでそこにいるかのように自らの環境に引きつけて周囲の人々と語り合うことが大切だという。実は「まわしよみ・イスラーム」もその実践の一つだ。(編)
