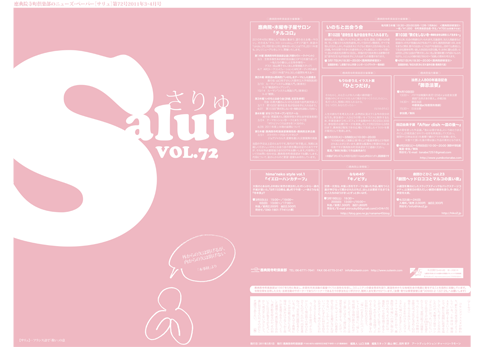
サリュ 第72号2011年3・4月号
目次
レポート「コモンズフェスタ2010」
コラム 大河内大博さん(NPO法人ビハーラ21事務局長)
インタビュー 尾角光美さん(Live on代表)
編集後記
巻頭言
外からの矢は防げるが、内からの矢は防げない
「本事経」より
Report「接」
他者の思いに接し、私を見つめる。共感が響き合うコモンズフェスタ
私をひらく、多様な場と機会
この数年、1月の恒例となった「コモンズフェスタ」が終了いたしました。今年のテーマ「onとoffのスイッチ~私をひらく6つのチカラ」には、普段は関心を向けないこと、あるいはあえて閉ざしてしまっていることにスイッチを入れていきませんか、という問題提起を込めました。そこで、副題に込めた、記憶、語り、誓い、場所、型式、身体の6つのチカラを手がかりに、大小13の企画を紐解いていきます。
(1)記憶 : 想起と忘却のスイッチ
私たちは日々の暮らしで、何かを思い出し、何かを忘れていきます。今回は、自らが蓋をしてしまっている悲しみに接近していこうと、箱庭療法、演劇体験学習、映像制作の3つの催しを実施しました。実際に誰かと場を共有し、手を動かし、身体を動かし、道具を使うことで、物体や風景を通じ、普段は思わない何かに思いを馳せられたようです。
(2)語り : 発話と傾聴のスイッチ
以前、朝日新聞のCMで「言葉のチカラ」を信じる、というものがありました。しかし今回は、あくまで言葉は道具であるとして、それをどう使い、使われるべきかに迫りました。読書会では「頭の体操」を、2つのセミナーでは物事を語り位置づける上で視点の切り替えが必要なことと、他人の生み出した物語を借りることの面白さを味わうことができました。
(3)誓い : 拘泥と刹那のスイッチ
人は時に、執拗に何かに対して長きにわたる執着をし、一方で束の間の出来事に大きな影響も及ぼされることがあります。そうした時間の長短に対して何を思うのか、「いのち」をテーマとした詩作と、自分にとっての「色」を選び抜くことなどから迫っていきました。終了後、両方に参加した方から、「個人作業だが、同じ作業を全員が同じ場でするのが興味深かった」との感想をいただきました。
(4)場所 : 開放と閉鎖のスイッチ
應典院はお寺をまちに開いていることで注目されますが、いかにして空間を開くか閉じるかは、その空間に流れる時間をどう演出するかに委ねられています。そこで、今回のコモンズフェスタでは、應典院の1階を毛糸で、2階を紙と布で、それぞれにまとうことといたしました。思い出の象徴としての白いノートから続く、色とりどりの毛糸は、人それぞれの多彩な人生を重ねています。これらの毛糸はお箸によって編み上げられ、会期中には来場者の方々の協力により、文字通り、多様な表現をまとうことになりました。
(5)型式 : 継承と創造のスイッチ
お寺による儀式も含め、一定の作法が受け継がれ、しかし新たな方法が模索されることで、自らの悲しみや苦しみが救われることがあります。今回は僧侶による社会活動の意味を問い、成人式の意義をひも解き、クラシック音楽に重ねられる先入観を解体していきました。
(6)身体 : 作動と停止のスイッチ
演劇の應典院が本領発揮して臨んだのが、プログラムに織り込んだ2つの演劇でした。一つは、ある児童擁護施設の入所者の葬式と供養にまつわる物語、もう一つは「愛染かつら」をもとにした女性の生きづらさに迫った物語でした。ともに喪失感を丁寧に扱った、今回のコモンズフェスタならではの作品でした。
場の相乗効果
このような多彩な企画が展開されましたが、思わぬ相乗効果が生まれました。それは、1月25日、14日から16日に「太陽物語」を公演いただいた「満月動物園」の皆さんが、2階ロビー「気づきの広場」に設えられた「いのちの木」を舞台にゲリラ公演をすることになったのです。
また、1月17日の「16年目の1・17」では、15人のリレーによって、鎮魂の願いを込めて117mを越える糸が紡がれました。綿から紡いだ真っ白な糸は、企画者であり染織講師の大石尚子さんにより円形の作品に編み上げられ、30日のクロージングトークの際に披露されました。こうして、場所と担い手の掛け合いを通じて、多くの場が豊かに彩られた17日間でした。
小レポート
イラスト展に向けて
参加型公開リサーチ コモンズフェスタ会期中の22日と30日、もりわきりえさんによる参加型公開リサーチが2F気づきの広場にて行われました。「人生の終わりにひとつだけ棺桶に入れるとしたら、あなたは何を入れますか?」の問いに対して、23名がインタビューに回答。小さなテーブルの脇に置かれた、段ボールで出来た小さな椅子に腰を掛け、それぞれが思う「物」の思い出が語られました。
中には、何を棺桶に入れるかを悩み、奥に置かれた特製の棺桶に入って考える方も。その他、時折、ガラスの窓越しに大蓮寺の墓地を見つめながら話をされる方や、直接「棺桶」や「死」とは関係ない話で盛り上がる方も。しかし、それぞれに、人に話す事により今の自分のあり方を見つめ、自分の歩んで来た道を振り返る機会となったようです。
十人十色の「棺桶に入れたいもの」は、各々の想いを重ね、もりわきさんによりイラストに。作品の展示と販売は、2月22日(火)から3月8日(火)の10時~20時まで、同じく気づきの広場にて。入場無料です。ぜひ鑑賞いただき、自らの死と生を考える手がかりとなれば、と願っています。
小レポート
舞台芸術祭space×drama2011、始動!
2011年のspace×dramaが動き出しました。1997年の再建当初から開催されている舞台芸術祭ですが、当初はその名のとおりに、ダンスや音楽などの公演もなされていました。しかし、2003年にリニューアル。参加を通じて互いに経験交流を図りつつ切磋琢磨を、という意図から、若手劇団を主な対象とした演劇祭として企画、実施されてきています。そのため、本番まで、毎月1回、劇団の代表や制作担当者が集う「制作者会議」を開いています。
今年は2月16日に第1回目の制作者会議を開催。7月初旬から9月初旬にかけて、昨年度の優秀劇団「コトリ会議」に加え、コレクトエリット、激団しろっとそん、プラズマみかん、ピンク地底人、Micro To Macro、Mayの計7劇団が「競演」します。この夏もまた、ご期待ください。
小レポート
呼吸で生きる~自らの心、「息」を整えて
2月22日、谷川俊太郎さんと加藤俊朗さんの「呼吸のレッスン」が開催。谷川さんによる未発表の詩の朗読に始まり、呼吸をめぐる対談、お二人が10年間続けているという加藤メソッドを用いた呼吸のレッスン、そして会場からの質疑応答と盛りだくさんの内容でした。
「呼吸は吐いてから吸うもの」とは加藤さんのことば。ゆえに「悪い物を吐いてから吸う、というリズムを取り戻すことにより、神経、そして身体のバランスが整う」とのこと。そこで、ストレスや不安で乱れている息を整える方法を実践。140名の参加者で埋め尽くされた本堂ホールに、静かな息遣いだけが響きました。あっという間の2時間半は、谷川さんの朗読で閉会。普段、何気なくしている呼吸を意識することで、新たな気づきが生まれてくるのかもしれません。
コラム「信」
お寺の「内」と「外」との循環
病院で患者さんの語りに耳を傾ける活動を始めた時、ある師が私に「仏さんのご飯で育った者がお寺を粗末にするようなことはないように」と言葉を掛けてくれた。お寺の中だけの活動だけではダメなのだと鼻息の荒かった当時の私にとって、師の言葉は拍子抜けのようにも聞こえた。
それから、縁あっていくつかの病院での活動機会に恵まれ、未熟ながらもビハーラを啓発する役割を頂いたりするなかで、師の言葉が私にこう問いかけてくるようになった。「お前は寺から出て病院という新しい場に関わっていることだけの自己満足に陥っていないか。本来大切にすべき檀信徒にお前は一体何が出来ているのだ」と。
そんな問いに触発される形で、病院という外の世界で体験させていただいたことを、自分のお寺で檀信徒にどれだけ役立ててもらえるか、半ば自分への挑戦の意味も込めて、2007年に檀信徒のための死別体験の分かち合いの会を立ち上げた。だが、決して順風満帆の会ではなく、参加者0人の時も珍しくない。会を立ち上げて改めて思い知らされたのは、お寺や僧侶が、死別の悲しみを癒してくれるという認識を、檀信徒は持っていないということである。
そんな痛い経験から、昨今の社会参加して市民と関わることの方が、檀信徒との関わりよりも上位に置かれている傾向に対して疑問を感じ始めた。ある牧師が私に「病院で患者をケアできない者が、教会の信者を癒すことなど出来るはずがない」と逆説的に語ってくれたように、実は檀信徒に信仰を伝え実践し、いのちを共に生きることこそ、何よりも厳しい修行なのだということを忘れていた。
僧侶はもっと社会に出るべきである。その考えは今も変わらない。しかし、「外」なる社会での経験が、「内」なる檀信徒の教化へと連綿と繋がっていく営みをどれだけ紡ぎ出せるか。それが自己満足に終わらない社会実践を実現し、さらには少し大袈裟な言い方だが、崩れ行く檀家制度のなかで、僧侶が現代社会に試されている最終テストへの解答なのだろうと最近感じている。
1979年生まれ。浄土宗願生寺副住職。10年前よりビハーラ活動に従事し、仲間とNPO法人ビハーラ21を大阪で立ち上げ、2010年より事務局長に就任。ビハーラの啓発、人材育成、訪問介護事業等を行う。現在は、大阪府下の緩和ケア病棟等でスピリチュアルケアを実践する他、上智大学グリーフケア研究所にてグリーフケア専門職の人材養成に関わるとともに、自坊で檀信徒のための死別体験の分かち合いの会「がんしょう寺ももの会」を主宰。
Interview「生」
尾角 光美さん (Live on代表)
死者を思うコミュニティには人の悲しみの個別性がある。悲しみを個人に閉ざし、悲しみの連鎖を生まないよう、不安と虚無の中を生きる人々が身を寄せられる場をつくる。
▼應典院とのご縁は2008年の12月でしたでしょうか?
はい。「101年目の母の日」という文集をつくり、その関連イベントをさせていただいたのがきっかけでした。既に多くの場所で語っていますが、私は入学の2週間前に母を自死で亡くしました。母の死を止められなかった自分を責めたりもしました。しかし、もともと母の日は、亡き母をしのんだ米国の女性が、1908年に教会で白いカーネーションを配ったことが発祥と知りました。そこで母の日から100周年に、亡き母への手紙への投稿を新聞で呼びかけることにし、それ以来毎年、文集をつくっています。
▼そうした活動のテーマが「グリーフ」なのですね?
そのとおりです。グリーフとは死別などの喪失によって生まれる反応やプロセスのことです。死、グリーフは、乗り超えるものでなく、それと共に生きていくことが大切ではないか、そう考えて活動しています。こうした考えを共にする臨床心理士の宮原俊也さんと、2009年の9月から應典院で「グリーフタイム」という場を設けさせていただいてきました。よくある「分かち合い」を重視するのではなく「思い思いのとき」を大事に過ごす場づくりをしています。
▼そうした経験からの知恵が「年越いのちの村」につながっていった、と。
1月に警察庁が発表した統計によると、13年連続で年間の自殺者が3万人を越えたそうです。昨年より減少したと言いますが、年を越すときに孤独感を感じる人たちが身を寄せ合う場をつくりたい、そんな思いを秋田光彦住職に投げかけ、開催に至りました。
▼自殺未遂を繰り返して「何度も死のうと思った」という自殺念慮者の方だけでなく、発達障害を抱える方、いじめに遭った方、引きこもりの方、それぞれ何らかの孤独感を持ちながら、最後は皆さん「ここに来てよかった」と仰っていたのが印象的でした。
実は参加者5名に対して20名のボランティアの方に参加をいただきました。ですが、それぞれが支援される側とする側という関係ではなく、まさに「同じ村の民」として時間を共に過ごしていただくように工夫をしました。というのも、そうして支援をしたいと思う人たちもまた、何らかの虚無感を持っているかもしれないと考えたためです。ゲームをし、自炊のカレーを食べ、銭湯に行き、年越しそばを食べて除夜の鐘を撞く、元旦の朝にはお雑煮を食べ、書き初めを終えた後には、全員が人のぬくもりに触れあい、「もう1年生きてみよう」と思うようになっていたと感じました。
▼全国から物資や寄付の支援も届き、見知らぬ誰かに思いを馳せる、そうしたやさしさのつながりが、よい形で共鳴していたように思います。
死にたいという社会から生きたいという社会に変わっていって欲しい、そんな願いを込めて、団体名には「Live on」と掲げています。生き続けるという意味です。顔を出せない人が顔を知らない人に思いを届けることで、個人の絶望の体験が希望へと変わっていく、特に「年越いのちの村」ではそれを実感しました。
▼「次の一手」が問われますね?
場づくりでは意図に満ちすぎない、これが大切だと強く思うようになってきました。とかく支えが必要な人には「弱い人」というまなざしが向けられがちです。そうではなく、しんどそうなら関わる、ただ傍にいる、それが大事だな、と。意図は頭でつくれますが、まなざしは考えてつくるものではありません。悲しみの中から生きる力を与えてくれた多くの方のまなざしを思いながら、生きることの魂を揺り動かす関係づくりに取り組んでいきます。
編集後記〈アトセツ〉
コモンズフェスタが終わり、新たな年度を迎えようとしている。1年前は「築港ARC」が終了するということで、新たな展開に思考を巡らしていた。そうして生み出したのが、木曜寺子屋サロン「チルコロ」だった。11月に「いのちと出会う会」が100回を迎えたことで、変則日程での開催となったことと年末の休館日を除けば、予定分も含めて51の場を1年で生み出してきた。
2006年のコモンズフェスタに「場へのまなざし」というテーマを掲げたとおり、應典院では「場」への強い関心が向けられる。その背景には一風変わった寺院空間であることが大きいように思う。だからこそ、そのような空間で、どのような時間を誰と過ごすのかが問われるのだろう。
「場へのまなざし」のパンフレットでは冒頭文に、「場」とは「時間と空間の掛け合わせ」と示した。そう、場づくりとは「足し算」ではなく「掛け算」の発想を必要とする。したがって「0」や「マイナス」の要素を持ち込むことを避けなければならない。しかし、だからといっていたずらに何かを持ち込みすぎても、身の丈に合わなくなることもある。
今、2010年度の「チルコロ」という場は我々の身の丈に合うものだったのか、内省を重ねつつ、次年度の展開を考えている。長く一橋大学で教壇に立った伊丹敬之先生によれば、場は「生成」だけでなく「かじ取り」が重要であるという。こうした議論では、誰が場を生み出し、誰が舵を取るのか、その担い手に注目が集まりがちだ。しかし「葬式をしない寺」として、誰に何をするのか、その点にこそ誠実でありたい。(編)
