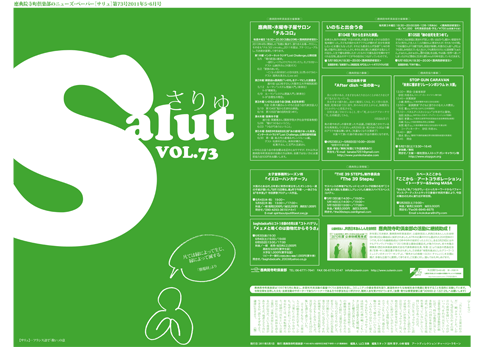
サリュ 第73号2011年5・6月号
目次
レポート「東日本大震災・祈りの市民集会」
コラム 稲場圭信さん(大阪大学大学院准教授)
インタビュー 弘本由香里さん(大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所特任研究員)
編集後記
巻頭言
縁によって滅する凡ては縁によって生じ、
「勝鬘経」より
Report「祈」
東日本大震災から一ヶ月、ただ「祈り」を捧げた一日。
忘れないための一日
「3・11」、この3つの数字は「1・17」や「9・11」と同じく、私たちの胸に深く刻まれるでしょう。3月11日に発生した東日本大震災は、現代社会に潜んでいた影の部分を、むごたらしくさらすことになりました。経済合理主義によって得てきた暮らしの姿は、果たして私たちに幸せをもたらしえるものだったのか…。その一方で、被災された方々に対して、被災地以外に生きる者ができることは何か、この問いを應典院が受け止め、應典院寺町倶楽部が事務局となり、4月10日に「東日本大震災・祈りの市民集会」を開催いたしました。
「ただ祈る場所があってもいい」「あの日を、あの悲しみを忘れないためにも、場が大切だ」「何ができるかわからないが、何かできるはずだ」「報道に一人で一喜一憂するよりは、もどかしい気持ちを互いに分かち合えないか」…4月10日の「祈りの市民集会」には、こうした思いを折り込み、「Pray from West」と掲げて実施することにいたしました。直訳すれば「関西からの祈り」という意味です。今回の震災では阪神・淡路大震災(1・17)の経験や、その教訓から、ということが前に立ち、「何かしたい」という思いを「被災地の、被災者のためには、今は待つときだ」と、どこかで抑止せざるをえない状況が長く続きました。もちろん、この背景には、被災範囲があまりにも広いということ、また、そうした広範な被災地の一つひとつの集落に、多様な文化的背景があったためでもあります。
そこで、「祈りの市民集会」では、地震発生時刻の14時46分に「311本のろうそくで、鎮魂の場をつくる」ことといたしました。そして、その前後に、應典院流の多彩な内容を盛り込み、亡くなった人・ものへの哀悼を、今なお続く状況にはお見舞いを、そしてそうした思いを寄せる私たちが今ここに確かに生きていることへの感謝の意味を込め、本堂ホールに集い合いました。ロビーでは、NPO法人Co.to.hanaの皆さんによるメッセージ募集「シンサイミライノハナ」、研修室Bでは谷町九丁目の「あいね」によるフェアトレードカフェも開設されました。合計で7時間半の長きにわたる催しの開会と閉会の際には浄土宗の儀式に則り、秋田光彦住職により追善供養の法要が執り行われました。
考えるのではなく考え抜く
午前中は発災直後に被災地に入った写真家から提供を受けた写真のスライド上映を行い、続いて現地で支援活動に取り組む宗教者(川浪剛さん)と研究者(関嘉寛さん)からの報告をいただきました。その後、詩人(上田假奈代さん)による手紙と詩の朗読、そして集会の呼びかけ人を代表して秋田住職から、この場に込めた趣旨が伝えられ、地震発生時刻を前後して、311本のろうそくによる献灯と、参加者の皆さんによる献花の時間となりました。その後は京都に事務局があるNPO法人アートNPOリンクによる「アートステージ」として、舞踏家の山田珠美さんの踊りと、現地の劇場支配人の取材映像の上映、そして改めて「表現とは何か」を語り合いました。最後は冒頭で上映した写真を撮影された山田直行さんによる講演で幕を閉じました。
終了後、参加された方から「こういう場があると、胸騒ぎが収まる気がします」といった声をいただきました。「あらためて現地へ思いを馳せる静かな時間を持てた場に感謝します」という言葉も得ました。これから日本社会は大きく変貌していくでしょうが、その構想を考え抜くためにも、祈りは出発点として欠かせないものではないかと感じました。
引き続き、應典院寺町倶楽部では、第四木曜日の「復興寺子屋」をはじめ、この災害を忘れないための場を設けます。ぜひ、多彩な方々と共に、多様な可能性を探り、かたちにして参りたく思います。
小レポート
應典院木曜寺子屋サロン
「チルコロ」第二ステージ2010年度から始めた週替わりで展開していくトーク企画、應典院木曜サロン「チルコロ」。2011年度、第二ステージに入りました。第1週は統一テーマ「Lost Challenge~喪失からの挑戦」に基づいたインターネットラジオの収録。第2週は個人の<いのち>と社会の制度を紐解く読書会。第3週は恒例「いのちと出会う会」。第4週は関西学院大学の関嘉寛先生による「復興寺子屋」。そして第5週はインターネットラジオ「Lost Challenge~喪失からの挑戦」の特別編として應典院寺町倶楽部会長の企画による「あの劇場があった風景」です。
チルコロとはイタリア語で「仲間」という意味です。ぜひ、旧知な方とも、新たな方とも、仲間づくりの機会となっていただければと思います。ちなみに今年度から應典院寺町倶楽部会員の皆さんは無料!(ただし、第3週の「いのちと出会う会」は会員優待料金での有料参加です) ぜひ、毎木18時半、多様な出会いと学びの場に関心とご参加を。
小レポート
浄土宗大蓮寺の塔頭、14年の軌跡…「呼吸するお寺」の挑戦を紐解く
2月17日、應典院代表秋田光彦による新著「葬式をしない寺」が新潮新書から刊行されました(207ページ・700円+税)。1997年の落慶から14年、「開かれたお寺」としての実践を書き綴った本書。お寺本来が持つ力と信頼を取り戻すためのいくつもの試み、そして今、社会から求められるお寺とは何かを問うています。
「場」の根源的な意味を問い直し、そしてその應典院という場所で、人との出会いとつながりを見つめてきた秋田代表が、お寺に重ねる思いとは…? 一人でも多くの方が手にされて、應典院の呼吸を感じていただければと願う、そんな一冊です。
小レポート
魚の骨を通じた自己との対話
4月23日(土)から田辺由美子さんの個展「After Dish~皿の後」が2F気づきの広場で開催されました。一見レース編みのようにも見える、幾何学的な世界観の作品ですが、よく目を凝らしてみるとそれらは魚の骨やにぼしの頭で構成されているという展開に圧倒されます。骨の一つひとつは田辺さんが食べられた後、洗浄、脱脂、乾燥を経て白く着色されたものとのこと。
これは、骨の形を鑑賞、そして感謝することで「日常見過ごされていること、骨=「死」からのアプローチで「生」を再確認」する試みです。しかし、決してグロテスクではなく、繊細で美しく、会場からガラス越しに見えるお墓の風景もあいまって「死と生」を想う崇高な時間へと誘ってくれます。無機質性と生活感の重なりが何とも玄妙な展示です。
コラム「縁」
東日本大震災と宗教者丸ごとのケアと新たな縁の創出
東日本大震災の2日後、私は研究仲間に呼びかけインターネット上に「宗教者災害救援ネットワーク」を立ち上げた。情報を共有・発信し連携する場だ。ボランティアをしている宗教者の中には、ネット上の情報を見て、自分ひとりではない、社会が見てくれている、エールを送ってくれていると感じている人もいる。また被災地に向かえない人たちも、サイトをみて苦難にある人たちへ心を寄せ、活動をしている人と心をともにしている。
僧侶が被災地への物資輸送から火葬場での読経奉仕まで様々な活動を展開している。被災者の受け入れをしている寺院もある。地域の文化・つながりを尊重しつつ、現地の宗教者が地域を立て直すのを後ろから支えるという形の支援も大切であろう。
宗教者の支援活動は社会に大切な何かを呼び起こしていると感じる。日本人の多くは自分は無宗教と思っているが、先祖に対する感謝の念や神仏や世間に対する「おかげ様」という思いは生きている。この「無自覚の宗教性」も支援の輪が広がっている背景にあろう。
一方で、公共施設の中に僧侶が入っていけない、弔うことができない。このような現実の厳しさを僧侶は痛切に感じている。僧侶は日常的にどれほど社会に関わってきたのか。
私は、「心のケア」ではなく「丸ごとのケア」が必要だと主張している。地域のつながりを奪われ、家族を無くし、あらゆる縁を失った人たちが、これから生きていく、その生を丸ごとケアする。苦難にある人を思いやり、苦に寄り添うのが宗教。宗教・宗派を超えて、また、信仰の有無を超えて連携して支援にあたることが肝要だ。未曾有の大災害に宗教者も社会も「新たな縁」を模索している。
3月6日、シンポジウム「共生社会と宗教~利他の実践は社会を救済するか?」(同志社大学ソーシャル・イノベーション研究センター、浄土宗、きょうとNPO センター主催)が開催された。宗教の社会的実践、公共性などが議論されたシンポジウムから5日後の大地震。今、宗教者の生き方が問われている。
1969年生まれ。宗教社会学者。専門は利他主義・市民社会論、ソーシャル・キャピタルとしての宗教、宗教の社会貢献研究。東京大学文学部卒、ロンドン大学大学院博士課程修了、博士(宗教社会学)。ロンドン大学、神戸大学等を経て2010年4月より現職。著書に『思いやり格差が日本をダメにする』、『Altruism in New Religious Movements』、『社会貢献する宗教』共編著、『The Practice of Altruism』共編著などがある。『宗教と社会貢献』(http://ir.library.osaka-u.ac.jp/web/RSC/) 編集委員長。東日本大震災後、黒崎浩行國學院大學准教授らとともに「宗教者災害救援ネットワーク」及び「宗教者災害救援マップ」を立ち上げて運営。「宗教者災害支援連絡会」にも参画。
Interview「復」
弘本 由香里さん (大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所特任研究員)
災害からの復興のためにも、地域・社会のありように応じて、日常と非日常とを往還する仕掛けや媒体が求められる。個人と地域・社会の物語の回復、持続的発展、それらのためにも…。
應典院での「Pray from West」の呼びかけ人に手を挙げた。「何かせずにはいられない」との秋田住職の思いを汲みとっての賛同であったという。「今回の震災では、阪神・淡路大震災との比較や、無縁社会といった問題が重ねられますが、東北という土着性が強い地域に対して単純に都市の論理を当てはめてはいけないと思っています。」高校生まで山口県岩国市で暮らした後、筑波にて芸術学を学び、多様な職業を経て現職に就く中で、画一的な都市の文脈で語れない地域の営みこそ大切にされるべきだ、と思いを寄せている。
「大学では総合造形という最も訳の分からないとされていた現代アートを専攻しました。しかし、ビデオアートやホログラム、またパフォーミングアートや野外環境彫刻など、ミックスドメディアやインスタレーションの最前線に触れ、芸術とは何かを考えさせられました。思えばそこで、アートと社会は不可分だと強烈に感じたんです。また、個人の表現も表現の技術も、社会と無関係ではないな、と。歴史・伝統と現代の関係もしかりです。」卒業後は東京で働き始め、後に関西に移り、1992年1月より大阪ガスエネルギー・文化研究所(CEL)に勤務し、1995年の1月17日は宝塚市で迎えた。
「関西に移ってから、東京で大正5年に創刊という前史を持つ雑誌『新住宅』の編集に携わりました。それがバブル崩壊とともに事実上廃刊になって、同誌の資源を活かすべくCELで研究活動に携わることになったんです。」大阪市立住まい情報センターの開設業務をはじめ、各種の業務に携わる中、一環して生活文化の視点から社会を見据えてきた。「生活文化とは、利便や収穫などの恵みを得ることの代わりに、犠牲にするものやリスクが必ずあることを自覚し、その矛盾といかに共存して暮らしの枠組みを調整するかを物語る知恵だと思います。その意識が薄れていくと、結果として人間が技術や社会の脅威に対して耳目を塞いでしまうことになります。」
今次の大震災では、技術や生活文化への敬意や畏敬の喪失と乖離が特に気になった。「本来、技術と生活文化は一対で存在してはじめて価値あるものとなりますが、リスクを排除しようとするあまり、矛盾に向き合う生活文化の力が希薄になりつつありました。両者の断絶を回復していくために、日常を揺さぶって矛盾を顕在化させ、同時に時を越えて寄る辺となるものを実感させる、その橋渡し役としての伝統文化を含めたアートの力はとても重要です。筑波大学を退職した後に淡路島の一宮町で芸術村計画を進めた山口勝弘先生は、阪神・淡路大震災の直後、第一声として『山と海はある、それは動いていない』というメッセージを発しています。私もそれに勇気づけられたのをよく覚えています。」
相次ぐ報道の中、被災者と呼ばれる人たちのことも気がかりだ。「災害の後、家や身近な人間関係を失い、職も断たれた身にはアイデンティティクライシス、人生の物語の断絶が起きます。そして、応急的にまとった被災者というアインデンティティを脱ぐことさえ怖くなっていきます。だからこそ、日常の多元性、主体性、能動性を回復する入り口として、芸能・芸術やさまざまな表現活動が果たせる役割は大きい。」
自分の感情を抑制している中では泣く事もままならない。阪神・淡路大震災のときに被災者となっていた過程を今、思い返す。「日常を取り戻すとは、何気なく笑ったり泣いたりできるようになること。そのためには、その場に応じた感覚、温度、ルールで接することが必要でしょう。それこそ、アートや表現の回路を現場に提供する意味かもしれません。」
編集後記〈アトセツ〉
「共生という言葉は厄介だ」一瞬、ドキッとした。しかし、なぜ厄介なのか、その発言の意図を聞いて、合点がいった。それは「共生という言葉を使う側は多数派の側に居て、時に少数派に対して多数派への同化を無自覚に求め、むしろ共に生きる可能性を奪っていないか」という問いかけであったのだ。
「共生」を「キョウセイ」と読むのか「ともいき」と読むのかで意味合いが異なると浄土宗は言う。「キョウセイ」は、天地自然の恵みを大切にして、互いに助け合いながら生きよう、という意味に捉える。一方で「ともいき」は、過去から未来へつながっている時間軸の中で、個々の〈いのち〉は一人のものではないと捉える。すなわち「キョウセイ」とは同時代の横の軸、「ともいき」は時代を超えた縦の軸、そうした概念の違いがある。
東日本大震災を経て、社会の動態は自ずと変わるだろう。その際に、言葉はどのように役立つのだろうか。むしろ、祈るといった個人の行為を集団の行動にしていくことが大事ではないか。なぜなら、それが地域を、社会を再起動させられるかもしれないからだ。実はそんなことを4月10日の集いを通じて感じていた。
言うまでもなく、言葉は人々の動きを左右する。しかし、言葉にこだわりながらも、なぜこだわっているのかを忘れては、本末転倒だろう。冒頭の「共生という言葉は厄介だ」には、世界を語る言葉が、言葉の世界にとどまるのが厄介だ、という背景がありそうだ。他者とどう共に生きるか、語りすぎぬよう、謙虚に生きよう。(編)
