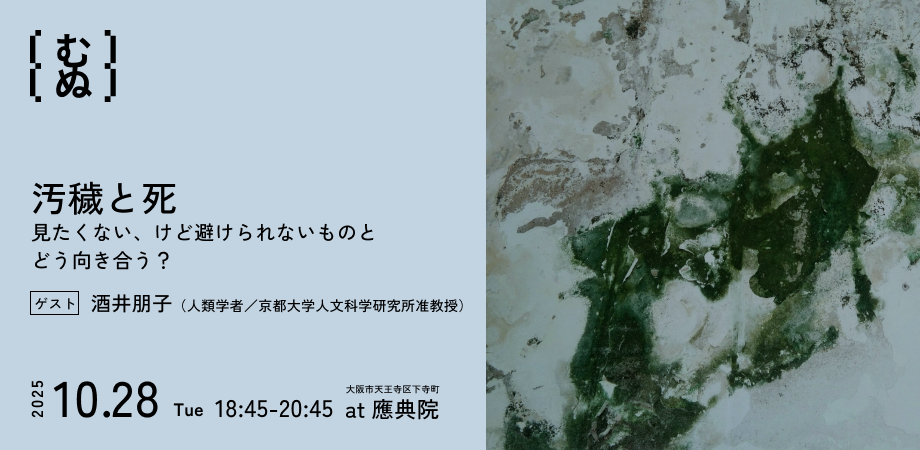
2025/10/28 むぬトーク vol.4「汚穢と死 ――見たくない、けど避けられないものとどう向き合う?」ゲスト:酒井朋子(人類学者)
「死」と向き合うことは、世界との関わり方を問い直すこと
ふとしたとき、「死」について考えることはありますか?
身近な人の死に向き合うとき、多死社会の訪れを感じる知らせを聞いたとき、自分のこれからを想像したとき、思い出の品を手放すとき。日常生活で様々な「終わり」に遭遇しますが、じっくり向きあい、話しあえる機会はなかなかありません。
「死」について語ることは、「生」を考えることでもあります。
『むぬトーク』について
『むぬトーク』は、現代における「生と死」をめぐる対話型トークイベントです。
「生と死」は誰にとっても避けられないテーマであり、社会全体の未来を見通すレンズにもなります。AI/VRの発展、多死社会、気候変動や災害、生物多様性の危機———こうした変化のなかで、私たちは「生と死」にどのように向きあえばよいのでしょう。
AI技術による死者の再現やグリーフケア、生類供養、風景に込められた記憶と継承などのテーマを横断し、むぬトークでは、独自の知見や経験を持ったさまざまな研究者・実践者をゲストに迎え、こうした幅広い観点から対話を深めていきます。また、参加者同士の対話の時間も大切にしながら、共に思考を深める場をつくります。
『むぬトーク』の名前は、2024年に開催された「産む」から「死ぬ」までをテーマとしたイベント『むぬフェス』に由来します。このイベントの背景を引き継ぎ、定期開催の対話の場として生まれ変わりました。
見たくないもの、触れたくないものとわたしたちはどう向き合うか?
家の中を自動で清掃するロボット、菌を完全に除去する消毒・殺菌の技術、見えないところで機能する下水処理やごみ処理のインフラ、そして死を遠ざける医療・延命技術。人間社会は、不浄・死・腐敗・ゴミなど「避けたいもの」を排除する仕組みや技術を発達させ「汚いもの」や「不快なもの」を視界から消し去り、見なくても済む社会をつくり上げてきました。
しかし、それらは本当に私たちから切り離せるものなのでしょうか。
腐敗や死、汚れは、生命の循環や私たち自身のいのちと深く結びついたものでもあります。
今回の「むぬトーク」では、『汚穢のリズム』(青土社、2023)の代表著者である人類学者・酒井朋子さんをお迎えし、現代社会が遠ざけてきた汚穢や死との向き合い方を考えます。
汚穢をどう受け入れるか、日常と死生観はどうつながるのか――。
避けたいものと共に生きるための態度を、参加者と共に探っていきたいと思います。
こんなことに興味関心がある方におすすめです!
・ケアと自身の死生観を現代の文脈で再構築したい
・対話を通して自身の思考・問いを深めたい
・「生と死」など、普段話す機会のないテーマで、気軽に話せる場を探している
・汚れや死といった「避けたいもの」との向き合い方に関心がある方
・日常から「生と死」を見つめ直すヒントを探している方
・仏教思想や民俗学、人類学的な視点を取り入れながら、現代の営みを読み解きたい
ゲスト:酒井朋子(さかい・ともこ):専門は人類学(人類学者/京都大学人文科学研究所准教授)
研究テーマは「危機とともにある日常」。調査フィールドはイギリス、アイルランド、東北地方東部。長期紛争の日常的経験と記憶、公害など危機的な環境変容のなかでの衣食住の営み、そして生活のなかでの汚穢や異物のあらわれと汚穢忌避について調べ、考えている。近年の著作に『汚穢のリズム——きたなさ・おぞましさの生活考』(左右社、2024年、奥田太郎・中村沙絵・福永真弓との共編著)。
当日の流れ
・イントロダクション
・ゲストからの話題提供
・参加者同士での対話
・対話の全体共有
・クロージング
※上記は変更になる可能性もありますのでご了承ください。
出来るだけ参加者の皆さんとの対話の時間を多く設けたいと思っています。
開催概要
日時
2025年10月28日(火)18:45~20:30
場所
應典院
ゲスト
酒井朋子さん(人類学者/京都大学人文科学研究所准教授)
定員
20名
参加チケット(必須)
参加チケット 500円 ※必須
お布施(任意)
参加は出来なくてもお布施というかたちで応援いただく方法もございます。
お布施 500円 ※任意
お布施 1,000円 ※任意
チケットのお申込について
以下、Peatixよりお申込みください。(クレジットカード・コンビニ決済・PayPal対応)
※現金でのお支払いは受付しておりません。
ご参加にあたっての注意事項
・欠席される場合はキャンセル待ちの方に参加枠をお譲りしたいと思いますので、欠席が決まった段階で早めにご連絡をいただけると幸いです。
・定刻で始められるように5〜10分前の入場にご協力をお願いいたします。
※上記にご了承いただける方のご参加をお願いいたします。
お問い合わせ
あそびの精舎|應典院:asobi.outenin@deepcarelab.org
背景と体制
本イベントは、「あそびの精舎」構想に関連した企画です。 仏教・アート・ケア・教育…多様な視点と活動から、 あそびを通じて、いのち・生き方・暮らしを分かちあう「ライフコモンズ」を都市に育みます。
あそびの精舎
「あそびの精舎」は應典院が一般社団法人Deep Care Labと協働で立ち上げた拠点づくり構想です。子どもからお年寄り、祖先や未来の世代が集い、ともに「あそぶ」ことで、いのちのつながりに気づき、今の生き方を見つめ、生まれ死ぬまでの、暮らしをともに支えていく。その3つのLifeをふまえた「ライフコモンズ」の拠点へ。仏教思想をベースとして、日常の居場所から、ケアと教育、子どもと家族、老いや死生観といったテーマでのマルチセクター協働につながるリビングラボへの展開をめざしています。
https://asobi.outenin.com/
一般社団法人Deep Care Lab
祖先、未来世代、生き物や神仏といったいのちの網の目への想像力と、ほつれを修復する創造的なケアにまつわる探求と実践を重ねるリサーチ・スタジオです。人類学、未来学、仏教、デザインをはじめとする横断的視点を活かし、自治体や企業、アーティストや研究者との協働を通じて、想像力とケアの営みが育まれる新たなインフラを形成します。https://deepcarelab.org/
主催・企画運営
主催:應典院
企画運営:一般社団法人Deep Care Lab


