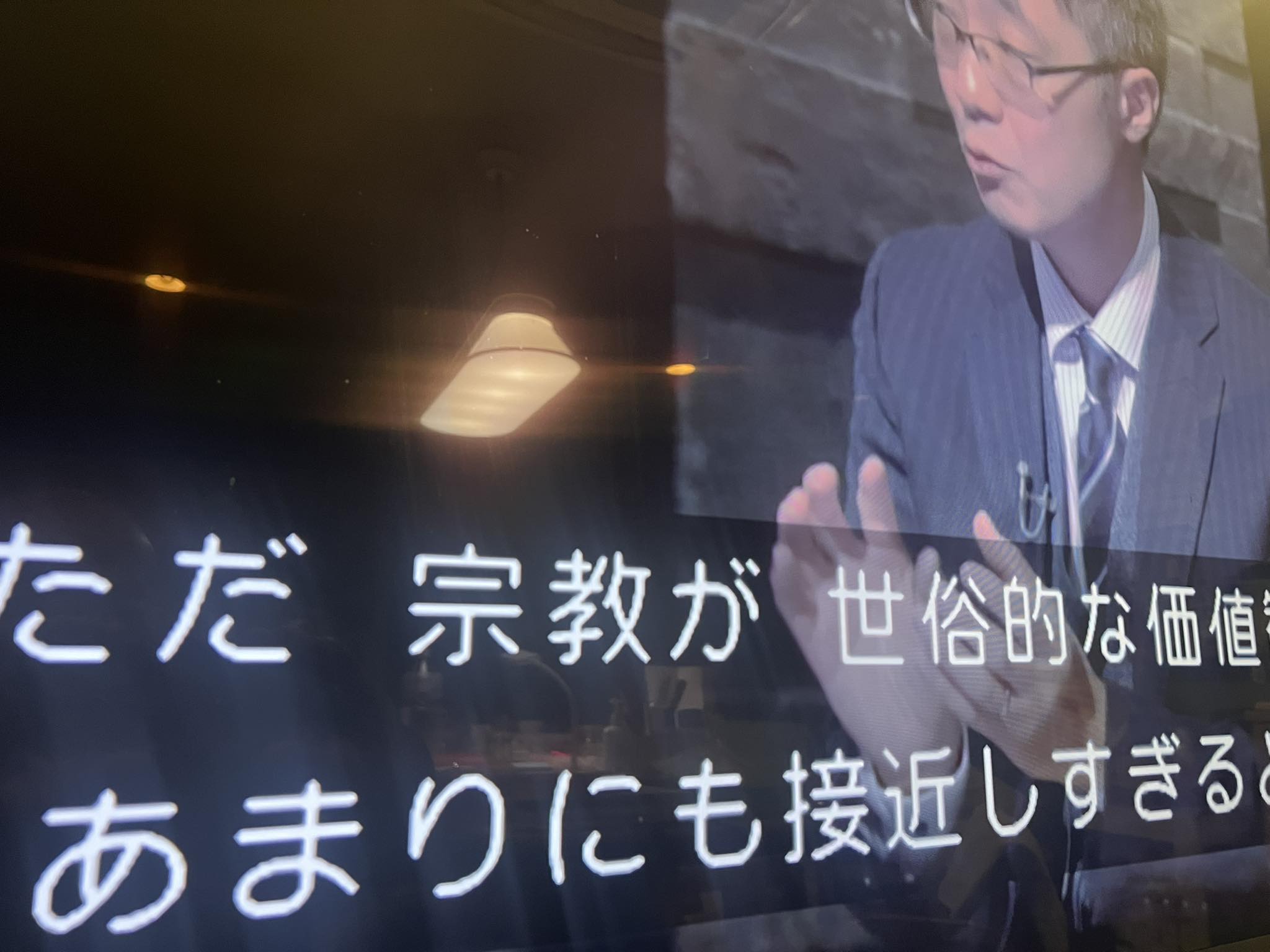
2026/2/1【住職ブログ】やりがいと、わりきれなさを往復しながら「宗教の社会貢献」を再考する
「(オウムのような)社会的な問題を起こす悪い宗教があって、一方に社会貢献をする良い宗教があるというような構図に、若干のモヤモヤ感がある」
これは、NHK「こころの時代 徹底討論」(昨年12月21日放送)における、駒澤大学の永岡崇さんの発言である。また、反社会的宗教は当然処罰の対象となるべきだとしたうえで、次のような問いを投げかけていた。
「社会に迷惑をかけず、人々のニーズに過不足なく応えるサービスを供給することが、果たして宗教に期待されている役割なのか。宗教が社会の世俗的な価値観に従属していくことで、むしろその価値観を問い直したり、相対化したりする力が弱まってしまうのではないか」(要旨)という危惧である。
番組の中では、宗教者による災害支援やケア、子ども食堂などの実践が例に挙げられていた。いわゆる「宗教の社会貢献」である。永岡さん自身はそれらを一概に批判しているわけではないが、その背後にある構図への違和感を率直に語っていたように思う。
この指摘は、とても重要だと思う。番組ではその後の「戦争責任」へと関係づけがあるのだが、それはさておき、宗教が「世俗的価値へと過度に接近していくことへの違和感」には、うなずかされる部分がある。とりわけ社会的活動に熱心な宗教者であればこそ、そうした自己懐疑の視点を内に持っている必要があるだろう。
一方で、「宗教の社会貢献」という文脈も、この30年のあいだに、時代と呼応しながら大きく変化してきた。
阪神・淡路大震災と東日本大震災とでは、宗教者の立ち位置や社会からの関心は明らかに異なっているし、インターネットが共通言語となった現代において、「世俗的」な手法や表現はいい意味で洗練されてきている。もはや宗教の社会貢献は、単に公共サービスに与する行為ではなく、むしろ、宗教者や寺院が社会と接点をもつための一つのインターフェースになりうるものと考える。
そこで問われるのは、個々の活動の是非というよりも、活動を通してどのような関係性が生成されているのか、そこからどのような宗教性が立ち上がってくるのか、という点ではないか。またさらに重要な点は、社会貢献の現場において、宗教が社会の中で(他者とかかわりあい、対話や協働をする中で)、自らの存在理由をあらためて問い返す機縁となっているか、ということだ。番組後半で島薗進先生がおっしゃっていた「他者との出会いの中で、元気が出てくる」という言葉は、その意味をおおらかに表しているように思えた。
では、社会の価値観を相対化する宗教の力とは、具体的に何か。常識を問い直し、固定化された視点を揺さぶり、時に秩序から距離を取る。でありながら、「カルト」とは異なり、市民と――檀信徒に限らず――相互理解の可能性を保ち続ける宗教のプレゼンスとは、どのようなものなのか。前回述べた「宗教的価値」の実体にもつながる。
自身は、「宗教の社会貢献」を進めている自覚はあるが、だからこれが結論というわけではない。宗教が社会に寄り添うことと、社会に対してクリティカルな存在を保つことは、どちらかが正解なのではなく、その緊張関係の中にこそ宗教のリアリティが宿るのだろう、と思う。社会貢献が宗教を世俗へと回収してしまう危険がある一方で、社会と交わろうとしない宗教もまた、閉じた独善に陥りかねない。そのあわいで宗教はいかに他者と出会い、いかに問いを投げかけ続けることができるのか――やりがいと、わりきれなさを往復しながら、これからもまたその間で揺らぎながら、考え続けていくしかない。そう思う。
