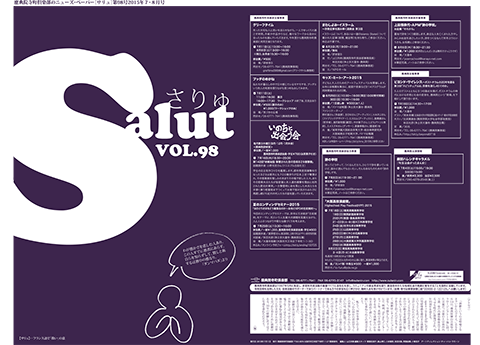
サリュ 第98号2015年7・8月号
目次
レポート「space×drama2015」
コラム 永原由佳さん(学校法人蓮光学園パドマ幼稚園教務マネージャー)
インタビュー 宮原俊也さん(臨床心理士)
アトセツ
冒頭文
report「彩」経験交流を通じた
劇団間での切磋琢磨
のびしろへの期待を込めて
1997年の再建時に始まった應典院舞台芸術祭が今年も無事に閉幕いたしました。14年目の演劇祭は、浪花グランドロマン、努力クラブ、笑の内閣、無名劇団の4劇団の参加に加えて、昨年の参加劇団から選考委員の合議で選出された優秀劇団として、がっかりアバターが演劇祭を主催する当会(應典院寺町倶楽部)と劇場側(浄土宗應典院)との協働プロデュース公演を行いました。そして、昨年度より事務局の企画として、長きにわたって公演を重ねてきている劇団を特別に招致させていただいており、今年は昨年度の劇団太陽族に続いて南河内万歳一座に協力をいただきました。こうして6つの劇団の競演により、約2ヶ月にわたって劇団と鑑賞者の出会いを通じて、表現の幅や意味を分かち合う場が創出されました。
よく「優秀劇団はどのように選出されているのか」と問いかけをいただきます。審査員と審査会自体は非公開ですが、事務局の進行のもと、審査員が全公演に対して講評を述べ、約1時間かけて討論を重ねていきます。評価の観点としては戯曲の作家性、演出に対する制作度、演劇祭への貢献度、題材の社会性など多岐にわたりますが、最終的には翌年の演劇祭において、また演劇祭までにどれくらいの発展が期待できそうかということが大きな論点となります。過去には2劇団が同時に選出されたこともあり、言わば劇団の「のびしろ」を巡って、冷静な言葉選びの中で、白熱した選考会が行われています。
無知の知への扉を開く
この舞台芸術祭は当初よりspace×dramaと名付けられています。そして、パンフレットやホームページには次の趣旨文を掲げてきました。「直径14メートル、高さ7メートルという円筒形の空間(space)に生み出される多様な劇団の多彩な物語(drama)を、どうぞお楽しみください。」このように、この演劇祭は「掛け算」による場づくりです。
掛け算と言って腑に落ちない場合は、相乗効果という表現で合点がいくでしょうか。各劇団が単独で行うだけではなしえない学びや成長を、演劇祭への参加を通じてもたらしたい、そんな願いから、この演劇祭では開幕の約半年前から、概ね月1回、劇団の代表者による制作者会議を重ねています。それにより、趣向や志向の異なる劇団間の経験交流の機会となるように運営してきました。
例年、閉幕にあたっては全劇団によるクロージングトークを開催させていただいておりますが、今年は南河内万歳一座の内藤裕敬さんより、各劇団に辛辣ながらに愛情を重ねた講評をいただきました。例えば、「(戯曲は)もっと好きに書いていい」、「作家は言葉に酔ってはいけない」、「わかりやすすぎる物語はおもしろくない」、「工夫をしたからと言って、それが新感覚とは受けとめられないことが多い」、「鑑賞者へのサービス精神が多いと、逆に引いていってしまうだろう」などです。どれがどの劇団に対して投げかけられたかは、ここでは記しませんが、こうして重ねられた言葉から、また新たな展開が生み出されることを期待してやみません。劇団の皆さんには応募から1年、ご鑑賞の皆さまには2ヶ月、場づくりへのご協力に謝意を表します。
小レポート
應典院寺町倶楽部が
浄土宗平和賞を受賞
去る5月11日、應典院寺町倶楽部が、浄土宗平和協会より第7回浄土宗平和賞を受賞しました。この賞は、浄土宗の教義を広め、儀式を行うという寺院の活動にとどまらず、「社会参加する仏教」を志向し、平和活動や福祉、教育など幅広い分野で公益に資する活動を行う浄土宗寺院・教師または団体を顕彰し、支援するものです。
授賞式には4年ぶりに浄土門主伊藤唯眞猊下が御出座され、直々に賞状を授かり、これまでの活動について「寺にあって寺にとどまらず、そして寺を出て寺を離れず、という活動」と祝辞を頂戴しました。
最後に、当会顧問でもある秋田光彦住職より「お寺とNPOの協働」と題した講演があり、宗教の布教を目的とした社会団体ではない、宗教と結びつきのある社会団体(Faith-related-organization)としての決意を述べました。
小レポート
日本保育学会にて幼稚園との活動を発表
5月10日に開催された第68回日本保育学会にて事例発表を行いました。「アートと子どもの出会いとすれ違い-保育におけるアートと保育の外のアート-」と題し、應典院寺町倶楽部から齋藤と小林が「キッズ・ミート・アート」や「コモンズフェスタ」での子どものための演劇ワークショップ等の事例を紹介しました。
共同発表者である大阪総合保育大学の弘田陽介先生と栗山誠先生は、應典院での一連のプログラムが、アートを通して異なる日常を見る目を養う契機になるのではないか、と指摘しました。
小レポート
タイからのまなざしに応えて
タイのコミュニティ再興プロジェクトである「D Jung Space Project」の皆さまが、アートと若者をつなぐ日本の取り組みを学びたいと、5月11日にお越しになりました。芸術文化活動による場の創出を通じて、子どものコミュニケーション機会の提供、コミュニティ内の結びつきの強化をめざしていらっしゃる団体で、大阪市立大学の中川眞先生からのご紹介により今回ご来訪されました。特に「キッズ・ミート・アート」に対する関心が高く、多様な表現手法に触れる子どもたちに、同化ではなく異化を大事にしている姿勢に関心を向けて頂きました。
コラム「児」
創造の場をひらく
このたび、パドマ幼稚園と應典院、そして城南学園の三者が共催して行う、夏の子どもとおとなのフェスティバル「キッズ・ミート・アート2015」のプログラム企画に関わりました。この企画を應典院スタッフと相談し始めた時、大学時代にお世話になった野村誠先生のお顔が真っ先に思い浮かびました。子どもとおとなが「即興」で音やリズムを重ねて遊ぶ空間を繰り広げたいと相談し、なんと両日ともにご出演を快諾頂きました。
應典院の隣に位置するパドマ幼稚園で仕事をして、今年で11年目になります。應典院の活動には昔から興味を持っており、さまざまな方たちの講演など、いつも「なんだか面白いことをされているな」という感覚で眺めていました。「まちとお寺と幼稚園」というテーマで應典院との連携が深まった2013年度は、育児に没頭した生活を送りながらも、今までの〈教諭〉という視点だけでなく、〈母親〉という視点で子どもの育ちを考える機会となりました。混沌とした現代社会を生き抜く子どもたちには、「当たり前」と思っているものとは違う世界に、積極的に向かっていく力も必要だと感じています。幼稚園や学校だけでは培えない創造力を、地域ではぐくむ機会も求められてくるでしょう。
実は高校時代には演劇部に所属し、役者を目指した時期もありました。大学の卒業論文は『理想の参加劇を求めて』と題して、子どもとおとな全員が参加し、それぞれが持っている力を出し合うことで完成する劇のあり方について考察しました。キッズ・ミート・アートで、これまで積み上げてきたものがひとつの形になるような気がします。日常では出逢えないアーティストの方と触れ合うことで、子どももおとなも幼稚園の先生も、知らなかった世界へ感性を開き、いつもと違う自分を発見できるはずです。みなさんの五感に残る、素敵な夏の祭典にしていきたいと思っています。
永原由佳(学校法人蓮光学園パドマ幼稚園教務マネージャー)
1980年広島県生まれ。京都女子大学家政学部児童学科(当時)を卒業し、同大学院で児童文化学を専攻。近隣の小学校・保育園などで劇の公演を行い、キッズ・ミート・アート2015で「即興音楽」を担当される野村誠さんのゼミで学んだ。大学院卒業後、パドマ幼稚園の教諭となる。2012年度途中に出産、育児休暇を取得後、2014年に職場復帰。
interview「嘆」
宮原俊也さん(臨床心理士)
失った大切な人・モノに想いを巡らせながら、
ゆっくりと過ごす時間。その人らしいグリーフ
を大切にできる場を目指して。
2009年に應典院ではじまったグリーフタイムが、今年度から應典院寺町倶楽部との共同主催という新しい体制でリニューアルする。グリーフタイムとは、亡くなった大切な人・モノのことをゆっくり想うための場である。創設者のひとりである宮原俊也さんは、2012年に仕事の拠点を福島に移した時にスタッフを離れたが、今年度から再び関西に戻った。今回、本格的に復帰した宮原さんに改めてお話をうかがった。
「グリーフとは、大切な存在を亡くしたことによる悲しみの反応、そのプロセスのことを指します。僕自身が母を亡くしてから家族のケアに関心を持ちはじめて、グリーフということばを知りました。亡くなった母を想う時間は心が落ち着く大事な機会でしたが、家に帰るとテレビを見たり漫画を読んだり、あるいは携帯を触ったりと、全然ちがうことをしてしまう。つい意識が外れてしまって、なかなかその時間を大事にできないというもどかしさがあったんです。それで、亡くなった人のことを集中して想うことができる場を作りたいと考えました。」
グリーフは時間の経過とともに単純に癒えていくものではない、という。「人は人であるかぎり、大切な存在を必ず亡くします。そして、大切な存在が占めていた部分に、ぽっかりとした穴が空いてしまう。それからは悲しみの反応のプロセスと、新しく生活に適応するプロセスが並行するのですが、生活に適応する方が徐々にメインになっていきます。ただし、悲しみのプロセスを見ないようにしてしまうと、穴が空いた状態のまま生活することになる。無理に適応したふりをするのではなく、時々その人のことを思い出すことで、ぽっかりとした穴を自分なりに埋めていくことが必要です。」
グリーフの対象は必ずしも人間であるとは限らない。「人によってグリーフの対象はちがいますし、失ったのがモノであったり信念である場合もある。失った対象が自分のなかの一部を形作っている時に、人は大きなグリーフを感じるのだと思います。福島で暮らしていた時は、生まれ育った土地を喪失することの辛さを感じさせられました。」
年月が経つにつれて、宮原さん自身がお母さんのことを想う時間は減っているそうだ。「絶対量としては減っていますが、それは自然なことだと感じていて、決して嫌ではないですね。時間は減っても、母親と一緒に過ごした経験がずっと残っている感覚です。具体的な思い出というより、自分のなかの確固たる基盤を作ってもらったというか。自分なりに穴を埋めることができてきたのかもしれませんね。でも、やっぱり亡くなってない方がいいなと思うことはあります。」
最後に今年度の展開について語っていただいた。「仏教とグリーフは深く関わり合うものだと思います。お寺で行うことの意味を大切にしながら続けてきたので、應典院寺町倶楽部の皆さんにも担っていただけることが嬉しいです。また、新たにお茶会の時間を終了後に設けることにしました。福島では集会所でお茶会が開かれていたんですけど、目的を持たずにただ喋ることの大切さに気づいて…。少し皆で喋って、あたたかいお茶でホッとしてもらえたらと願っています。」
〈アトセツ〉
「演劇というのは暗喩でなきゃいかんのですよ。」去る6月14日、應典院舞台芸術祭のクロージングトーク後に伺った言葉だ。言葉の主は南河内万歳一座の内藤裕敬座長である。学生時代に旗揚げされ、今年35周年を迎える。
冒頭の発言は、space×dramaが特に若手の切磋琢磨を期待する演劇祭ということもあって示されたのだろう。劇団によって生み出される世界で、世の中の動きを直接想い起こされないようにするのが演劇であると仰ったのである。そして「演劇はシチュエーションではなく、空間なんです」と。テレビ、映画、はたまたインターネット等、表現の手段が多様化する中、なぜ演劇なのかを突き詰めて欲しい、そうした願いも重ねられての発言であろう。
転じて、何かを楽しむときに、いつかの何かの状況が今ここの世界に重ねられない方がよいのは、演劇に限ったことではない。ハンガリー出身の心理学者・チクセントミハイは世界への没入を「フロー体験」と指摘した。実際、非日常の場に浸る上で、日常の経験は疎外要因になりうる。劇場では携帯電話の電源を切るよう促されるように、場に浸る上では、その場に立ち現れる世界への集中が絶たれる可能性を減らした方がよい。
演劇が非日常へと没入する世界ならば、やはり演劇は暗喩でなくてはならなくなる。舞台に重ねた現実が各々の現実へと引き戻すためだ。日常を見つめなおすために演劇はある。35年の経験に若手はどんな魂を重ねたのだろう。(編)
