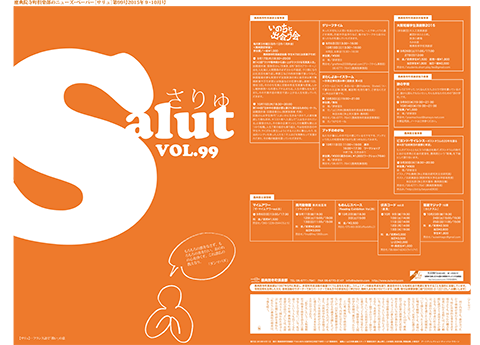
サリュ 第99号2015年9・10月号
目次
レポート「夏のエンディングセミナー2015」
コラム 蔵田翔さん(NPO法人寺子屋共育轍 代表)
インタビュー 島原夏海さん(無名劇団 座長)中條岳青さん(無名劇団 脚本部)
アトセツ
冒頭文
report「支」おひとりさまの共同体が
死生観を育みあう
身のため世のため人のため
去る7月25日、「おひとりさまをどう看取るのか~お寺とNPOの生前契約」と題し、お盆の時期の恒例事業、夏のエンディングセミナーが開催されました。冒頭、進行役を務めた大蓮寺・應典院の秋田光彦住職は「現代は支援漬けになっていないか」と問題提起を行い、単身者の最期にお寺やNPOといった地域社会の公共的な存在はどんな役割を果たせるかに迫りました。とりわけ2010年のNHKスペシャル「無縁社会」での特集以来、孤独死は無縁死と呼ばれ、個人で生き抜くことの難しさが多様な角度から論じられてきています。だからこそ、制度だけではなく、頼ることのできる相手や仲間をどうつくるか、転じて、お互いさまと言える人間関係を身の周りでどう築くかが鍵となってきているでしょう。
社会構造や価値観が大きく変化する現代を捉えるため、話題提供者には立教大学社会デザイン研究所の星野哲さんをお招きしました。星野さんは朝日新聞社の学芸部記者として、長らく市民社会の動向を取材されており、『葬送流転』や『終活難民』といった著作で知られています。星野さんからは、各種の統計や調査の結果がひもとかれ、少子高齢化、非婚化、家族葬や直葬など葬送儀礼の簡素化、これらの背景についての理解が促されました。そして、こうした状況に応えるべく「終活セミナー」が各地で開催されると共に、「エンディングノート」が活用されているものの、よい最期を迎える準備は、自分自身、世間、他人の3つの視点を重ねてしていかないと、途中で止まってしまう傾向にあるといいます。
地域交流のハブ機能を担う
本紙「サリュ」と並行して編集している「サリュ・スピリチュアル」9号で紹介のとおり、星野さんは昨年のエンディングセミナー「おひとりさま、最後の終活」にもご参加、会場から発言いただいておりました。そのため、大蓮寺で既に連携している生前契約NPO日本生前契約等決済機構(りすシステム)の特徴を改めて整理されました。星野さんによれば「人として生きていくには、面倒をかけるしかない」が、できるだけ「自分の力でなんとかしたい」人たちを支えるのが、お寺とNPOとの生前契約の意義だといいます。それにより、お寺は先祖供養だけでなく、地域交流の拠点になる可能性が高いと話題提供を締めました。
後半は会場を含めた対話の時間となりました。2002年に建立の生前個人墓「自然」を通じ、本人の遺志が反映される永代供養を追求してきた秋田住職からは、お寺とNPOの協働によって「教義に基づく宗教的ケアと、契約者どうしの交流を通じた死後の予行演習」がもたらされるため、経済的な側面だけが強調されない中で死生観が形成できると、この間の取り組みの実感が語られました。加えて「お寺が頼り、頼られてきたのは、檀信徒との宗教的結縁に基づく、しがらみの中での社会関係だった」ことに触れると、星野さんからは「地域の伝統や風俗が弱くなってきている中、お金に換算できない価値を生み出す力のあるNPOが重要」と応答がありました。会場からは「東日本大震災を機に広まった臨床宗教師の存在に期待」「病院でお墓やお葬式を一緒に考える人が大事」など、多様な関心が重ねられました。
小レポート
共に一人で
喪失感を過ごす
2009年に始まったグリーフタイムの開催形態が、今年度より変更となりました。グリーフとは特に喪失による悲しみのことを意味します。失った大切な人やモノの存在、その後の自分の人生に思いを巡らせながら、ゆっくりと過ごす場を提供しています。グリーフに目を向けたくなったとき、日常とは異なるお寺という空間で、その時々の自分を静かにそっと見つめる時間になればと願い、開催されてきました。
これまで應典院寺町倶楽部協力事業として開催されてきたグリーフタイムですが、同事務局との共同主催で行うこととなりました。これにより、スタッフ体制も厚くなり、開催頻度も増えることとなりました。グリーフタイムの担い手は、あくまで悲しみと共にお越しになる方と捉えています。そうした場づくりを支える側として、これからも変わらず皆さまが大切な存在を大事にしていただけるよう努めます。
小レポート
ことばと出会う、古くて新しい読書会
去る7月11日、「ブッダのめがね~仏教と出会い自分を見つめるお寺サロン~」を開催いたしました。本企画には昨年に引き続き、企画運営の調整役としてNPO法人寺子屋共育轍の皆様をお迎えいたしました。
参加者の方には初めてお越しくださった方や、前回お越しいただいた方もいらっしゃり、幅広く関心を寄せていただきました。「落ち着いた空間でした」「素敵な時間でした」とお褒めの言葉や、改善点など率直な意見もいただきました。これからもブッダの言葉に出会い、自分自身や日常の暮らしに目を向ける機会づくりを重ねます。
小レポート
亡き人への想いを詩に託す
8月6日、詩の学校のお盆編「それから」が大蓮寺と應典院にて開催されました。本堂での読経を終え、秋田光彦住職の法話を聞いたあと、墓地で思い思いの場所に移り、蝋燭のあかりのもと、創作した詩の朗読を聞きました。
今年の開催日は、70年前に人類に原子爆弾が落とされた最初の日。広島への想いや、今は亡き大切な人へ宛てた想いを込めた言葉が詩にのせられ、夜になっても残る蝉の声が印象的な時間でした。終了後は應典院に会場を移して、それぞれに感想や詩に託した想いを語り合う、静かな時が過ぎていきました。
コラム「鏡」
ブッダのめがねをかけてみる
私は17歳の時、高校へは入学せず、大蓮寺小僧インターンプログラムに参加し、大蓮寺と應典院で活動していました。その時、兄弟子が2006年から開催していた「ブッダカフェ」というイベントの運営に加えていただきました。2014年、應典院寺町倶楽部で「ブッダカフェ」を参考にした新企画が検討され、当時の運営メンバーと共に起業し、私が代表を務めている、NPO法人寺子屋共育轍にコーディネートが依頼されました。仏教を日常に活かす語りの場が應典院で再スタートされるにあたり、仏教から縁遠い若者たちが、ブッダという先人の知恵をお借りして自分を見つめなおす空間を作る、と理念を再定義し、「ブッダのめがね」と名前を改めました。
「ブッダのめがね」では、言葉の美術館というコンセプトのもと、ブッダの言葉を壁一面に飾り付け、会場内では話すことができない空間になっています。入り口でろうそくに火を灯し、お線香の香りが漂う落ち着いた空間で、ただ静かに言葉と向き合う。言葉の美術館が閉館してからは、ワークショップ形式で、言葉に包まれた空間の中、車座になって自分語りを行います。心に残った言葉を一枚選び、感じたことや思ったことを語りながら、空間に言葉を増やしていくようなイメージで、床にも散りばめていきます。
こういった時間を作ることで、仏教から縁遠くなってしまった若者が、ブッダの教えである「自灯明 法灯明」を疑似体験し、自分の心にあかりを灯すことができる場づくりを続けています。
最後にブッダの言葉に触れた若者の感想を紹介し、締めといたします。「思い悩むことがあって、そのことを考えたいなと、来てみた。自分の部屋より居心地がいい。 沢山いる見学者の人たちに、気をつかわず(声をかけないという空間だから)存分にものおもいにひたれるからかもしれない。で、孤独な空間じゃないし。不思議。」
蔵田翔(NPO法人寺子屋共育轍 代表)
1989年生まれ。滋賀県出身。大谷大学文学部社会学科臨床心理学コース卒業。中学卒業後、高校へは進学せず淡路島で農業をして過ごす。その後、浄土宗大蓮寺による應典院での小僧インターン生として仏教を学び、仏教を日常に活かすための語り場「ブッダカフェ」を実施。また、奈良の薬師寺にて小学生から大学生まで100名ほど集まる寺子屋の運営スタッフも経験。
2010年に寺子屋共育NPO轍‐わだち‐を設立し、2012年4月に寺子屋共育轍としてNPO法人化。共に育む教育を目指して、京都市北区にて活動を行っている。
interview「名」
島原夏海さん(無名劇団 座長)
中條岳青さん(無名劇団 脚本部)
今年のspace×dramaでは優秀劇団に選出。
母から引き継いだ劇団の新たな一歩目。
現在の心境について伺った。
應典院舞台芸術祭space×drama2015は、『無名稿 あまがさ』を上演した「無名劇団」を優秀劇団に選出し、幕を閉じた。来年度の協働プロデュース公演に向け、今回演出を務めた現座長の島原夏海さんと、脚本を務めた前座長の中條岳青さんの二人にお話を伺った。
-これまでの劇団の歩みについて教えていただけますか。
島原(以下S) もともとは学校で演劇部顧問をしていた母が、「卒業してもこのメンバーで芝居がしたい」という想いからはじめた劇団です。立ち上げ以来、作演出を手がけていた座長の中條が、2009年に「もう芝居はやらない」と言って辞めてしまい、必然的に休団となりました。私は当時大学2回生でしたが、芝居を続ける意味を完全に見失ってしまって……それから5年間は、キャリアウーマンを目指しながら中條を恨んでいました(笑)。
中條(以下N) 梅田とかで会ったらきっと殴られるな、とは思ってました(笑)。
-2014年に劇団を再スタートさせたのはなぜですか。
S 他の劇団の公演に出させていただいたことがきっかけで、やっぱり演劇が好きだと気づいて。同じ頃、休団中に1回限りの短編を上演したのですが、「二度とこの劇団で芝居はできないと思っていたのに、こうやって実現して嬉しい」という母のことばが胸に残り、2代目座長として新しい劇団員とやれるだけのことをやる、と決心しました。
N その間、僕は演劇から離れていましたが、劇団の復活公演に当日だけ顔を出したんです。正直期待していませんでしたが、島原の奮闘がひとつの希望に見えて、この火は絶やしたらあかんと思い、次に挑戦するspace×drama公演の執筆を志願しました。仕事との兼ね合いが厳しかったですが、久しぶりの復帰で楽しかったです。
-優秀劇団選出の報を聞いた時はいかがでしたか。
S とても驚きました。本当の意味で復活するには評価されないといけないと思っていたので、安心した気持ちもあります。
N 僕はあまり驚かなかったですね。自分の持ち札の中から、演劇祭で評価されるだろう要素をピックアップして書いたので、可能性はあると思っていました。
-應典院やspace×dramaについて、どのような印象を持たれましたか。
N 朝早くからお経を唱える声があたりに響いて、それが異質なものではなく、自分の生活と関わっているものだと感じられました。非現実と現実のあいだにあるお寺という場が、演劇の世界にハマっていたと思います。
S 應典院寺町倶楽部の皆さんに支えられながら、それぞれの劇団が意見を出し合って作り上げた演劇祭だったと思います。私、大変人見知りで、同年代の演劇人に知り合いがいなかったので、新しいつながりが生まれたのが嬉しくて。来年度は私たちが引っ張っていく責任も感じます。
-最後に、劇団の今後について教えて下さい。
S 来年度までに動員550人を目指しています。中條作品の他にも、劇団員共同の「みずしまみほこ」名義作品を1月に上演しますので、また異なる作風で勝負していきたいと思います。
N 中心である島原の周りに集まる人たちが、新しい無名劇団を形作っていくはずです。僕は僕なりにサポートしていきたい。来年度の公演では、評価を気にせず、もっと大胆な内容に挑戦したいです。
〈アトセツ〉
同じ内容でも、誰が言ったかで価値が変わることがある。特に具体的な事実を表す場合よりも、何らかの概念を他者に伝える際には、どの瞬間に誰がどう表現するかが鍵となる。心理学者の杉万俊夫は、言説の人称という視点から、言葉を通じた人間関係について論じている。たとえ丁寧に場面を観察しても、表現の仕方によって、思考の伝播力が異なると述べている。
少なくともこの10年、應典院では記事の執筆者の名前を明かさない方針が貫かれてきた。スタッフの誰もが應典院の立場や姿勢を語ることができるように、という志向によっている。杉万先生の視点を借りるなら、水素原子2個と酸素原子1個で水の分子1個ができる、といった自然科学の命題は誰が言っても意味は変わらない。しかし、価値を扱う人間科学の命題は、誰が言ったかで意味が変わる。
この夏、戦後70年談話が発表された。内容には立ち入らないが、21世紀構想懇談会と呼ばれる有識者会議によってまとめられたものだ。これもまた、自然科学的な命題ではない。日本国政府がどのように過去を見つめて未来を見据えたかが示された。
「私たち」という一人称複数形で物事や関係を語るのは簡単なことではない。「いや、私は違う」という人も出てくるためだ。今年度、應典院寺町倶楽部の会員のつどいでは、出席者の方々と「開かれたお寺とは」をお題に対話を重ねた。「私たち」の應典院の模索は、今後も続く。(編)
