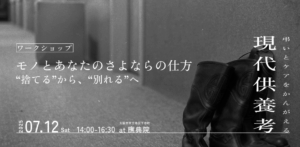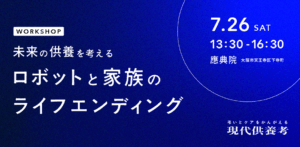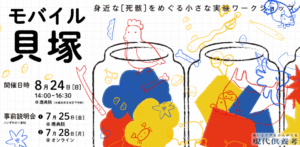2025/11/8-16 おわりのケア展 -モノ・いきもの・AI/ロボットの死と供養-
11月8日より、Deep Care Labとの共同プロジェクトとして、「
昨今、さまざまな「死」が、
こうした状況を背景に、わたしたちは、日本で静かに息づいてきた「供養」
本展示では「日常の中で無数にある”おわり/ 死”と関わり直し、ケアするには?」という問いのもとに、「
一つ目のテーマは、「モノのおわりと供養」。
古いスマホや焦げついたフライパン、役目を終えた掃除機――
二つ目のテーマは、「いきもののおわりと供養」。
漁村の魚供養碑や養蚕の慰霊碑のように、
三つ目のテーマは、「ロボット/AI/家族のおわりと供養」。
子どもを産まない選択や気候危機を背景に、
こんな方におすすめです!
・「おわり」や「死/死生観」を日常の視点から考えてみたい方
・仏教思想や供養の文化に関心がある方
・自然共生に関心がある方
・モノと循環、サーキュラーデザインの関係性を見直したい方
・AI・ロボットなど新しい存在との「別れ」に興味を持っている方
・ケアやグリーフケア、ウェルビーイングに関わる活動をしている方
・アートやデザインを通じて社会的テーマを探究してみたい方
開催概要
会期日程
2025年11月8日(土)-16日(日)
・平日:12:00-17:00
・休日:10:00-17:00
会場
應典院 ※展示・イベントはすべて2Fです
(大阪府大阪市天王寺区下寺町1丁目1−27 (google map)
※お子様連れでの来場も歓迎です。
※エレベーターもございます。
入場
無料(要予約)※関連企画は一部有料
チケット予約について
以下、Peatixよりお申込みください。
※予約についての注意※
・展示、関連イベント全てに参加チケットが必要です。(一部有料)
・当日の申し込みも可能です。
・有料企画のキャンセルによる返金は、セッション当日の3日前までとさせていただきます。
関連イベントについて
展示期間中、様々な関連イベントをご用意しています。是非併せてご参加ください。
有料・無料に関わらず、全てのイベントには参加チケットが必要です。
11月8日(土) 13:30-15:00『人間以上の死者の弔い・供養、そしてケア(仮)』
『RITA MAGAZINE2 死者とテクノロジー』も編著した中島岳志さんの最近の関心をもとに、本展示の主題である供養や弔いを人間以上(more-than-human)の死者への”ケア”の社会実践を語る。
・ゲスト: 中島岳志(政治学者)・川地真史(一般社団法人Deep Care Lab代表)
・モデレーター:田幡祐斤(Deep Care Labパートナー / 株式会社MIMIGURI)
・申込:peatixからチケット購入ください(1000円)
11月8日(土) 16:00-17:00『おわりのケアと供養を語る、振り返りトーク』
本リサーチに関わったプロジェクトメンバーが、各々の関心やリサーチのプロセスを振り返り、発見をシェアしながら「おわりのケア」としての供養について語りあう。加えて、それを元に、浄土宗僧侶の秋田光軌さんによる、仏教の視点から供養を紐解きます。
・ゲスト: 秋田光軌(僧侶)・持丸可奈子 / 西田亮太郎 / 井出明日佳 (本プロジェクトメンバー)
・モデレーター:川地真史(一般社団法人Deep Care Lab代表)
・申込:不要
11月10日(月) 13:00-14:00『ミナミ/供養のディープな風景を訪ねる』
大阪ミナミの千日前の只中にある三津寺松林庵墓地には、線香の煙が絶えない。俗界にある供養空間を手がかりに、現代人の供養の風景について加賀住職に聞く。
・ゲスト:加賀 俊裕(三津寺住職)
・会場:2F気づきの広場
・申込:peatixからチケットお申込ください(無料)
11月12日(水) 13:00-14:00『供養とスピリチュアルケアが願うもの』
宗教的供養とスピリチュアルケアは同じ地平にあるのだろうか。宗教と非宗教のケアは何が異なり、どう響き合うのか。應典院でケアプログラムを担当する宮川氏に聞く。
・ゲスト:宮川栄美子(看護師・専門スピリチュアルケア師)
・会場:2F気づきの広場
・申込:peatixからチケットお申込ください(無料)
11月15日(土) 13:00-14:00『お墓供養なんて意味はない、は本当か。』
増加する墓じまいや仏壇じまい‥若い世代の供養離れが当然のように言われるが、お墓や葬儀の相談を8000件受けてきた30代のコンシェルジュ池邊氏に聞く。
・ゲスト:池邊文香(エンディング・コンシェルジュ)
・会場:2F気づきの広場
・申込:peatixからチケットお申込ください(無料)
11月16日(日) 13:30-14:45 『モノと人との別れ方の作法(仮)』
・ゲスト:ソン・ヨンア(法政大学 デザイン工学部教授)
・会場:2F気づきの広場
・申込:peatixからチケットお申込ください(無料)
11月16日(日) 15:30-17:00『お寺リビングラボの可能性(仮)』
・ゲスト:木村篤信(地域創生Coデザイン研究所、日本リビングラボネットワーク代表理事)
・会場:2F気づきの広場
・申込:peatixからチケットお申込ください(無料)
会期中、カフェフィロ20周年の集い〜「社会の中で生きる哲学」の現在地〜 も同時開催します!
11月16日は、別企画として 『カフェフィロ20周年の集い〜「社会の中で生きる哲学」の現在地〜 』も開催予定です。
詳細は下記ページをご確認ください。
https://fb.me/e/8MxOpRu7T
背景と体制
本イベントは、「あそびの精舎」構想の具体化企画第一弾。一人ひとりに死生観を問いかけ、いのちのはじまりと終わりに向き合うことで、生き方を見つめ直し、立場も世代も混ざりながら暮らしを支えあう「ライフコモンズ」の再生をめざします。
あそびの精舎
「あそびの精舎」は應典院が一般社団法人Deep Care Labと協働で立ち上げた拠点づくり構想です。子どもからお年寄り、祖先や未来の世代が集い、ともに「あそぶ」ことで、いのちのつながりに気づき、今の生き方を見つめ、生まれ死ぬまでの、暮らしをともに支えていく。その3つのLifeをふまえた「ライフコモンズ」の拠点へ。仏教思想をベースとして、日常の居場所から、ケアと教育、子どもと家族、老いや死生観といったテーマでのマルチセクター協働につながるリビングラボへの展開をめざしています。
https://asobi.outenin.com/
主催:應典院
浄土宗應典院は、大蓮寺三世誓誉在慶の隠棲所として1614年に創建された大蓮寺の塔頭寺院。1997年に再建される際、かつてお寺が持っていた地域の教育文化の振興に関する活動に特化した寺院として計画され、〈気づき、学び、遊び〉をコンセプトとした地域ネットワーク型寺院として生まれ変わりました。2024年4月より、「あそびの精舎」構想を掲げ、再始動します。
https://www.outenin.com/
企画運営:一般社団法人Deep Care Lab
祖先、未来世代、生き物や神仏といったいのちの網の目への想像力と、ほつれを修復する創造的なケアにまつわる探求と実践を重ねるリサーチ・スタジオです。人類学、未来学、仏教、デザインをはじめとする横断的視点を活かし、自治体や企業、アーティストや研究者との協働を通じて、想像力とケアの営みが育まれる新たなインフラを形成します。https://deepcarelab.org/
研究・展示協力(モノのおわり):法政大学 Affective Design Lab
クリエーション、テクノロジー、マネジメントの専門性を総合的に取り入れつつ、社会における現実問題だけでなく少し先の未来の可能性を提案する研究室です。
※展示内容の一部はJSPS科研費23K28374の助成を受けたものです。
リサーチプロジェクト・メンバー
・川地真史 (Deep Care Lab代表理事 / 公共とデザイン共同代表)
・田島瑞希 (Deep Care Lab)
・持丸可奈子 (フリーランスデザイナー)
・西田亮太郎 (Deep Care Labインターン)
・井出明日佳 (Deep Care Labインターン)
・宮本萌々子 (Deep Care Labインターン)
お問い合わせ
一般社団法人Deep Care Labまで
mail:info@deepcarelab.org
弔いのケアを考える「現代供養考」ワークショップシリーズ
本展示に向けて、全3回のワークショップを開催しました。