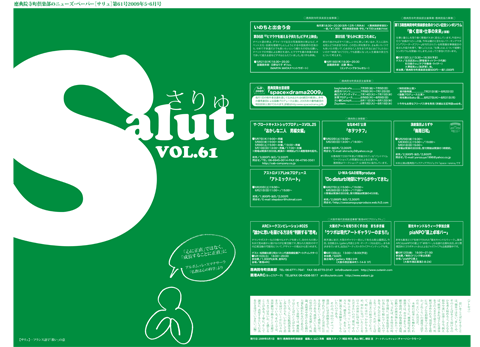
サリュ 第61号2009年5・6月号
目次
レポート「space×wave」
コラム 岡澤慶澄さん(僧侶)
インタビュー 釈徹宗さん(宗教学者・如来寺住職)
編集後記
巻頭言
「心に正直」ではなく、「成長することに正直」に
アルボムッレ・スマナサーラ「仏教は心の科学」より
Report「学」
学生演劇人技術向上ワークショップspace×wave開催
「場」が持つ「人的資源」
應典院ではこれまで協働企画の演劇祭「space×drama」、劇場側と劇団側の競作「space↓arena」、通常の作風と違う実験公演「space×labo」、これら3つの演劇関連企画が行
われてきました。この「space」シリーズに、今回新たに「space×wave」という企画が加わりました。これは高校生・大学生を含め、これからの関西演劇界を担う若手演劇人を対象としたスタッフ研修会で、3月23日から25日に行われました。命名の背景には、「space=場」から「wave=波」を起すという発想のもと、受講生が演劇界を担っていく「最初の一歩」になればという願いを込めていました。
そもそも、演劇に関するワークショップは役者対象のものが多く、裏方のスタッフに焦点が当てられたものは数える程です。また、少ないながら行われているスタッフ対象の研修は長期間のものが主とされてきました。しかし、今回のような短期集中型のワークショップが行われるに至る背景には、毎年夏に高校生が学校外で演劇をする大阪高校演劇祭(HPF:Highschool PlayFestival)の会場として應典院が使われてきたことがあります。制作、音響、照明、舞台製作、全てを高校生自身が考えて作り上げるHPFでは、危険がないように、舞台作りがスムーズにいくように、と、関西小劇場のスタッフたちが全面的に高校生を支えています。そのスタッフたちから應典院寺町倶楽部に、「スタッフがどう作品に向きあっているのかをHPFに参加している高校生たちが知ると、作品に対する姿勢や自分自身を見つめられるようになるのでは」と寄せられたことが、space×waveの「最初の一歩」となりました。
「時代の流れ」を「時代のリレー」に
講師陣はHPFのスタッフに関わっている4名、舞台監督に小林敬子さん、音響に須川忠俊さん、照明に根来直義さん、制作に桝田聖美さんが務めました。初日の23日は、高校生の部と大学生・若手演劇人の部と2つに分かれ、舞台・音響・照明・制作の部署の講師の各々のスタイルで講義が行われました。専門用語や機材の説明、仕込みの手順や簡単な演劇の歴史まで、多彩な内容を言葉を噛み砕いて説明がなされました。また、舞台上に椅子とバス停を置き、音響・照明の効果で四季を表すという、機材の操作を体験する機会も設けていました。
通常、演劇は、仕込み、本番、撤収と3~4日間をかけて行われますが、今回、仕込み、本番、撤収を一日で行う「乗り打ち」による模擬公演が盛り込まれていました。24日、25日の両日とも、参加人数に合わせて内容を変化させ、仕込みが学生演劇人技術向上ワークショップspace×wave開催進められました。それぞれによい表情を浮かべながら創り上げた舞台では、模範公演「スクラップ・ヒーロー」の上演と、同作の作・演出を務めた劇創ト社の城田邦生さんと受講生との質問コーナーが設けました。城田さんからは、作品作りに対する考え方、スタッフとの連携の重要性等について丁寧な解説がなされ、受講生からも役者とスタッフとの関係構築や、細かな演出の意図についての質問などが寄せられました。短期集中型とはいえ、朝から晩までの長丁場だったものの、疲れを感じさせない受講生の表情から満足度を伺うことができました。
終了後に受講生からは「またやって欲しい」「次回は違う部署を勉強したい」など前向きな意見が多数寄せられました。受講生の学びとともに講師陣自身の学びも大きかったようです。特に、自分たちが担っている裏方という仕事を「分解」し、受講生に説明する為に「再構築」することで、先輩の演劇人として次世代につなぐべきバトンが何かを探り出せたとのことです。「最初の一歩」として「楽しむ」ことから始めた若手が、徐々に仕事として活躍する日を、スタッフ一同、心待ちにしています。
※本事業には、大阪府芸術文化振興補助金の交付を受けました。
小レポート
集い、学び、語り、楽しむ「ちべっと寺子屋ふぉーらむ」開催
去る4月25日の26日に、「落語deチベット実行委員会」との共催で、「ちべっと寺子屋ふぉーらむ」が開催されました。この催しは、落語家の桂七福師匠によってチベット問題の創作落語の披露を中軸にして、チベット密教の高僧ニチャン・リンポチェによる法要や、清風学園の平岡宏一先生による講演、またチベットの最新映像を捉えた映画上映や、佛教大学の小野田俊蔵先生らによる音楽公演など、実に多岐にわたるお祭りとなりました。創作落語の題名には「チョビット・チベット」が掲げられました。ここには、少しのことからチベット問題に埋め込まれた事柄について知って欲しいという願いが込められています。
この催しは、應典院にて行われてきた公開勉強会等を通じて組織化された実行委員会によって企画運営がなされました。元をたどれば、2008年6月22日、「宗派を超えてチベットの平和を祈念する僧侶の会」事務局も務める長野・長谷寺の岡澤慶澄住職から應典院に投げかけられた提案が発端でした。そして、社会問題や人権問題を素材とした創作落語にも取り組んでいらっしゃる桂七福師匠の多大なる協力を得て、無関心層にチベット問題を「演じることで伝える」という挑戦に向き合ってきました。生憎の天気ではありましたが、両日あわせて150名程度の皆さんに、應典院での挑戦に立ち会っていただきました。なにわ発、世界初の「落語でチベット」を扱うという取り組みは、5月9日の長野での公演へとリレーが続いています。
小レポート
築港ARC 再び横浜へ
去る3月20日、21日、横浜で活動するアートNPO「AAN(アートオートノミーネットワーク)」さんに招かれ、2つのシンポジウムに参加してきました。1つはアートアーカイブ(芸術に関する資料)が、もう1つはアート・イニシアチブ(芸術による社会参加活動)がテーマでした。トーカーは、ヨーロッパ、アメリカ、アジア各国から招かれました。日本からは青森にてまちづくりとアートを絡み合わせた事業を展開するteco LLCの立木祥一郎さんが、そして大阪からは朝田と蛇谷が事例を発表しました。とりわけ、築港ARCにはポッドキャスト事業とアートマップ制作事業の運営形態に関心が寄せられました。このような国際的な現場で活動を報告できたことも意義深いのですが、それ以上に各国の社会状況を文化政策の面から垣間見ることができ、大変勉強になりました。
小レポート
「コミュニティ・デザイナー」に宛てた一冊
應典院寺町倶楽部では、2003年5月の「上町台地からまちを考える会」発会以来、上町台地界隈のまちづくりに積極的に取り組んで参りましたが、このたび、「地域を活かす つながりのデザイン~大阪・上町台地の現場から」が創元社より刊行されました(246ページ・2,000円+税)。本書は、大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所(CEL)による同志社大学での寄付講座「コミュニティ・デザイン論」の内容がもとになっています。通読されると、資本優先の「都市再生」ではなく、まち優先の「コミュニティ・デザイン」の手法で持続可能な地域をつくる価値に触れていただけるでしょう。應典院にもお馴染みの面々の表紙を飾り、執筆にもあたっているおすすめの一冊です。
コラム「共」
暴悪大笑無関心を喜ぶ悪魔の笑い
チベット仏教のダライ・ラマ14世は、しばしば「仏法の鍵は大悲である」と語っている。大悲はサンスクリット語ではカルナー、英語だと「compassion」というが、面白いことに、このcompassionは和訳されると大悲ではなく「共感共苦」となり、少子高齢化、格差社会が抱える諸問題を打開する鍵として、福祉や医療や教育の現場に導入されているのである。
この大悲=共感共苦を主題とする菩薩は十一面観音である。奈良のハツセのような人間性の回復、魂の再生、甦りを願う古代からの聖地にまつられる観音で、私たちの祖先は、この観音すなわち大悲=共感共苦という働きが魂を再生に導くものであると直観したのであろう。
この大悲の観音が十一番目の顔としてその背後に秘めているのは意外にも「笑い」である。私はこの笑い顔が背後にあることに関心を持っている。というのは、その背後を見ることになるのは、悲惨な人々の救済に向っていく十一面観音を「見送る人」、すなわち他者の苦難にもその救済にも無関心な人だからだ。おそらくその人は、その顔を見るや戦慄せずにはいられない。そこには、暴悪大笑という、得体の知れぬ、薄気味の悪い不気味な大笑いがあるからだ。
私は、この笑いは他者の悲苦に無関心な私たちを笑う「悪魔の笑い」なのではないかと思っている。他者の苦を傍観する人は、自分の苦も放置する人であり、悪魔はその無関心を喜び、笑っているのである。そこで十一面観音は、大悲方便によってこの魔的な笑いを敢えて示し、無関心に安逸する私たちに衝撃を与え、深い慙愧とともに共感共苦を呼び覚まそうとしているのではないか。
先頃、應典院で初公開されたチベット問題を知るための創作落語『チョビット・チベット』も、笑いを鍵として無関心層の共感共苦の扉を開く試みであった。笑いの力が、他人事を我が事に引き寄せ、瀕死の共感力を甦らせる。むろんそれは、大悲=共感共苦に根ざす笑いでなければならない。でないと、悪魔が笑う。
1967年生まれ。立命館大学文学部中退後、総本山智積院の智山専修学院にて真言宗の僧侶となる。巡礼・遍路をきっかけに、魂の浄化と再生(シラ=生まれ清まり)という日本古来の(今も変わらぬ)宗教的テーマと、仏教の観音信仰とが連結した寺作りに取り組む。寺院は「祈り・学び・遊び」のコンセプトによって人々の再生の場となると考え、伝統的な祈りとともに、講演会やイベントを企画する一方、中世の「聖(ひじり)」に宗教者としてのモデルを見出し、参加者を募っての巡礼や絵解きの復興にも関る。信濃三十三観音札所連合会事務局、宗派を超えてチベットの平和を祈念する僧侶の会事務局。チベット落語『チョビット・チベット』呼びかけ人。
Interview「説」
釈 徹宗さん (宗教学者・如来寺住職)
應典院による「つながり」を生み出す試行錯誤の歴史。お寺がまちづくりの拠点となってきた背景にある宗教性を当事者が語ることにこそ、先駆者の役割がある。
時々聞かれるのですが、お寺に対する反発はありませんでした。浄土真宗本願寺派のお寺に生まれた私は、むしろ一刻も早くお寺の仕事をしたいと考えていました。転機となったのは、龍谷大学で真宗学を学んでいた4回生のとき、指導教員から大学院進学を勧められたことです。その後、大学院も終盤にさしかかって、特に宗教を信じる人への興味を抱くようになったためです。
龍谷大学の大学院を修了すると、理論的に宗教を研究できる大阪府立大学の大学院に進学し、比較宗教思想を専門とする花岡永子先生に指導を仰ぎました。既に非常勤講師等もさせていただいていた頃でしたが、住職を経職したら、全て辞めてお寺の仕事に専念しようと考えていました。その頃、大蓮寺の住職に就かれた秋田光彦應典院主幹(当時)にお会いし、應典院が取り扱っている「関係性」という視点に影響を受けたように思います。
應典院に来ると「お寺ってこんなにおもしろいんや」と改めて感じさせられます。應典院は何かと何かをつなげる「コネクター」の役目をしている、そう思えるからです。應典院では、何も山の中で修行をしたり、特別なトレーニングをしなくても、聞こえてくる声に耳を澄ませて感じることを大切にすればいいと、應典院寺町倶楽部をはじめとするイベントの企画者たちが気づかせてくれます。イベントを通じて関係性を紡いでいくこと、それはまさに縁起の実践であり、存在論や認識論を説明する術にもなっています。
今回、「ちべっと寺子屋ふぉーらむ」に関わらせていただきましたが、イベント当日には実に多彩な方々が出会い、つながりました。実行委員の顔ぶれも幅広かったものの、参加者の中には、チベットに一年留学していた方、こどもの英語落語をしていた方、こうした方々は集めようと思っても、なかなか集まるものでありません。こうして、お寺がアートやまちづくりや行政との関わりを持って行けるのは、そもそものお寺は人々を無条件に受け入れる機能を持っているからでしょう。ただし、それはお寺の宗教性であって、社会性ではない、その点が重要です。
お寺には社会とは違う時間が流れるからこそ、そこに物語が生まれます。つまり、社会の歯車とうまく合わないという人たちが、お寺という宗教空間で救われるのです。例えば、社会はニートと呼ばれる人たちを、社会に適応できていないと位置づけることがあります。ところが應典院では、演劇や各種イベント等で、そういう人たちが受け入れられ、力を発揮しています。
宗教や哲学や思想というのは、ある意味人類の知恵の総カタログですが、應典院はそれらをフル活用し、現代社会における寺院運営の1つのモデルを創り出したと思っています。そこで、お願いしたいのは應典院で生まれた物語を理論づけ、一回きちんとまとめて欲しいということです。私は檀家さんの協力を得て、お寺の裏の民家を拠点に「むつみ庵」というグループホームを運営していますが、こちらは應典院のような都市型寺院とはまた別のモデルです。とにかく様々な寺院や人々がいろんなモデルを提示していくことが大切でしょう。そのためにも、ぜひこれまでの應典院の歩みを整理する作業を行ってほしいと思っています。なにしろ、應典院が自ら苦闘の軌跡を体系的に語ったものはまだありませんからね。
編集後記〈アトセツ〉
思いをことばにすることは、簡単ではない。ましてや、そのことばをどう届けるのかを考え始めると、さらなる悩みや迷いは深くなる。例えば、紙面であればどんな書体をどの大きさで使うのか、判
断が求められる。発話する際には、どんな抑揚をつけるのか、どれくらいの速度で話すのか、といった具合だ。
本紙の記事にも触れられているように、應典院寺町倶楽部では、お寺やまちで、演劇や落語、その他各種の表現活動の企画実施にあたっている。言わば、ある特定の時間と空間に、世界を仮設する行為に取り組んでいるのである。なんだか小難しい表現となってしまったが、ことばと間(ま)の組み立てによって、時には引っかかりも含め、何かに気づいたことを日々の世界に持ち帰っていただきたいのだ。要は、その場に立ち会っていただく方々に、膝を打つ、あるいは腑に落ちる体験をしてもらいたいのである。
その点、今回の「チベット落語」には企画側ながら、圧倒された。どんどん世界に引き込まれていく感覚に浸ったのである。落語という表現の型が持つ力を実感した。無論、表現者や受け止める側の
力量も問われるのであるが。
そういう意味では、應典院ではことばのことばかり考えている。こんな駄洒落を楽しみながらも、いかにして思いを届けていくかに日々向き合っている。その上では、美辞麗句で飾ることは避け
るべきではないか、と感じることがある。丁寧に、そして誠実に、表現するという行為を引き受けていきたい。(編)
