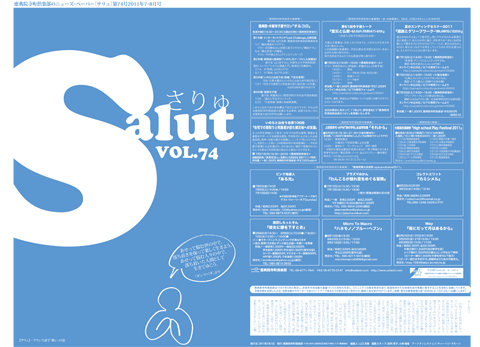
サリュ 第74号2011年7・8月号
目次
レポート「さいごのいきかた」
コラム 井上治代さん(NPO法人エンディングセンター理事長)
インタビュー 樋口貞幸さん(フリーランス・アートアドミニストレーター)
編集後記
巻頭言
あせって悩む世の中で、落ち着きを保って楽しく生きよう。あせって悩む人々の中で、落ち着いた人間として生きてゆこう。
「ダンマパダ」より
Report「根」
共同体の新しい形をつくるため、どんな結び目と橋渡しが必要か?
時代の生き方の行方
東日本大震災から3ヶ月を迎えた6月11日、上町台地からまちを考える会(秋田光彦代表理事)の協力で、應典院本堂ホールに中島岳志さんをお招きしてのトーク企画が開催されました。ある新聞では、東日本大震災の後の社会を「災後社会」と呼び、東日本大震災を経て、新たな社会の姿を見いだす必要があると問いかけました。「もはや戦後ではない」と言われて久しい日本が新たな局面を迎えたのではないか、そんな投げかけであるとも言えるでしょう。では私たちはどのような社会を、どのように生きていくのか、今回の催しはそれらを深める機会となりました。
学界や論壇で幅広く発言する気鋭の研究者で言論人の中島岳志さんを迎えての機会に掲げられた名前は「さいごのいきかた」でした。あえて平仮名にされたのには理由があります。まず、震災の後という「災後」と人生の完成という意味での「最期」の2つの意味を重ね、さらにそれぞれの個人から集団レベルの「生き方」と「逝き方」の2つの観点が埋め込まれれたのでした。大阪に生まれ、京都でアジア地域研究を進めた後、近代の日本思想に根ざす源泉を幅広く取り扱う中島さんと、関西を拠点に多様な実践的研究などに取り組む人々とのあいだで、どのような対話の場が生まれたか、紹介していくことにしましょう。
ジモト、それは「根拠地」
冒頭の秋田光彦さんの開会挨拶では、「地球にやさしくあるために、でなく、地球がやさしくあるために」という表現があることに触れ、この災害による喪失からどう立ち起こるかに関心を向けていきたいと訴えかけられました。続けて中島さんは、阪神・淡路大震災の折に高齢の女性が位牌を探している報道に衝撃を受けたこと、また阪神・淡路大震災の後には全ての要素が流動化して物事や出来事の着地点がなくなるという、大澤真幸さんの言う「不可能性の時代」が到来したこと、またオウム真理教事件によって宗教はあぶないと言われながらも論理的根拠が欠けるものを断言的に語る人々が増えたということ、大学での学びを通じて思想家の吉本隆明さんの『最後の親鸞』を通じて仏教に深く関心を向けていったことなどがテンポ良く語られていきました。そして、死者を通じて自己と対峙する態度が生まれること、また近著『秋葉原事件』(朝日新聞出版)で展開された、近代という時代を経て対面の関係が結びにくくなった人たちが求める「透明な関係」という視点を提示。さらに時代をさかのぼって、第一次世界大戦後のゆるやかな不況の時代、承認欲求を満たされない人々が暴力にて一発逆転を訴えかける「テロリズム」の時代に入ったことを指摘し、そこにはスピリチュアリティとナショナリズムが結びついている、と、当時の社会に流れる雰囲気について、精緻な解説がなされました。
1時間の話題提供の後は、参加者どうしで円座となり、1時間半を越える対話の時間となりました。震災救援に携わった宗教者や、マイノリティ支援のNGO活動に取り組んできた方、中島さんと同世代の高校教員など、多彩な方からコメントや質問が寄せられました。今後はそれぞれが持つ複数の「根拠地」を大切にしようと呼びかけた中島さん。最後は「自分たち自身が自分たちに向き合うためには、自分が他者に及ぼしているかもしれない暴力、そこにある断層を常に自分に対し投げかけないといけない」とし、公と私のあいだの関係性を丁寧に見つめることの意義を説き、濃密な議論を終えました。今回の議論は全文、文字化をする予定ですので、ご期待ください。
小レポート
毎月第4木曜日夜…「復興寺子屋」開講中
3月11日に発生した「東日本大震災」。4月11日には「祈りの市民集会~Pray from West」を開催しましたが、その際にも示したとおり、應典院では災害について、そして復興について考える定例の機会を設けることに致しました。それが「復興寺子屋」です。毎週木曜日のトークサロン企画「circolo~チルコロ」の一環としての開催です。
復興寺子屋は毎回、関西学院大学災害復興制度研究所研究員の関嘉寛先生(社会学部准教授)を迎え、現地の今と、地域社会の未来について、参加者の皆さんと意見交換を重ねています。寺子屋という名のとおりに、何かを誰かから教わるという、一方通行の学びではなく、参加者の皆さんの謎や疑問を紐解いていく機会となっています。例えば「被災者とは何か」という問いかけに対して、関先生は「被災をしていない者たちが与えているレッテル?」などと返し、それを参加者どうしで議論する、といった具合です。「焦らない」ことが大切とされる復興の過程を定点で見つめていく場に、どうぞご関心とご参加をいただければと思います。
小レポート
應典院の取り組みをケーススタディ「官民協働の文化政策」
去る5月17日に静岡文化芸術大学の松本茂章教授による新著「官民協働の文化政策:人材・資金・場」が水曜社から刊行されました(259ページ・2,800円)。公共事業の民営化や市民自治が促進される中で、「新しい公共」の意義が改めて問われる昨今、文化政策の領域においても、市民主導の芸術創造拠点の運営に注目が集まる中での出版です。
本書では、これまでの文化行政の成り立ちや課題を概観、これからの「地域ガバナンス」の担い手となり得る存在として3つの芸術創造拠点を取り上げています。そこでは京都芸術センター、CAP houseとともに、應典院の実践に焦点が当られました。設立経緯からスタッフのひととなりまで迫り、應典院史を紐解く貴重な研究ともなっています。
小レポート
夏の演劇祭 space×drama2011開幕!
應典院の夏の風物詩、舞台芸術祭「space×drama 2011」が7月8日に開幕します。1997年の開始以来、関西小劇場を中心に活躍する劇団が相互に支え合い、切磋琢磨し合う機会となっているこの演劇祭。大きな特徴の一つは、前年度の優秀劇団が次年度に劇場と協働プロデュースの公演を行うことです。今年は昨年の優秀劇団であるコトリ会議の公演に加え、6団体が優秀劇団を目指し競います。
また参加劇団からの発案により、今年は東日本大震災の復興支援に向けた企画(折り鶴での祈り等)の実施に加え、ホームページをリニューアル。参加団体の紹介のほか、リレーブログや劇評なども特設ページ(http://www.spacedrama.jp)にてご覧いただけます。
コラム「数」
死隠蔽せず、見据えることが重要
「今日は、みんなに見てもらいたい写真がある」。
4月のある日、このような言葉で始まった授業とは、私が教えている「生死の社会学」。東洋大学ライフデザイン学部でのことだ。教室のスクリーンに映し出した写真は、『ニューヨークタイムズ』に掲載された、陸前高田市の体育館に設置された遺体安置所で、息子を探す父親の写真である。黒や青色のビニール袋に入れられ顔だけが露出している遺体がいくつも並ぶ。
テレビでは、来る日も来る日も、東日本大震災での被災状況を伝えていた。死者と行方不明者数は毎日更新され、数が被害規模のバロメーターとなっていた。
この報道を見て、これでは真実は伝わらないと、私はもどかしく思っていた。そこで「いのちの教育」を盛り込んだ科目で、先の写真をみせることにしたのだ。「一刻も早く、探してあげたい」と願って必死で探す父親。どこかで「お父さん、ボク、ここだよ」と、それを待つ息子。つい数日前まで、幸せな家族の日常があった。いま父親はどれだけ無念か。気が狂うほどの愛情で、異常な光景の中を探し続けていることか。
こう説明した後、私は、「いーち、にーい、さーん、しーい」と数を数え出した。「(死者・行方不明者)2万5000人以上と数字を言うのは一瞬だけど、2万を数えるとどのくらいの時間がかかるんだろう」と語りかけ、総数ではなく、一つひとつのいのちの重さに注目させ、実態を感じさせようとした。
家族が届け出ても、遺体が見つからず未だ行方不明の者もいるが、しかし一方で、役所ごと津波に流されて戸籍も定かではない地域がある状況下では、届けを出す人もなく、行方不明者にもカウントされていない人が入るのではないかと、心を痛めている。遺体は見つかっているのに、身元確認者や引き取り手がなく仮埋葬された人がいるかもしれない。
2万5000人以上という死亡者と行方不明者、さらにその家族には、それぞれの物語がある。復興には「希望」を持つことは大事だが、死者を忘れず、死者を弔ってこそ、真の復興となるのだろう。
東洋大学で「生死の社会学」や「いのちの教育」等を教え、また尊厳ある死と葬送をめざしたNPO法人エンディングセンターでは、桜を墓標とした「桜葬」墓地を企画し、エンディングサポート等を実践している。主な自著は『最期まで自分らしく』毎日新聞社、『墓をめぐる家族論』平凡社新書、『新・遺言ノート』KKベストセラーズ、『墓と家族の変容』岩波書店、『子の世話にならずに死にたい』講談社。共著に『岩波講座「宗教」第10巻 宗教のゆくえ』岩波書店、『思想の身体、第10巻 死の巻』春秋社等多数。
Interview「溢」
樋口 貞幸さん (フリーランス・アートアドミニストレーター)
被災地のアーティストとアートNPOの表現の回復に取り組むプラットフォーム「アートNPOエイド」。今、問い直してみる表現することの強さとは?
震災翌日、ビルの屋上から旗をふって救助を求める人達に対して成すすべのなかったアートであるが、それから3ヶ月経ち、被災者のメンタルケアや日常の回復が必要とされる中で、今まさにその社会的役割と存在意義が問われている。そこで今回、震災以降被災地での文化芸術活動の環境整備に取り組まれている樋口貞幸さんにお話しを伺った。
樋口さんご自身は地震当日鳥取にいて、海外の友人からのメールで東日本大震災を知ったとのこと。一週間後に予定していた『全国アートNPOフォーラムin鳥取』の準備をしていた最中だった。「フォーラムを実施するか否か、悩んだあげく3日前に開催を決めました。」結局、のべ250名近くが参加し、2日間の議論の末に、閉会のことばを表明した。そこでの約束を実現していく形で「アートNPOエイド」が発足。フォーラムを主催したNPO法人アートNPOリンク理事のほか、様々な立場のメンバーによって活動が展開されている。「1月の理事会で『市民ファンド』の立ち上げが決定していたので、普段やっている事業をシフトする形で実現できました。」
アートNPOエイドのプログラムは4つある。アートNPOやアーティストに寄付を分配する「活動支援プログラム」、被災地でのアート活動をドキュメントする「伝えるプログラム」、表現に必要な機材や道具を寄贈する「表現の回復プログラム」、そして、アートNPOをコーディネートする「つなげるプログラム」だ。
確かに一方で、創作活動の再開に向けた要望は切実だ。「現地の状況は様々でひとく くりに語れないのですが、ただ、落ち着いて制作できるスペースがほしいという声をよく聞きます。津波で家が流され、親戚の家やゲストハウスを転々とする若いイラストレーターや、今なお続く余震のため繊細な作業に向き合えないアーティストの姿をみていると深刻です。」被災地のアーティストにとって今何が必要なのかを聞いてまわる樋口さんに、地元のアート関係者は「現地の今の状況を知ってほしい、その上で一緒に何かつくろう」と語る。
しかし他方で、絵を描き、音楽を奏でるといった表現活動に対してやはり慎重になる雰囲気があるのも事実。多くの方が亡くなり痛みを抱えている中で、アートだ表現だと言ってよいのか。そこには支援してもらうことに対するためらいや、「震災」という文脈を帯びてしまうことへの危惧も存在する。
さらに樋口さんが懸念する点は他にある。それは、アートが批評をできなくなる雰囲気であるという。「アートはそもそも波風をたてる存在。社会に対して批判的な表現が制限されることで、自由な表現ができなくなることが最もこわいことなのです。」そこで今一度「被災地支援の対象がアートである意義」を問うてみると、意外な答えが返ってきた。「私は究極的に、『アート』でなければならないとは思っていません。人権に関わる活動をしていると思っています。〝あふれでてくる表現〟を大切にしたい。私たちは、日々表現を通してコミュニケーションしているし、アートは表現の最突端にあると思います。アートNPOは、社会の課題に向き合い、多様な表現を保障する存在です。だからこそ、アートNPOやアーティストがいち早く表現を回復してほしいと願っているのです。」
編集後記〈アトセツ〉
かねてよりお世話になっていた、ささえあい医療人権センターCOMLの辻本好子理事長が6月18日に亡くなられた。「賢い患者になりましょう」というフレーズに聞きなじみのある方がいるとすれば、それはCOMLが提案し続けてきた「医者にかかる10カ条」が世の中に響いていった結実なのだと思う。
6月9日、辻本さんが最後に綴ったブログが何とも印象的だ。それは「『真実』と『事実』と『現実』は微妙に異なる…」と始まる文である。要約すれば「真実」とは思い込み、「事実」とは客観的な現実、そして「現実」とは今起きている限りなく可能性の高いこと、と区別がなされ、ご自身の病状のカミングアウトが行われた。それは「医者にかかる10カ条」の10番目の項目「治療方法を決めるのはあなたです」を自らが実践している証左であった。
辻本さんを思うとき、もう一人、浮かぶ人物がいる。COMLの山口育子事務局長だ。二人三脚、阿吽の呼吸で共に活動してきた山口さんを、辻本さんは5月13日に記したブログで「家族以上にきめ細かく私のすべてを支えてくれている」と紹介している。
東日本大震災の前、「弧族」という言葉が新聞で紹介された。その後、報道には「絆」の掛け声が響き渡った。改めて、辻本さんと山口さんのあいだの関係を思うと、「あなた」に寄り添っていく縁は一朝一夕には結ばれないのが現実だろう、と思う。とはいえ、血縁なき家族関係に根ざした「ささえあい」の豊かさを、二人の、そしてCOMLの活動から学び直したい。(編)
