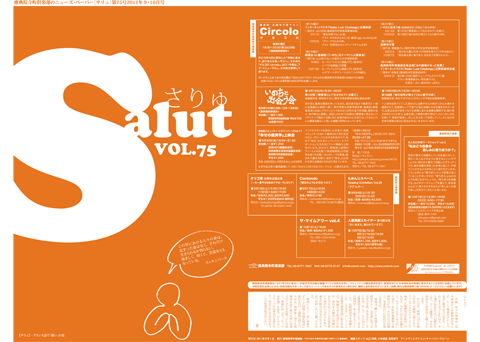
サリュ 第75号2011年9・10月号
目次
レポート「舞台芸術祭space×drama2011」
コラム 今城良瑞さん(NPO法人HAPPY FORCE 理事長)
インタビュー 小谷みどりさん(第一生命経済研究所主任研究員)
編集後記
巻頭言
この世における人々の命は、定まった姿はなく、どれだけ生きられるか判らない。
痛ましく、短くて、苦悩をともなっている。
「スッタニパータ」
Report「興」
「祈ると折るは似ている」千羽鶴に込めた劇団の願い
変化と安定の中の工夫
夏の應典院の本堂は舞台芸術祭「space×drama」と、高校演劇部が集う大阪高校演劇祭「Highschool Play Festival(HPF)」によって演劇真っ盛りとなります。今年はspace×dramaでは7劇団が、HPFでは14校が、それぞれ競演することとなりました。HPFは昨年度末で精華小劇場が閉鎖されたことに伴い、これまでのウイングフィールドの他に、新たに吹田のメイシアターでも実施されるという変化がありました。他方、1997年に開始のspace×dramaは、2003年の大幅なリニューアルから9年目を迎え、ある種の安定感の中での展開となりました。
space×dramaは例年2月に全劇団が顔合わせをし、「制作者会議」を設置して、その年の運営方針等が協議され、実施されるという形態を取っています。そんな中、2011年度は①スマートフォン時代に対応したウェブサイトの設計・運営、②幟などの新たな広告宣伝媒体の企画開発、③東日本大震災の被災地への支援、これら3点が重点方針となりました。ウェブではリレーブログや劇評ブログ、そして昨年度から実施しているTwitterとの連動はもとより、デザイン等を全面リニューアルの上で、各劇団が協力して写真による道案内を行ったり、終演後、各劇団からのメッセージ動画を配信するなどの取り組みや、公演期間中は應典院山門に水色の幟が掲げられるなど、これまでにはない工夫が重ねられたのでした。
祈りを折る~playとpray
space×drama2011ならではの取り組みが、3番目の重点方針、東日本大震災に関する取り組みです。具体的には「募金」活動と「千羽鶴」を折る場の提供、この2つがなされました。募金については開演前と終演後に受付ロビーに設置され、劇団によっては物販等の売り上げの一部も含めて、企業メセナ協議会によるGBFund(東日本大震災芸術・文化による復興支援ファンド)に送ることとしています。また、千羽鶴については「あの日を忘れない」という劇団の願いを白布に記して呼びかけ、来場者の方々に折っていただきました。
時間が経つごとに、應典院のロビーには募金と折り鶴、そしてメッセージが増えていきました。演劇は英語で「Play」、そして祈りは「Pray」、似た響きのあるこの2つのあいだを、千羽鶴を「折る」という行為がつなぎ、彼の地に「祈り」を捧げているようにも思えました。長きにわたる復興への道を歩んでいる東北を思う、ピンク地底人、プラズマみかん、コレクトエリット、激団しろっとそん、Micro To Macro、May、コトリ会議、この7劇団に、改めて敬意を表します。とはいえ、演劇祭としては例年どおりに優秀劇団を選出し、今年のコトリ会議のように、次年度の協働プロデュース公演の座を獲得すべく、それぞれに創意工夫を凝らした表現にあたられたことも、ここに綴っておきます。
應典院寺町倶楽部の演劇担当専門委員等による選考会議を経て、今年度の優秀劇団は史上初となる2劇団の選出となり、MayとMicro To Macroが選ばれました。講評は上述のウェブに掲載となっています。実は今年度も3劇団が「再チャレンジ」による参加でした。来年度、どんなラインナップで、どのような場が生まれるか、楽しみです。
小レポート
喪失の時代を
みつめなおす 7月16日より全3回に渡って、エンディングセミナー2011「遺族とグリーフワーク:“喪失”の時代をどう生きるか」が開催されました。今年度は、世界有数の「死者大国」となることが想定される超少産多死社会の現代日本に焦点をあて、3名のゲストにお話しいただきました。第1回は自らの遺児体験を生かしたグリーフサポートを行う尾角光美さん、第2回はホスピスケア活動等で著名な飛騨千光寺住職の大下大圓さん、そして第3回は企業シンクタンクの立場からエンディングデザインを提唱されている第一生命経済研究所主任研究員の小谷みどりさんをお迎えしました。
今年はとりわけ東日本大震災で犠牲となった多くの方々の葬送と残された人々のグリーフワークについて語られました。「三人称の悲しみを一人称として受け止める」グリーフワーカーの社会的意義が改めて確認された機会となりました。
小レポート
暮れゆく墓地に、言霊が鎮まる
お盆恒例の上田假奈代さん主宰による「詩の学校」の特別編「それから」が8月3日に開催されました。大蓮寺本堂で秋田光彦住職による法要と講話、大蓮寺墓地で詩作と発表、そして應典院研修室で茶話会という流れでした。
住職の講話では、東日本大震災犠牲者にとって初盆にあたる今回、特に亡くなった方々への哀悼と、私たちが生かされていることへの尊さに思いを馳せてほしいと語られました。その後、墓地での詩作では個人の記憶を紐解き、それらを詩へと編み上げる過程でわき起こる思いを、涙やつまる声と共に21名の参加者どうしで共有しました。
小レポート
夏の風物詩・高校生の演劇祭HPF開催
7月17日~31日、HPF(Highschool Play Festival)が開催されました。総勢26校の演劇部員たちが府内3劇場に分かれ、日頃の成果を披露する大阪高校演劇祭。應典院では、2003年より青少年の芸術文化活動支援の一環として毎年協力しています。今年は台風の影響により1校が後日、別会場での公演となりましたが、連日應典院は高校生の元気な声が響き渡り、活気に溢れました。HPF出身のボランティアスタッフの運営のもと、14日間に及ぶ演劇祭は無事、幕を降ろしました。
コラム「始」
震災で腹をくくる
ボランティア元年と呼ばれる阪神淡路大震災があった平成7年、私は前年に修行を終え、山を降りたばかりの小僧であった。この震災以後、災害がある度に、支援に取り組む僧侶の数は増し、その質は向上していったが、この度の震災においても、更なる活躍をしていると聞き及んでいる。
虐待やいじめ、DVや性被害にあいトラウマとなった方をケアすることを、自分の活動分野としている門外漢の私でさえも、何もできなかった阪神淡路大震災のときとは異なり、僅かながら貢献している。
なぜ僧侶が災害支援に取り組むのかと言えば、理由は至極簡単である。衆生を救うという菩薩の願いが、大乗の教えが、僧侶に染み付いているからだ。宗旨宗派は問題ではない。じっとしていられないよう、こころの中に装置が組み込まれていて、自動的に体が反応するようになっている。
この度の大震災でひとつ、腹をくくった事がある。児童養護施設をつくることにしたのである。テレビで震災の映像を見た瞬間、「震災孤児」が多く出てしまったことが容易に想像できたからだ。
虐待を受けてきた人たちと接する中で、漠然と児童養護施設をつくりたいと考えてきた。そこに震災があったのだ。
釈徹宗さんと宮崎哲弥さんの「寺子屋トーク」では、「人生は危機的だということを認識しておくこと、世界は意のままにならないという自覚のもとに生きること」と、無常や苦についても語られていた。しかし、避けられる危機は避けたいし、避けてもらいたいし、自己実現したいし、自己実現してもらいたいのが、大乗仏教だと考える。
児童養護施設の設立は、人生をかけなければ成らない高い目標ではあるが、じっとしていられない装置が体の中に組み込まれているので、今はその目標に向けて、まっしぐらである。
1971年、大阪市生まれ。真言宗僧侶、保護司。「いのちに向き合う宗教者の会」「高野山真言宗 こころの相談員ネットワーク」に参加。平成17年に、不登校、ひきこもりを対象としたNPO法人HAPPY FORCEを設立。現在は、不登校、ひきこもりだけを対象とするのではなく、虐待やいじめなど、トラウマとなる経験をした人へのサポートも行っていて、インターネット上のコミュニティには、2万人以上の参加者がいる。平成21年に、『ボクらの仏教~毎日がラクになるヒント~』(PHP)を上梓。現在の目標は、社会福祉法人、児童養護施設の設立。
Interview「繋」
小谷みどりさん(第一生命経済研究所主任研究員)
無縁社会の中で死者と向き合う場や、
心のつながりをどう保証していくのか。
グリーフケアとしての葬送の可能性を問う。
誰にとっての葬送なのか
日本の家族のありかたが大きく変化しています。
日本の単身世帯は1500万世帯を超えていますが、中でも深刻な事態は、生涯結婚しない男性単身世帯が急増していることです。例えば、現在56歳の男性の中で、6人に1人が1回も結婚したことがないという報告があります。また対人関係も乏しい傾向にあり、ある調査では、2、3日の中で1回も会話をしたことがない単身男性は4割を超えています。家族がいない、周囲とのつきあいもない。だから、葬式も無用。無縁社会は、身近なところにあります。
「エンディングデザイン」とは、自分の死を生前から準備しておこうという考え方ですが、ここでは、一体誰の死なのか、という人称別の捉え方が重要です。一人称は「自分の死」、二人称は「大切なあなたの死」、三人称が「客観的な他人の死」となりますが、特に一人称と二人称の間に転位が生じやすくなります。例えば大切な人は死んで浄土に行ってほしいが、自分は死んだら無になるという感覚です。延命措置の必要を聞いた調査でも、自分については7割以上が拒否するのですが、対家族には半分以下に減ります。墓参りには誰もが熱心ですが、自分の墓は要らないという。そこのズレは非常に大きいといえます。つまり、それは誰にとっての葬送なのかという観点と重なるのです。
現代の死は本当に悲しいか
「死」は4つに分類できます。「医学的な死」「法的な死」、そして「社会的な死」「文化的な死」です。日本人は医学的に死んでも、文化的には死なないといわれます。グリーフからの立ち直りも欧米人に比べ早いとも。その理由は、日本人は死者と共存しているからではないでしょうか。亡くなった人の写真をいつまでも飾る。好物を仏壇に供える。お墓も死者と向き合うための装置であって、日本人は信仰がなくても、土台は熱心な宗教的民族なのです。
しかし、近年、日本人の死が大きく変容しています。例えば、高齢者の死の増加、未曽有の大量死そして死を迎える場所の変化などの特徴が挙げられます。現在、日本人のうち85%が病院で亡くなっていますが、そのことと死に対する意識にも深い関連があります。
そこから窺えることは、「現代の死は本当に悲しいのか」という問いです。病院で手厚い医療や看護を受けて迎える高齢者の死は、家族にとって、いわば「納得できる死」ではないのか。また長期の入院中にすでに死を予測している家族にとって、死後の悲しみ以上に、生前の予期悲嘆のほうが長いのではないか。
その意味で、お金もあるし、家族もいるが、葬式をしない、という選択が増えているのは、現代の死の結末なのかもしれません。グリーフケアとしての葬送が有効かどうかは個別の問題です。慣習としてだけ存在するなら、葬式は今後、いっそう縮小していくことでしょう。他方で死者と向き合う場や、心のつながりをどう保証していくのか。葬送は、日本の家族問題の変化と密接に関係しているのです。
編集後記〈アトセツ〉
先般、原子力発電は「安全神話から必要神話を生んだ」という報道を目にした。安全に絶対はないはずだ。しかしそう言ってきた以上、やり遂げねばならない必要を生んだ、という論理だ。それが神話なら実話は?と勘ぐりたくなる。
そんな中、映画『10万年後の安全』が劇場公開された。フィンランドやスウェーデンで始まった地層処分を取材したものだ。今から10万年を遡ると、ネアンデルタール人がいた頃だ。放射性廃棄物の最終処分には、それだけの時間と、未来世代への信託が必須となるのだ。
映画は一瞬にして時間と空間をずらし、見る者に気づきや学びや楽しみをもたらしてくれる。そこで、9月30日には應典院本堂ホールで『幸せの経済学』を上映することとした。仏教経済学を基軸とした、「生きる」ということの意味や価値を問い直す作品だ。無縁社会と呼ばれた昨年、東日本大震災に見舞われた今年はアメリカ同時多発テロ事件から10年でもあり、喪失の時代の幸せのかたちを見つめ直したいと願ったためだ。
映画によって、良い意味でずらした時間と空間を現実に重ねるのが、上演後の語りだ。今回は、開発途上国で人間関係を取り結ぶ仕事に従事されてきた中田豊一さんを招く。著書には『ボランティア未来論』もある。ローカルとグローバルの視点の交差の中で、安全で安心できる社会づくりの知恵を紡ぎ出したい。(編)
