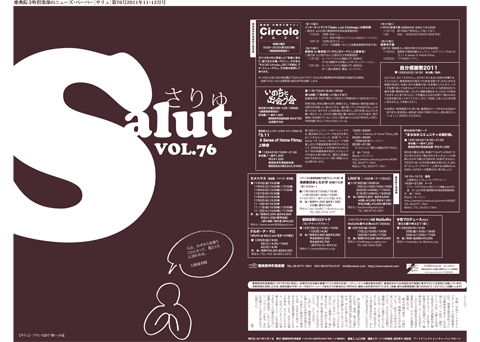
サリュ 第76号2011年11・12月号
目次
レポート「コミュニティ・シネマ・シリーズvol.17」
コラム 金村俊治さん(パナソニック(株)社会文化グループ参事)
インタビュー 川中大輔さん(シチズンシップ共育企画代表)
編集後記
巻頭言
人は、みずからを救うことによって、他とともに済われる。
「大無量寿経」
Report「問」
「やらない理由」を言わないためにグローバリゼーションに抗う知恵を
映画の世界を味わう場
9月30日、シリーズ初となる、平日夜の應典院「コミュニティ・シネマ」が開催されました。17回目に取り上げた映画は、ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ監督らによる『幸せの経済学』でした。この映画は5月に渋谷の映画舘「アップリンク」で先行ロードショーの後、全国各地で自主上映が進められています。作品は、ヒマラヤのラダックをはじめ、世界で起きている様々な実態と、各地で地域に根ざした活動に取り組むリーダーの証言を織り交ぜながら描くドキュメンタリーです。
一連のシリーズでは作品世界を味わう時間も生み出したいと、必ず上映後にトーク企画を組み合わせています。今回は「ポスト3・11から『本当の幸せ』を考える」と題し、ゲストに参加型開発研究所の中田豊一さんをお招きしました。特に都市文明における消費社会のグローバリゼーションが世界全体に広がっていく中で生まれた新たな格差や貧困、それらを身近な暮らしからどう見つめ直すのか……。単なる復古主義、懐古主義ではない、地域コミュニティの姿を展望すべく、阪神大震災地元NGO救援連絡会議、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、シャプラニール、市民活動センター神戸等、多彩な現場に携わってきた中田さんと、グローバリゼーションの反対方向、すなわちローカリゼーションのための知恵を紐解くことにいたしました。
当たり前の日常を問う
映画では経済、ビジネス、食べもの、それらが一人ひとりの人間の手に及ばない範囲に広がっていくグローバリゼーションの影響が細かく解説されました。具体的にはグローバリゼーションには、人を不幸にする・不安を生み出す・自然資源を浪費する・気候を激変させる・生活を破綻させる・対立を生む・大企業へのばらまきである・誤った会計の上に成り立つ、という8つの不都合な真実がある、と言います。だからこそ国際貿易や他国との交流を廃止するのではなく、「地域で必要なものはその地域で生産」するということで、「公平な競争条件の確立」をもたらす「ローカリゼーション」が重要だと訴えます。例として上がっていたのが、スーパーで買うのと、地元のお店で買うのとでは、会話の量が10倍違う、というものでした。自らの暮らす地域に関心を向け、その地に住む人々と関わり合う機会を重ねていくと、自然と他者を敬い、生きている実感が導かれる、それを各地の映像から訴えかけてきました。
映画の後のトークでは、中田さんから地域コミュニティの捉え方について、ご自身の経験から話題提供がなされました。例えば、あるアフリカの国で「家族は?」と尋ねると「100人」と答えが返ってきたそうです。これは身近にいる人が困ったらどんなに犠牲になっても助けに行くことを意味していること、そしてそういう関係の中では互いの対話を通じて問題に対する答えが見つかってくることが示されました。トークの最後、中田さんは、グローバリゼーションとは、収入と支出の根拠がわからない中で「足りない」と思ってしまうこと、と語りました。当たり前となっている今を問い続けること、それがよりよい未来を拓く、幸せへの道標となるのでしょう。
※なお、本事業は「安全で安心できる社会づくり」を求めるべく、JR西日本あんしん社会財団による助成で行われました。
小レポート
小劇場ブームを支えた演劇人の思い
9月29日、木曜サロンチルコロ・インターネットラジオ「Radio Lost Challenge」の公開収録がありました。應典院寺町倶楽部の西島宏会長が担当するシリーズ企画「あの劇場があった風景」は、70年代以降の大阪の小劇場演劇シーンについて当時を代表するゲストの証言で構成するもの。
今回は80年代から90年代の関西小劇場演劇をリードした、OMS(扇町ミュージアムスクエア)をテーマに、同館の初代支配人・熊澤泰雄さん、当時は劇団☆新感線の女優を引退した直後で、現在は演劇プロデューサーの岡本康子さん、そしてテレビや劇団で活躍する国木田かっぱさんと石原正一さんの面々が語りあう中で、関西小劇場演劇シーンの貴重な証言をいただきました。2002年に閉館となったOMSですが、その劇場の精神を、いま引き継いでいるのは「應典院ではないか」という声もあり、演劇人の思いが交流したひと時でした。収録内容は後日ホームページで配信いたしますのでぜひお聴きください。
小レポート
神戸女学院学生によるトークイベント
9月23日、應典院スタッフが講師を務める神戸女学院大学「アートマネジメント演習」の受講生が「Design Your Life~今、食から健幸に気づくとき」を開催。今年は「日常にある“当たり前”を見つめなおす」ことの必要性から「食」にまつわる生産-流通-市場-消費といった過程に秘められた様々な文化的視点を、ゲストのエピソードから紐解き、そこで得た感覚をアート作品の制作へと繋げました。日常の気づきを具体的な作品へと昇華させつつもまた日常に戻すというサイクルは、まさにお寺という場だからこそより効果的に意識されたのではないでしょうか。
小レポート
旗揚げ支援プロジェクト始動
應典院舞台芸術祭space×drama2011が終了し、次年度の募集が始まる中、今年から新しい演劇支援が始まりました。シアトリカル應典院旗揚げ支援プロジェクトです。
これは、應典院寺町倶楽部が新たに活動を始める劇団を応援する事業で、今回そのプレ企画に選ばれたのが「演劇集団あしたかぜ」です。この劇団の劇団員は全員卒業を間近にひかえた大学4回生。代表のつぼさかまりこさんは一生演劇を続けたいと意気込みます。今回の旗揚げ公演には、寺町倶楽部から本堂ホール使用費やアドバイザー費等の一部が援助され、11月15日16日に本番を迎えます。
コラム「築」
NPOも企業も人がつくる
10月14日から16日に「全国アートNPOフォーラム in 大阪」が開催された。社会を取り巻く課題やアートをめぐる環境について、各地でアートに関わるNPO関係者や市民が集い討論する。今年度は、震災とアート、自治の創造について考える場となった。私はフォーラムにお招きいただき、應典院本堂ホールで「NPOのキャパシティビルディング」というテーマでお話した。
キャパシティビルディングとは組織基盤の強化のことで、建物に例えると基礎や土台の強化の
ようなものである。社会課題の解決のために市民活動が持続的に発展していくためには、NPOのキャパシティビルディングが必要であると考え、当社は「Panasonic NPOサポート ファンド」を2001年に設立。以来10年にわたり、よりお役に立つプログラムへと改善に努めながら、一貫してNPOのキャパシティビルディングを支援してきた。そこで得た気付き、学びを皆様にご紹介した。
キャパシティビルディングに奇策はない。いろいろな言い訳をして先延ばしにしてきた自分たちの組織の問題に本気で向き合い、地道に課題の解決に取り組むというシンプルな王道あるのみ。重要なポイントを3つあげるなら、「課題の深堀り・絞り込み」、「今考えられる最善解を求め、実行と改善を繰り返す」、「多様な視点・第三者の客観的な視点を入れる」。これはNPOも企業も人がつくるものだから同じである。
社会を取り巻く課題やアートをめぐる環境について、みんなで討論するフォーラムが、全国各地で毎年継続して開催されている。 そして今年は、従来の参加者に加え、釜ヶ崎で働き暮らす人も参加して積極的にのびのびと発言を行った。日本・世界の状況は厳しく、将来も明るい見通しがあるわけではないが、このような集まりが続く限り、決して絶望することはない。
Interview「語」川中大輔さん(シチズンシップ共育企画代表)
應典院で「生と死の共育ワークショップ」を開催して5年目。
若者主体の「自分を開いて他者と対話する場」を継続させる中でみえてきたものとは。
市民主体の社会づくりを提案するNPOシチズンシップ共育企画の創立は2003年、若干22歳の時だった。應典院と共催の『生と死の共育ワークショップ』は2007年から続いており、毎年1泊2日かけて〝自死〟や〝老い〟〝みとり〟などをテーマに若者たちが語りあう。今年で5回目を迎えた。「きっかけは2006年に祖母を亡くしたことがあります。大切な人の死ということと同時に、周りの悲しんでいる人たちにどう声をかけていいかわからない自分がいるということがとてもショックでした。」
そんな自身の葛藤を契機に、應典院を会場としてワークショップをスタートさせた。5年間企画を継続させる中で、徐々に同世代の若者の反応も変化してきたという。例えば、宗教や死について語ることに対する抵抗感もやわらいできたのではないか、といことがある。確かにここ数年、エンディングデザインやグリーフをテーマにした映画や小説が話題となっている。「現代の若者は、明るい未来を想像しにくい中で、自分が『負け組』になってしまわないかという恐怖心や不安を持ちながら、『自分らしい将来設計』を求められています。生活体験の幅が狭いのに、いったい自分は何者かと問われつづけ、心が疲れているのではないでしょうか。」
そんな若年層にとって、このワークショップは自己開示と対話による気づきの場であると語る。「ワークショップに来る若者にとって、企画のテーマは入口。生きる上で根源的な問題について、関心は共有しつつも背景は異なる他者とじっくり対話できる場ということに関心が持たれているように感じます。」一人一人の語りの場面があり、その中で声に表したり、耳を傾けることで気づきにつながる、というワークショップならではの効用がうまれている。
今年のテーマは『私はどう他者の悲しみに寄り添うか』。参加者はNPOスタッフや介護士、主婦などさまざまだ。〝寄り添い〟を主題に、体験を分かち合い、語り合い、仏教の考え方にも学ぶ。1泊2日の長丁場だから、自ずと対話の内容も深まる。
ワークショップを始めた当時の原点に戻るようなテーマを選んだ理由には、東日本大震災の影響があったという。「ボランティアとして、現地に行ったメンバーは、初めて死が充満する場に身を置くという経験をして帰ってきた。彼ら・彼女らが被災者との関わりにおいて『あれでよかったのか』と悩んでいる姿をみたのがきっかけでした。」
「ただ過去の若い参加者には、ワークショップの場での気づきを自分の日常の暮らしとどう結びつけていいのか、すぐに答えが出せずに、問いを抱え続け、温めている方も少なくありません。学びを熟す時間が必要なのかもしれません。」と推測する。
「その意味で、生と死を考えるうえで、『参照点』としての宗教の役割は大きい。なぜ私は生まれたのか、あなたと出会ったのか、理屈では語れません。死や病など不条理な出来事であればなおさら、人間を超越したものがないと、寄りどころがなくなってしまうのではないでしょうか。」それぞれの問いや痛みを持ち寄りながら、その迷いをも共有する、そんな対話の場の継続に今後も期待がかかる。
編集後記〈アトセツ〉
先般、全国アートNPOフォーラムin大阪が開催された。関連企画を含めて3日目は應典院本堂ホールが会場となった。午前は「震災・アート、自治」と題した対談、午後はNPOの基盤形成に関するレクチャー、その後で2時間半の総合討論だった。激動の時代、アートの自治も、一人ひとりの総合的な表現が重要になる、そうした議論が基軸となった。
総合討論の最中、27歳の女性が、感極まりながら発言した。「私たちの世代では使ってないことばが使われている」。自分たちの活動が、議論の俎上に載せられていないのでは、という問いだった。そこには、その場に居ながらして身の置き所がない、そんな主張も含まれていたんだろう。
時に言葉は関係を分かつことになる。事実、使う言葉に世代間の格差が如実にあらわれる。そんな関心もあって、総合討論においてはトップダウンでもボトムアップでもない「ボトムダウン」が必要ではないか、と提案した。海に喩えるなら、水面から深海まで、実に多様な存在があるはずであり、そこに目を向けていこう、というものだ。
とはいえ、過度な多様性への関心にも注意が必要だろう。水面から海底まで攪拌すれば、それぞれに成立、生存できた前提を壊すことになるためだ。ただ、自分とは違う世界が、すぐそこにつながり、広がっていることへの想像力を抱くこと、これが重要であることは論を待たない。想像と創造が、いみじくも同じ「ソウゾウ」である、またも言葉のことばかり考える3日間だった。(編)
