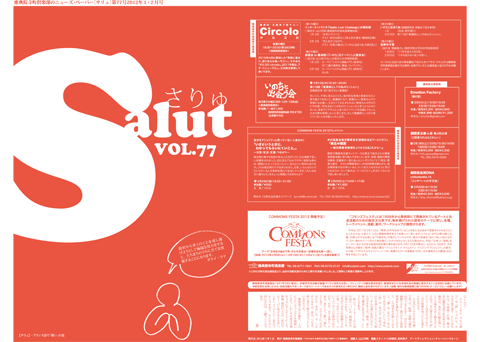
サリュ 第77号2012年1・2月号
目次
レポート「第62回寺子屋トーク」
コラム 釜中悠至さん(NPOいい家塾 事務局長)
インタビュー 山﨑都世子さん(映画監督)
編集後記
巻頭言
最初から多くのことを成し遂げようとして極端な努力をすると、たちまちのうちに全てを放棄することになります。
「ダライ・ラマ」
Report「街」
私の世界と社会とを結び合わせ地域のつながりを活かす
あえて「しない」デザインへ
年の瀬の12月14日、寺子屋トーク第62回「まちなかコミュニティの設計図」が應典院本堂ホールにて開催されました。メインゲストにはStudio-Lの代表で、京都造形芸術大学空間演出デザイン学科長の山崎亮さんを、後半のトークセッションにはアサダワタルさん(事編〜Kotoami)、中村裕子さん(大阪商工会議所)、松富謙一さん(からほり倶楽部)をお招きいたしました。珍しい平日夜の開催ながら、満場の参加者を得て会場は熱気に包まれました。東日本大震災を経験した年の末に、今後の地域を考えるヒントを共に探ることになりました。
第一部は「人を結ぶ地域のデザイン」と題した山崎さんの講演でした。造園をはじめとしたランドスケープから、ハード整備を前提としないコミュニティへとデザインの関心が移っていった経過について、世の中の関心の変化とあわせて丁寧にお話いただきました。また、著書『コミュニティデザイン』(学芸出版社)で紹介されたマルヤガーデンズ(鹿児島市)などの事例をはじめ、多様な現場で多彩な担い手が鍵となって積極的な実践が重ねられていることが紹介されました。そして、自分のやりたいことと社会が求めることから「夢」を描き、やりたいことにできることを重ねて「趣味」を活かし、自分ができることを社会に投げかけることで「労働」とする、それこそがコミュニティデザインにおける企画の醍醐味だとまとめられました。
否定しないということ
後半は「持続可能な〈まちなか〉コミュニティとは」と題した円卓会議の形を取りました。まずは3名が話題提供を行い、まずはアサダさんが上町台地マイルドHOPEゾーン協議会による「オープン台地」から、まちを見つめる個人の目線について解説しました。続いて中村さんが事務局を担われている東横堀川水辺再生協議会(e― よこ会)の内容を説明。そして松富さんは、戦災で焼け残った空堀界隈の長屋再生を通じた魅力発見の取り組みを紹介しました。
その後、参加者の方々にマイクを向けた総合討論になると、会場からは「身分志向の人と目的志向の人とが混在する集団」、「継承者が居ない墓地が多い霊園」など、多様なコミュニティのデザインに対して質問が寄せられました。「デザインするコミュニティにそもそもあった関係性こそが大事」(松富さん)、「外部の人々の眼差しと関わりによって協働の水準はステップアップ」(中村さん)、「まちは共同体と言うより共異体」(アサダさん)と、各々の現場からの知恵が示された後で、山崎さんは「変数を大事にする」のが重要、とまとめました。つまり、コミュニティを一様に考えない、と。コミュニティデザインには「教科書」はなく、「Yes, and…」と、まずはその人を受け入れていくことで、ないものを「つくる」ことから、あるものを「つかう」ことへと関心の重点が変わるとのことです。
小レポート
映画「3.11 A Sense of Home Films」上映
11月24日、コミュニティ・シネマシリーズvol.18を開催。上映作品、また、「震災に映画は何ができるのか」というテーマへの関心の高さから、110名を超える方々が参加、堂内は満場となりました。
この映画は、3月11日に起こった東日本大震災後、カンヌ国際映画祭新人監督賞を史上最年少で受賞した河瀨直美監督の呼びかけにより世界各地21人の作家がそれぞれ3分11秒の短編映像を制作したオムニバス作品です。
上映後の河瀨監督によるティーチインでは、「自分ごと」という言葉をキーワードに、この作品が奈良金峯山寺で奉納上映されたことや作品への思いなどが語られました。
その後のディスカッションも含め、参加者それぞれが「Sense of Home(家という感覚)」について考える機会となったのではないでしょうか。
小レポート
秋田光彦住職共著『仏教シネマ』刊行
秋田光彦住職と宗教学者の釈徹宗氏の共著『仏教シネマ~お坊さんが読み説く映画の中の生老病死~』がサンガより刊行されました(254ページ・1,500円+税)。元映画プロデューサー・脚本家である秋田住職と、世界の宗教研究に加えて芸術文化にも造詣の深い釈先生が、映画を手掛かりに「生老病死」について語り合い、死生観に迫ったもの。
「おくりびと」にみる葬送儀礼、ゾンビ映画にみる多文化共生論など、2人の仏教者によって紐解かれる映画の背景には非常に重層的な解釈が広がります。巻末には、震災後の仏教について緊急対談を採録。映画の観方が変わります。
小レポート
應典院で生まれた作品が、小説に!
12月7日、應典院2階の気づきの広場にて、劇団「突劇金魚」の主宰・サリngROCKさんによる初の小説作品『しまうまの毛』(198ページ・1,600円+税)の出版記念パーティーが、関係者によって執り行われました。これは2008年7月に應典院舞台芸術祭(space×drama)にて前年度の優秀劇団として協働プロデュースにて公演された同名の作品が、この11月、創英社より刊行されたことを祝ってのことでした。
サリngROCKさんはspace×drama2007での「愛情マニア」でOMS戯曲賞の大賞も受賞。今後の活躍にさらなる期待が高まります。
コラム「結」
まちを共有する感覚
「オープン台地 in OSAKA 」(主催:上町台地マイルドHOPEソーン協議会)が2012年2月 3日、4日、5日に開催される予定だ。今年で2回目となるこの企画は、ツアーや建築案内などのコンテンツが約20個用意されており、各ディレクターがそれぞれの視点でまちを捉え、編集し、紹介する。主に20代後半から30代の若い世代が企画を担っており、私も全体運営の一人として関わっている。普段は入ることのできない上町台地ならではの建物、気になっていた場所、見過ごしていた面白い空間を知るきっかけになるような内容作りを心がけた。
また、建物などを知ることで、そこで行われている生活者の日常を知ってもらいたいという思いも強い。企画にあたりとりわけ意識しているのは「生活(住む、働く、遊ぶ)」というテーマである。
「大阪の背骨」と言われる上町台地は、大阪市の地理的中心を南北に細長く切り取ったエリアである。歴史が積層し、時代ごとの文化と新たな生活が日々折り重なっているような場所だ。大阪城などに代表される歴史的な建造物や日本でも有数の寺院密集地帯があり、タワーマンションやオフィスビルが建ち並んでいるかと思えば、そのそばに商店街やどこか懐かしい長屋が軒を連ねる。
都市部にあり広いエリアであるがゆえに、多様な生活が営まれている。上町台地の住人であり職場もある私は、その独特の生活に触れる時、自分もまちの共有者のひとりであるという感覚になる。
企画を通し関係者がまちのことを知り、地域の人ともつながり、時にはお酒を酌み交わし、楽しいこともつらいことも共有して新しい一歩を踏み出せる原動力になれば、私はひとまず成功だと思う。地域と人との繋がりを大事にし、継続していくこと。今までもそのようにして上の世代から次世代へまちを引き継いできたのではないだろうか。
1982年生まれ。生活者対象の家造り勉強会を開催。家に関する専門家と共に基礎から周辺知識を伝える。住宅戸数が足りている今、それでも新しく建てるなら、社会資産として価値がある家を、と活動を続ける。上町台地マイルドHOPEゾーン協議会では、会員として企画運営などに携わる。平成23年開催「オープン台地in OSAKA〜上町台地の生活鑑賞ツアーコレクション2010/2011〜」統括ディレクター。東日本大震災の影響で親を亡くした子どもを支援する団体、NPO子ども達の自立を支援するネットワーク事務局。
Interview「語」
山﨑都世子さん(映画監督)
釜ヶ崎のおっちゃんたちをカメラで追う。
フィクションとドキュメンタリーを自在に
横断しながら「人」を撮り続ける原点とは。
應典院での第18回コミュニティ・シネマで上映した「3.11 A Sense of Home Films」に、世界各国20人の作家とともに参加した。釜ヶ崎のおっちゃん達が演じる紙芝居劇「むすび」の姿を、3分11秒のショートフィルムに焼き付けた。日本最大の日雇い労働者の町・大阪西成の釜ヶ崎。実はこの町を舞台にした作品をつくるのは3回目。1994年、当時通っていたビジュアルアーツ専門学校の課題のために、ふらりと訪れたところから始まった。「天王寺で町ロケをしながら一人でテクテク歩いて西成にたどりついたのですが、それまで西成という町すら知らなかったんです。でも人がすごく生き生きしてる。人を知りたい、見たいと思っていたんですね。でも周りの人たちには、危ないと言われました。でも怒られたら『ごめんなさい』、撮らせてもらったら『ありがとう』というスタンスで続けました。」
釜ヶ崎に初めて足を踏み入れてから、約17年経ち、今回3分11秒という新たな枠組みを携えて久々に西成に戻ってきた。「そもそも震災の前に、原点に戻るためもう一度西成を撮ろうと思っていました。でも学生当時の若くて怖いもの知らずの頃から年月が過ぎたこともあって、初めは不安でした。そんな中一人で歩いていたときに、朝早くてあくびをしてしまったんです。その時、前から来たおっちゃんに「あくびしたらあかん!」っていきなり言われて、おもわず大きな声で「はい」と返事をしたんです。そこでスイッチが入りましたね。あ、私、気持ちがあがってる。もう大丈夫やって。」
ただ、この17年間で、釜ヶ崎の風景も大きく変わってきたという。「いい意味できれい。でも悪い意味でキレイすぎる。行政のおかげで路上生活者も減って、町もきれいになりました。でも人間、衣食住が与えられるから幸せなのではないということも感じます。」
さらに、釜ヶ崎を闊歩する若者の姿も増えてきた。それは一方で社会問題に対する若年層の関心領域が広まってきたことや、バックパッカー用のゲストハウスの増加、昨今のコミュニティ・アートへの注目の高まりなど肯定的な側面もありながら、他方でハートがない若者の姿も気にかかる。「釜ヶ崎でカメラを向ければ、どこを撮っても絵になる。その安易な着想や雰囲気をもっている若者もいますね。でもいろんな意味で一段とおもしろい町になってきていると感じます。」
東日本大震災を経て、日本人の死生観も大きく変化しつつあるといわれる中で、今後のテーマとしては「生と死」を軸にしていきたいと語る。「生と死について考えだしたのは2、3年前。当時、友人や知り合いの自殺が相次いだんです。その時『生きようよ』って思ったんです。表現が悪いかもしれないけど、西成のおっちゃんたちは何回か死んでます。故郷や家族も捨て、名前も変え…でも、それでも生きてるんです。」復興のドラマではなく人間の基盤にスポットをあてる。「『死んだと思って生きようよ』そういうのを撮りたいと思っています。」
編集後記〈アトセツ〉
2011年の「今年の漢字」は「絆」とされた。大方の予想の通り、という声もある。大規模・広域・複合型の激甚災害である東日本大震災は、各所に爪跡を残し、人々の魂を大きく揺さぶったためだ。その揺さぶりは「絆」ということばが中点となり、一定の振幅を保ったとも捉えられるだろう。
ちなみに1995年は「震」であった。阪神・淡路大震災は言うまでもなく、世の中を震撼させた一連のオウム真理教事件も重ねってのことだろう。この両者を比較してみると、「震」は〈あの日〉を忘れてはならないという戒め、「絆」が〈あの日〉を起点に自らを律していこうという誓い、そんな違いを見いだすことができそうだ。要は、戒と律の構図にあるのでは、ということである。
転じて、2011年の流行語の一つには「無縁社会」が挙げられた。いみじくも、つながりのなさが問題とされた後、つながっていこう、というメッセージが重ねられたのだ。ただ、言うは易し、である。果たして、誰と、誰に、どこまで、どのようにつながるのか、あるいは、今、つながりを生み、育み、つなぎ、時にあえて断ち切ろうとしているだろうか。
應典院ではこの数年、1月にコモンズフェスタを開催してきた。しかし今年度は会期を3月にずらすことにした。無論、関西の人々の〈あの日〉は1・17と挙げる人も多い。しかし、3・11という〈あの日〉から今を思う、そんな9日間になれば、と願うところである。
(編)
