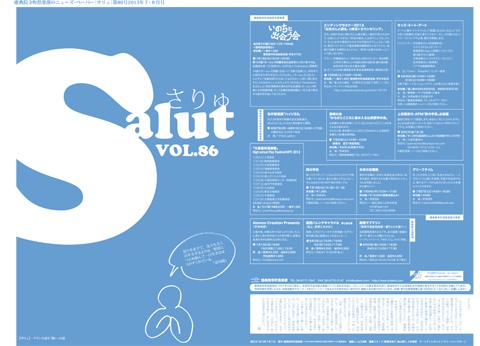
サリュ 第86号2013年7・8月号
目次
レポート「舞台芸術祭space×drama2013」
コラム 西田亮介さん(立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘教授)
インタビュー 伊藤伸二さん(大阪スタタリングプロジェクト・大阪吃音教室)
編集後記
巻頭言
怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、堅固につとめ励んで一日生きるほうがすぐれている。
「法句経」
Report「個」
墓場を見下ろす劇場でのリアルな生に迫った演劇祭
7劇団の「競演」
毎年、夏の風物詩となっているのが應典院舞台芸術祭space×dramaですが、2013年度は通常より変則日程での開催となりました。去る6月16日、4月の下旬から約3ヶ月にわたって開催されてきた7劇団の参加による演劇祭が、無事、幕を閉じました。時期がずれたことで、鑑賞する方々の関心がどのように変化するか、心配を重ねていたものの、結果としては各公演とも大盛況とのうちに終えることができました。実際、例年、事務局で発行している、全劇団を特別料金で鑑賞できる「共通パス」も、早々に完売となっていました。
1997年の應典院再建時より続いているspace×dramaは、その名を「舞台芸術祭」としているとおり、開始当初は演劇以外の表現も盛り込まれていました。しかも開催時期も「芸術の秋」の実施でした。とはいえ、應典院の空間の有り様から、2003年から現在まで「演劇祭」として定着してきました。演劇祭としての特徴を「若手劇団の支援」に置き、平日のみの短期集中型と、週末を盛り込んだ通常の公演とを組み合わせ、一定の歴史を重ねてきました。
毎年の演劇祭の個性は、開催の半年ほど前から開かれる、参加劇団の代表者による「制作者会議」によって定まります。この会議は、上演回数や作風の違いを超えて、互いの経験交流を重ねる貴重な機会ともなっています。そして、1回あたり2時間前後の協議を通じ、それぞれの創意工夫が共鳴することで、演劇祭と自公演の双方の充実がもたらされていきます。とかく、長く開催してきた事業は、事務局による方向付けや、前例に縛られる場合があります。しかし「それでいい」ではなく「それがいい」と納得のいく方法を探り、毎年の個性が際だっていくことになります。
前例に縛られない創作
参加劇団が変わっても、例年実施されていることがあります。共通チラシの発行、前年度の公募団体から選出された劇団による「協働プロデュース公演」の実施、そして演劇祭の幕引き時に全劇団による公開での「クロージングトーク」の開催、などです。共通チラシは演劇祭のテーマ「可能性の交差点」を図案化した横断歩道を模した柄を取り込みつつ、大きさや色合いなどは劇団間の議論で決まります。そうした議論を牽引するのが、前年度の経験から勝手を知っている「協働プロデュース公演」を担う劇団です。
今年度は「劇団壱劇屋」が協働プロデュース公演の対象劇団でした。昨年度の参加の折には、沈黙劇を盛り込みつつ、圧倒的な音響と照明機材を駆使した舞台が話題となりました。四面舞台で展開された1時間半あまりの物語に、この1年の飛躍と成長をまじまじと感じた壱劇屋はもとより、あわせて今年の参加劇団も、古代バビロニアとの往復(かのうとおっさん)、ワンシチュエーションながら登場人物の伏線の効果的な錯綜(匿名劇壇)、バイオリン生演奏を加えたことによる戯曲の世界の重層化(ミジンコターボ)、方言によるリアリティの追求(カンセイの法則)、一人11役の挑戦(劇団東京ペンギン)、サンタクロースという統一モチーフを2公演から接近(劇的☆ジャンク堂)など、実に個性豊かな演劇祭となりました。
小レポート
捨てず、携えて…
生きづらさと共に生きる 去る6月22日、午前に開催の應典院寺町倶楽部の「会員のつどい」に続けて、午後より第66回寺子屋トーク「生きづらさを生きる~情報社会における<役割>を求めて」を開催いたしました。ゲストは通信制高校への教育支援や中退予防などに取り組むNPO法人D×Pの今井紀明さんと、近著『ネット選挙』(東洋経済新報社)が高評の社会学者、西田亮介さんでした。
今回は座席を扇形に組み、共に80年代生まれのゲストと、密な対話ができる環境としました。若者たちは「孤立」の中でも生きづらさは捨てられないと言う今井さん、それを「世代のせいにせず時代の問題として捉える必要がある」と西田さん。会場からは「今日、来ていない人にこそ、こうした場に足を運んでもらえるように」や「制度を求めるだけでなく、自らの提案や行動を」など、提案や誓いの声も。変化に富む現代をどう生き抜くかを考える、貴重な共有体験の機会となりました。
小レポート
からだとこころに〈染み入る〉
難病からの救済を本願とする観音菩薩の一つから名をお借りした「楊柳の会(からだとこころに染み入る仏教医学の会)」が今年度から應典院の共催事業として、主催の楊柳の会(代表:川浪剛さん)と二人三脚で始まりました。
初回は山内宥厳さんを特別ゲストにお招きして、天然酵母のパンのこと、また、二人一組で行う「楽健法」についての楽しいお話をお伺いしました。途中、山内さんがお焼きになった「風変わりでまともな」天然酵母のパンに参加者がほっとする時間もありました。お寺が地域社会に開き、人へ「<染み入る>学びの場」としての月一度の機会を大切にしていきます。
小レポート
育成と伝達の場としての高校演劇祭
今年も應典院が高校生で賑わう季節がやってきました。HPF(Highschool Play Festival)2013は、新しく会場にドーンセンターが加わり、参加校も総勢29校となりました。應典院を会場とする高校12校が7月20日から31日まで連日公演を行います。HPF常連の強豪校から新参加の高校まで、個性的なラインナップが揃います。
6月17日から19日まで実施された会場下見見学会と技術講習会でも、高校生達がプロの照明や音響担当のスタッフから指導を受けていました。若い俳優の育成の場だけでなく、スタッフにとっても経験を伝達する貴重な機会となっています。
コラム「知」
古くて新しい情報社会
「情報社会」という言葉は、一見数多の学術用語同様、「Information Society」の輸入概念のように思える。しかし、そうではない。
1950年代に、当時日本でも放送が始まったテレビと、その社会的影響から、梅棹忠夫が「情報産業」という言葉を使ったことがその起源といわれている。諸説あるが、世界的に見ても相当早かった。
以来、林雄二郎、増田米二、公文俊平といった先達の手で、日本では情報社会のあり方についての議論、すなわち情報社会論が―幾分、未来学的で楽観的な側面を含みながら―議論され続けてきた。ダニエル・ベルやアルビン・トフラー、ハワード・ラインゴールドらの手による欧米の情報社会論とも呼応しつつも、独自の発展を遂げてきた。
だが現在ではどうだろうか。インターネットの世帯普及率が90%を越え、人々はいつでも、どこでもインターネットに接続できるスマートフォンを手に歩くようになった。ところが、筆者が受け持っていた講義で、「情報社会という言葉を聞いたことがあるか」と問うと、学生たちは一様に「そのような言葉は聞いたことがない」という。彼らは一昔前と比べて相当高度な「情報社会」を、無自覚なままに生きているのだ。
情報技術は人々の生活に深く浸透し、影響を及ぼすようになっているにもかかわらず、人々自身はそのことに無自覚になっているのかもしれない。かつての先達の議論が参照される機会は乏しくなっているようだ。
言葉や概念は問題の所在を指し示し、共有することを促す。2013年4月には公職選挙法の改正が行われ、今夏の参院選からネット選挙が部分的に解禁されることになった。今一度、「情報社会」について考えなおす時期かもしれない。
西田亮介
(立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准教授)
1983年生まれ。専門は情報社会論と公共政策。社会企業家の企業家精神醸成過程や政策としての「新しい公共」、情報化と政治、地域産業振興等を研究。東洋大学、学習院大学、デジタルハリウッド大学大学院非常勤講師等を経て現職。共編著・共著に『「統治」を創造する』(春秋社)『大震災後の社会学』(講談社)等。
Interview「認」
伊藤伸二さん(大阪スタタリングプロジェクト・大阪吃音教室)
吃音はどう治すかではなく、どう生きるか。
「あきらめる」とは「明らかに見る」ということ、
認めることから始まる悩みとのつき合い方とは?
1965年に、吃音の当事者として「どもる人のセルフヘルプグループ言友会」を設立。当時は、吃音を治療するための民間吃音矯正所はあったものの、「当事者が集う」ためのグループの存在は珍しい時代だった。その中でこの先進的な試みを始めたきっかけは、大学生の時に、同じくどもる人たちと吃音矯正所で合宿をした経験であったという。「1ヶ月寮に入って、吃音克服のために上野の西郷さんの銅像前や山手線の電車の中で演説しました。自分と同じ悩みを抱える人たちと過ごすことで、仲間と出会う有り難さや安心感を知ったんです。これまで孤独に生きてきた人間だったので、もうあの寂しさに戻りたくないという強い思いがめばえましたね。」
しかし、1ヶ月を終えても結局吃音は治らなかった。それは、ありとあらゆるアルバイトを経験してもやはり同じ結果だった。「対人恐怖症も克服したくて、飛び込みの営業やキャバレーのボーイなど、いろいろ経験しましたが、忙しい時にどもるのでよく怒鳴られました。でもどんなに苦しくても1ヶ月続けるということを自分に課していました。」
「でもなぜか僕はどもりを治すことをスパっとあきらめることができたんです。あれだけ治したいと思っていたのにねぇ。それは自分が立ち上げたグループの仲間たちと毎週1回集まって語り合うことで、吃音を治すよりも、どもりであることを認めるという生き方を選ぶようになれたからです。『あきらめる』の語源は『明らかに見る』ということといわれています。実はこれが一番難しいのですが、生きる上で一番大事なことだと思います。」
親しくしていたスキャットマン・ジョン氏(吃音を公表した米国人ミュージシャン)にも、「あなたは、どもりが治ったからではなく、どもりを認めたから今の人生がある」と伝えた。彼は何度も頷いて共感してくれたという。
ただ現実には、吃音は治さなくてもいいという考え方は主流ではない。「『治らないと決めよう』と言っているのは世界中で僕だけなんですが、それを支えてくれているのは、應典院で開催している大阪吃音教室のメンバーです。」
1986年に大会会長として京都で主催した「吃音問題研究国際大会」は、今年6月のオランダ大会で第10回目を迎えた。「アルコール依存やホスピスなどの領域では、病気とどう生きていくかという考え方が浸透してきていますが、吃音に関しては『治す・改善』にこだわる傾向が40年前から変わらないですね。」
「先日、東日本大震災の被災地にスクールカウンセラーとして入った臨床心理士の知人が、『子どもたちは、地震や津波は自然災害だからと受け止め始めている。世間が考えるようなトラウマを抱える子どもは実はそれほど多くない』と話してくれました。子どもたちの「レジリエンス」=「自然治癒力」を改めて感じましたね。今まさに、自分で自分のことをサバイバルしていく力が問われているのではないでしょうか。」
すべての人間が悩みとともに暮らす中で、それを不本意として生きるのか、納得しながら生きるのか。自分自身を認めることで、「矯正」から「共生」へと変換していく治癒力の大切さをあらためて提示する。
編集後記〈アトセツ〉
久々の寺子屋トークで「生きづらさを生きる」という主題を掲げることにした。ゲストは新刊『ネット選挙』が高評の西田亮介さんと、かつて「自己責任論」の渦中に置かれた今井紀明さんであった。対象と観点は違えど、それぞれに教育の現場に携わる二人の若者の対話から、変化の時代をどう生き抜くのか、その知恵を探りたかった。詳細は別稿に譲るが、多彩な参加者層が得られたことに、應典院という場所の力を見た。
昨年度のコモンズフェスタで鎌仲ひとみ監督の映画『内部被ばくを生き抜く』を上映させていただいた。放射線被害に焦点を当てた映画の上映後、監督と会場との対話の時間を設けた。その際、会場からの質問に「オセロのように、四隅をとれば、世界は変わる」と監督は応えた。実はこのときの印象が、今回「生きづらさ」を扱うことにした源流となっている。
以前「生前」という表現に対して、ふと疑問を抱いた。なぜなら通常この言葉は「死ぬ前」の出来事に対して用いられるからだ。ではなぜ「死前」のことが「生前」に置き換えられるのか。それは死と生の連続性と、生の儚さが重ねられる所以かもしれない。
人の夢と書いて儚いと読む。人の為と書いて偽りと読む。文字に拘ると、普段は捉えていないことに視点が向きそうだが、だからと言って、言葉に囚われすぎると、生きづらさが先に立つ。それでも人は夢を抱き、人の為に、時代を生き抜く、そんなささやかな決意を大事にしたい。(編)
