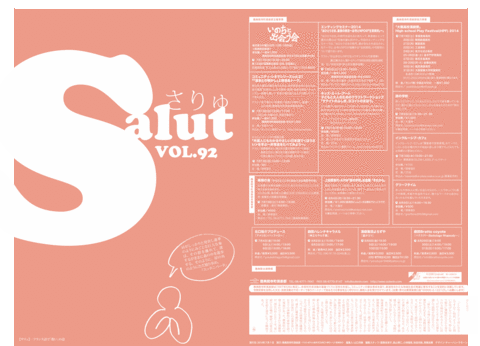
サリュ 第92号2014年7・8月号
目次
レポート「space×drama2014」
コラム 一ノ瀬かおるさん(少女漫画家)
インタビュー 坂下清さん(写真家・映画監督)
編集後記
冒頭文
肩がしっかりと発育し蓮華のようにみごとな巨大な象は、その群を離れて、欲するがままに森の中を遊歩する。そのように、犀の角のようにただ独り歩め。
『スッタニパータ』
report「祭」
時代と世代を超え交差する
「可能性の交差点」
多様な担い手の競演の場
ゴールデンウィークの最中から始まった應典院舞台芸術祭space×drama2014は、6月9日の「劇団太陽族」による公演で、無事終幕を迎えることとなりました。今年も多くの皆さまのご来場を得て、多彩な劇団の競演の場づくりを楽しんでいただくことができました。主催団体として、鑑賞していただいた皆さま、また公演していただいた劇団、全ての方々にお礼申しあげます。ここで改めて今年の演劇祭について振り返ることにいたします。
今年は4劇団の参加による演劇祭となりました。公演順に、その概要を紹介することにいたしましょう。まず参加劇団の中でも唯一の学生劇団である「劇団てんてこまい」は、犬と人間の寿命に着目しつつ、映画の構成に着想を得て、死ななければならなかった理由を問いかけるものでした。続く「劇団大阪新撰組」は80年代に産声を上げ、今回の公演が38回目を数える老舗ですが、演出を若手が務め、実際にある大阪市内の施設や文化などを長編の中に織り込みながら、人々の暮らすまちでは何を大切にすべきなのかを問う作品に仕上げられました。そして3番手の「がっかりアバター」は、日常の延長にある非日常な世界を、いくつかの題材を効果的に重ねることで描き出すものでした。
ちなみにspace×dramaでは2008年度より感想ブログ(http://spacedrama.exblog.jp)を開設しているのですが、そこでも多くの方が「がっかりアバター」は「いつもと違った」などと綴られていました。実はspace×dramaは、2003年度から演劇に特化した舞台芸術祭として開催しています。そして、参加劇団の中から次年度に企画運営に協力いただける劇団を、事務局が組織化した審査会により「優秀劇団」として選出しています。4番手「斬撃☆ニトロ」の公演は、新撰組が活躍した時代と現代とを時間旅行する高校生を主人公にした物語でしたが、日替わりゲストを迎えて展開された劇中劇でも、このことが触れられた回がありました。
異才のリレーで育む技
ちなみに優秀劇団の選考対象は4劇団でしたが、それらの競演に続いて、昨年の公演で選出された「匿名劇壇」が5番手を務めました。7つの劇中劇が編み上げられていき、最後に一つの場面につながるという緻密な構成は、優秀劇団ここにあり、といった品格を感じさせたことでしょう。さらに、今年は優秀劇団の後に、事務局により招聘された劇団による「特別招致公演」として「劇団太陽族」が続きました。1982年結成という圧倒的な経験知をもとにした、舞台芸術としての演劇がどのようなものだったのか、ぜひ上記の感想ブログで追体験くださいませ。
なお、今回は2003年の演劇祭化から10年という区切りを迎えたことを記念し、例年開催しているクロージングトークを拡大版として実施いたしました。設立5年以内の若手劇団による平日のみの演劇祭の時代、設立年数不問で新旧世代が切磋琢磨する週末公演を含めた演劇祭の時代、そして今年の公演団体、と3部構成で行いました。当時を振り返り、合意形成の難しさや、お寺の本堂での公演で留意したこと等が語り合われました。来年は「がっかりアバター」の皆さんと共に場づくりにあたります。
小レポート
芸術と福祉の可能性
包摂的な社会へ
「障害者の芸術表現」をテーマに語り合う「インクルーシブ・カフェ」が、今年度から應典院の協力事業としてはじまりました。2000年から2004年まで應典院ディレクターを務められていた川井田祥子さん(大阪市立大学都市研究プラザ)が主催されており、新たにスタートした企画ではありますが、これまでの歩みを引き継ぐ試みであると言えます。
4月は『アウトサイダー・アート:現代美術が忘れた芸術』(光文社新書)を著されている甲南大学の服部正さん、5月は社会福祉法人みぬま福祉会「工房集」アートディレクターの中津川浩章さんをお招きし、それぞれの視点からお話をうかがいました。後半には、サンドイッチを頬張りながら参加者同士で交流する時間もあり、定員いっぱいの盛況となっています。誰もが共に生き、創造性を発揮できるinclusive(包摂的な) 社会に向けて、思いを巡らせる場になればと願っています。
小レポート
高校演劇祭で学び、表現する
6月10日から12日、Highschool Play Festival(HPF)2014の会場下見見学会と技術講習会が行われました。高校生の大きな声がロビーに響き、元気いっぱいな3日間でした。高等学校演劇大会と違い、上演時間の制限もなく自由に公演が出来ます。
演出効果を高めようと、音響・照明の技術を関西小劇場で活躍するスタッフが伝えていました。本番は7月19日から31日(休演日あり)。ウイングフィールド、シアトリカル應典院、吹田メイシアターの3会場で開催され、全23校の内10校が應典院で公演します。講習会で学んだ事が存分に発揮されるよう祈っています。
小レポート
上町台地マイルドH0PEゾーン助成事業報告会
5月10日に、追手門学院大阪城スクエアで同助成事業報告会が行われ、昨年のキッズ・ミート・アートとコモンズフェスタを報告致しました。「地域へ溶け込んで協働していきたい」という思いで、開かれたお寺の面白さ、異色さが詰まった両企画に取り組んできましたが、まだまだ地域と繋がれていないという課題が見えてきました。参加されたどの団体からも、「上町台地」で繋がりを深め、歴史ある地域の魅力を知ってもらいたいという思いを強く感じた報告会でした。今年度も引き続き、関係性の更なる構築を目指します。
コラム「居」
仏教と
当事者研究について
私の兄は統合失調症です。家庭内での居場所は家族の心がけで確保できたとしても、社会での居場所を作ることは家族の手だけでは無理でした。そこでたどりついたのが、べてるの家(※)です。
ところが、べてるの家は定員オーバー。私たちは落胆しましたが、諦めたくありませんでした。どうにかして、べてるの家のような居場所が作れないか。ですが、場づくりに関して何の知識もない私にできることではなく、私は神頼みならぬ「ご縁頼み」をすることにしました。“大阪にべてるの家を作りたい”。この考えに共感してくれる人を探し、その人たちが集えば、それが結果的に居場所を作ることになると思ったのです。
その当時、私は應典院主催のイベントによく参加していました。應典院で行われている取り組みは興味深いものが多く、集う人々も魅力的な人ばかりでした。ここに集まる方々なら、べてるの家に興味を持ってくれるのではないだろうか?そう考えた私は、應典院の山口洋典さんと観光家の陸奥賢さんに、べてるの家の向谷地宣明さんをご紹介しました。その求心力は大変なもので、話は一気に弾み、あれよあれよという間に「仏教と当事者研究プロジェクト」が立ち上がったのです。
私はこのプロジェクトの発起人と命名していただいていますが、べてるの家と應典院を結んだご縁の一本のより紐に過ぎず、実際のところは特に何もしておりません。私よりずっと前からべてるの家に関心を寄せられている方、このプロジェクトを通してはじめて知った方、その皆さんが場を動かして下さっているからです。
兄に居場所を。この私のわがままから始まった「ご縁頼み」。しかし、私のわがままは私だけのわがままではない気がしています。このプロジェクトの先にあるものが、べてるの家とは全く別物になろうとも、私はそのセレンディピティを楽しませていただこうと思っております。
一ノ瀬かおる(少女漫画家)
1983年11月22日生まれ。2009年「イパーシャ」にて白泉社よりデビュー。著作に「未少年プロデュース」「神様のソナタ」(白泉社刊)など。写真はべてるの家のスーパースター早坂潔さんと、浦河で行われたべてる大会にて。
■Twitter Ichinose_Kaoru
■HP http://kaorukoru.blog66.fc2.com
※1984年に北海道浦河町に設立された、精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点。
詳しくは、サリュ91号レポートをご参照ください。
interview「映」
坂下清さん
(写真家・映画監督)
どのようにして私たちは死者と関わるのか。
コミュニティ・シネマvol.21上映作品を作
る中で、生じ始めた宗教観の変化とは。
岩手県宮古市では、お盆の時期、夜になると家の前で松に火をつけて燃やす風習がある。その風習「松明かし」の起源を追ったドキュメンタリー映画『波あとの明かし』が、7月13日(日)に行われるコミュニティ・シネマvol・21で上映される。『波あとの明かし』が初の長編監督作品となる坂下清さんに、作品に込めた想いを伺った。
「僕自身、地元である宮古で、小さい頃から松明かしに対して『これは何なのかな』という疑問は持っていました。でも、調べても全く資料がなくて、作品という形にするのは難しいだろうと手をつけなかった。東日本大震災が起きた後、変わらずに行われているのを見たときにはじめて、『災害で亡くなった方の霊が無事に帰ってこられるよう、火を照らしているのかも』と直感的に思いました。確かな先行きが見えないまま、制作をはじめたのが2013年のお盆です。」
だが、プロの写真家としてメディアとしての写真の特性を知っているがゆえに、松明かしや震災に関して写真で表現することには抵抗があった。「写真って〈死〉なんですよね。撮る人間の主観で生きている空間を切り取って、時間を止めて、額縁に入れて飾るじゃないですか。まるで棺桶に入れられるような。いま生きている街や人々を、棺桶に入れることはしたくなかった。生きている、続いている、ということを描きたかった。それで映画という手法を使うことにしました。」
映画を撮ると決めてから、勉強のために他のドキュメンタリー映画も見始めたが、最も参考にしたのは柳田國男ら、民俗学の著作だという。「民俗学って、あるテーマを考察するために色んな人の話を聞き取っていく。皆それぞれ違うことを語るので、究極的な結論は出せないわけです。僕の映画も色んな人へのインタビューを中心に構成されています。結論は明確に提示せず、見た人が考えられる余地を残しました。ドキュメンタリー映画の専門家には、ひどく酷評されましたけど(笑)。」
これまでも全国各地で上映会を行ってきた。映画を客観的に批評するのではなく、映画に触発されて自分自身について語りはじめる観客の姿が印象に残っているそうだ。「青森や京都の方は『うちの地方ではこんなことやるよ』と話してくれましたし、『お祖父さんが亡くなった時のことを思い出した』という兵庫の方もいらっしゃいました。描いているものは宮古の風習ですが、似たような体験が一つぐらい見る人にもあると思う。生者が死者とどう関わることができるのか、改めて考える機会にしてもらえれば嬉しいです。」
自らの意志でコントロール不可能な制作体験を通して、監督ご自身の価値観にも変化が生じた。「インタビューしても、皆さん自分の思った通りに答えてくれない(笑)。撮れば撮るほど、自分の想定していたものから離れていく。大きな流れに身を任せるしかないですよ。その結果、目に見えないもの、答えのないものに対するアンテナが磨かれて、以前は『自分は無宗教だ』と思っていたんですけど、生活の中で様々な神さま仏さまに手を合わせている自分のことを、すごく信心深いじゃないかと感じました。今は、特定の宗教ではない『日本人の信仰』に興味を持っています。」
編集後記〈アトセツ〉
「こんなことして何になるんですか?」時折、そうした問いが投げかけられる。特に取り組みに懐疑的な方から寄せられる傾向があるように思う。だからこそ丁寧に言葉を選んで説明せねばならない。
「終わった後には新たな言葉が生まれます。」実践の意味がわからないと問われたとき、大抵はそう説明させていただいている。実際は「まったく新しい言葉」ではない。2つの言葉の組み合わせや、ある分野の専門用語が全く違う領域で用いられることで、実践の場に光が射していく。
先日、秋田光彦住職らと北海道浦河町の「べてるの家」と関連拠点を訪れた。2月に始まった「仏教と当事者研究プロジェクト」の一環だ。「自分を見つめるとか、反省するとか言うよりも、『研究』と言うとなにかワクワクする感じがする。」(『べてるの家の当事者研究』医学書院・刊、3頁)かねてより研究対象とされてきた精神障害の当事者らが、自らを共に研究するという新たな取り組みに、多方面からの注目と関心が高まっている。
また、比喩表現の活用でも新たな意味がもたらされる。例えば應典院舞台芸術祭space×dramaで用いられてきた「可能性の交差点」もその一つだ。今年の閉幕時の議論の折、過去に優秀劇団に選出された団体が、この言葉を用いてお寺での演劇祭の意味を語った場面があった。應典院の再建とあわせて生まれた演劇祭が、現在の形となり十年。使い続けた比喩が、継続への意志決定を促す道具になった瞬間であった。
(編)
