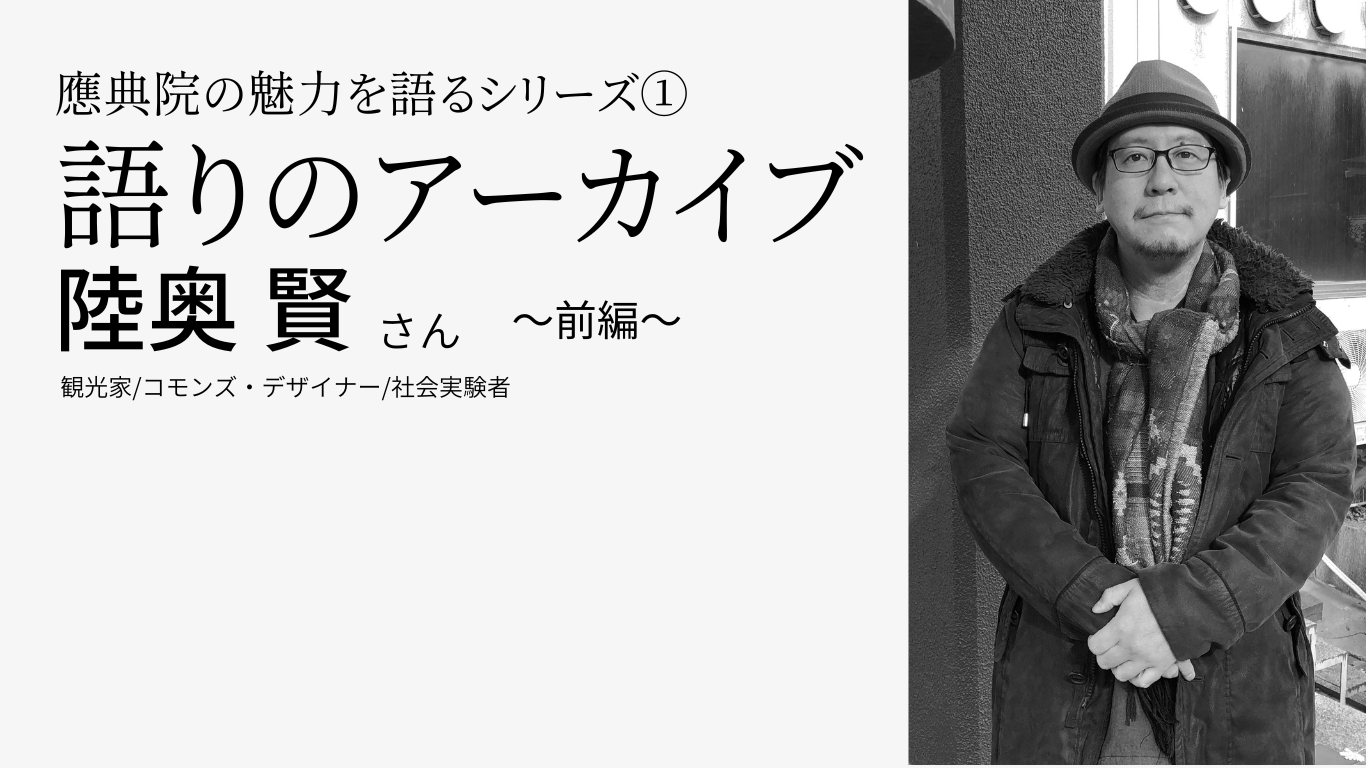
2025/2/25【語りのアーカイブ】應典院の魅力を語るシリーズ①陸奥賢さんインタビュー(前編)
應典院のWEBサイトは現在、事業やイベントの告知のみならず、過去事業の開催報告などのアーカイブ、あそびの精舎としての取り組みや狙いを仏教の教えと共に伝えていくことを主な目的としています。情報の提供だけでなく、読み物としても充実したサイトになっていくことを目指して、この度、新たにインタビュー記事の連載を始めることにしました。應典院に縁のある方々から、これまでの應典院との関わりや、場所としての魅力や可能性について語って頂きます。
第1弾は、これまでに應典院で様々な企画を実践され、應典院を長らく外側から見つめて来られた陸奥賢さんにお話を伺いました!
インタビュアー/中嶋悠紀子
陸奥 賢(むつ さとし)
観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。1978年大阪・住吉生まれ、堺育ち。最終学歴は中卒。15歳から30歳まではフリーター、放送作家&リサーチャー、ライター&エディター、生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)の大阪ガイドなどを経験。2007年に地元・堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞(主催・堺商工会議所)。2008年10月から2013年1月まで「大阪あそ歩」(2012年、観光庁長官表彰受賞)プロデューサー。2011年から「大阪七墓巡り復活プロジェクト」「まわしよみ新聞」(読売教育賞最優秀賞受賞)「直観讀みブックマーカー」「当事者研究スゴロク」「演劇シチュエーションカード 劇札」「歌垣風呂」(京都文化ベンチャーコンペティション企業賞受賞)「死生観光トランプ」などの一連のコモンズ・デザイン・プロジェクトを企画・立案・主宰している。大阪まち歩き大学学長。著書に『まわしよみ新聞をつくろう!』(創元社)。2024年4月から日本初のコミュニティ・サイクル・ツーリズム「いわき時空散走」のプロデューサーに就任。
阪神淡路大震災の後悔が、「大阪七墓巡り」を駆り立てた。
―陸奥さんはこれまでに應典院で様々な企画を実践され、應典院を長らく外側から見つめて来られたと思いますが、最初の出会いはどのようなものでしたか?
應典院との関わりは2012年のコモンズフェスタの企画委員に選ばれたのが最初です。僕は前年の2011年に「大阪七墓巡り復活プロジェクト」※を始めたんですが、秋田(光彦)住職とはそこで出会いました。七墓巡りをするにあたって、まず春先に墓巡りの勉強会をしてから8月15日に色んな人を連れて歩きました。そのさいに「七墓巡りを語る会」というトークイベントをやったんですけど、そこに突然、秋田住職が現れたんです。そこで「なんで七墓巡りをやるんや?」みたいな話になりまして。それが最初の出会いです。
―そもそも、陸奥さんはなぜ、「大阪七墓巡り」をやることになったのでしょうか?
七墓巡りをやろうと思ったのは、東日本大震災がきっかけですが、元を辿ると阪神・淡路大震災です。震災当時、僕は17歳で。当時はいきがってた若者で、いろんなバイトをしながら演劇や映画を作ったり、路上で流しみたいなこともやっていました。ただ本当は小説家になりたかったんです。明治、大正、昭和前期の文豪たち、特に安吾、オダサクなど無頼派に傾倒していたんですが、いざ自分が書くと1行で挫折してしまいました。自分の書くものはなんて幼稚なのだろうと。知識も教養も人生経験も何もかもがないと絶望してしまったんです。でも若いしパッションだけは有り余っているから何かしらの表現がしたくて、それで映画や音楽、演劇などにどっぷりはまっていました。そんな時に起こったのが阪神・淡路大震災です。こんなことをいっては怒られそうですが、当時の僕は不謹慎ながらも「世の中が劇的に変わっていく」とワクワクしているような自分がいました。1995年は地下鉄サリン事件が起きた年でもあって、バブル経済が崩壊し、戦後民主主義が瓦解して「失われた30年」が始まっていくんですが、僕は屈折している若者だったので、そういう崩壊、瓦解、堕落していく時代精神に、妙に同調していくような気分があったように思います。
また僕はいまでいうところの「カルト3世」でして。思春期の頃から母親(母親はカルト2世になるのですが)がはまっていた某在家法華教団の教えに嫌気がさして、家や親戚に反発して、一人で生活したいとバイトでの自立を考えて、だから高校も途中で辞めて大学も行ってないんです。でもバイト先の先輩が通う大学の講義なんかには勝手に出入りしていた時期があって。そこで阪神・淡路大震災以降の話ですが、日本各地にある原発も地震によって危ないのでは?と危機を覚えた学生さんたちが大学の構内で「原発は危険だ!廃止せよ!」と訴えてビラ配りをしている現場に出くわしたことがあるんです。しかし僕はそういう学生運動的なものが性に合わなくて「なにいうてんねん」って笑殺したんです。
だから2011年に東日本大震災が起きて、その後、福島原発が放射能漏れの事故を起こしたときは「しまった!」と思いました。1995年の時点で既に原発と震災の危険性について考え、行動してきた人がいたにも関わらず、僕自身は、その様子を見ていたのに何もしなかったことを反省して後悔したんです。この災害は当然、想定できた。僕一人がなにかやっても世の中が変わるということはないだろうが、僕は社会の一員として行動する責務を果たしていなかったのでないか?と。
阪神・淡路大震災の経験者やボランティア経験者で、東日本大震災の現場でも積極的に携わって活動している人がいます。例えば山口洋典さん(元・應典院主幹)は阪神・淡路大震災の時からボランティア活動を積極的に行い、その後、大学の先生になると、学生たちと一緒になって、いろんな震災現場に出向いて、まちづくり、次世代の育成などに携っておられます。じゃあ自分はどうだろうか?と自問して。自分には何ができるだろうか?と自分なりに、いまの社会をよくする方法を模索していて、そこで思い付いたのが大阪七墓巡りです。えらい、凄い飛躍ですけど(笑)
要するに僕が思ったのは、東日本大震災では津波などの被害で原発事故が発生して、放射能漏れが発生して、その汚染の影響が半減、消滅するのに何千年、何万年もかかるという想定だにしない事態が発生した。こんなにも危険な原発を誘致したのは、簡単にいえば選挙の結果で、原発誘致を良しとする政治家たちがいて、それを支持する有権者がいたからということになるんですが、しかし、そもそも、こんなにも大きなリスクがある原発の設置なんてことを、いまの人たちだけで、民主主義の選挙制度の中だけで決めてしまって良いのか?という疑問が起こったわけです。いまの日本の、世の中の方向性やベクトルは、生きている人たちの投票や選挙で決定されていきますが、そもそも、この社会は、生きている我々だけのものではないでしょうということなんです。世の中や社会というのは、過去の先人たちから受け継いできたものですから。また、やがて生まれてくるこどもたちや次世代に大事に渡していかないといけないものです。なのに原発事故の放射能汚染で町に何万年も人が住めなくなるとか、お墓参りが出来なくなるということは過去の先人たちを蔑ろにし、未来に生まれる子どもたちの生存権を脅かす選択をしてしまったということなんです。自分たちの住む世界は自分たちだけのものではないということ。我々には先人から未来の子どもたちへバトンを渡す中継ぎの存在に過ぎないのだという自覚や慎ましさが必要だし、より良いものを次世代に渡していくために我々は何をするべきで、何をやめるべきなのかを慎重に考えていかなければならない。イギリスの作家チェスタトン※が「死者の民主主義」を尊重せよといっていますが、そういう先人たちの存在を気付かせてくれるのが、ある意味、お墓参りなんですよ。お墓は死者のモニュメントで、このまちや命や社会は、死者から受け継いだものであることを知ると同時に、だから生きている人たちだけで決めることの横暴性に気付かせてくれるのではないか?と。そういう狙いで大阪七墓巡り復活プロジェクトがスタートしました。
無縁の人を供養することこそが、慈悲の本質である。
―秋田住職は、陸奥さんの「大阪七墓巡り」のどういう部分に関心を持たれたのでしょうか?
普通、お墓参りというのは有縁の方の供養で行うことが多いですけど、大阪七墓巡りは江戸時代からの風習で無縁仏を供養しようという巡礼なんです。僕は、この無縁の人を巡るのがええなと思っていて。無縁仏になる人って、縁もゆかりもなく、一人で孤立して死んでいった、社会の一番の弱者なんじゃないかと思うんですよね。究極の社会的弱者。でも、かつてのこのまちに、確かに生まれて生きて、そして死んでいった人ですから。そういう人たちのことを慮る、考える、想いを馳せるという時間を自分の中に持ちたいなと。そういうことがいまの社会に必要なことじゃないかと思ってるんです。まぁ、でも、いま話している七墓巡りの意図とか意義とかは、最初から、こんなにちゃんと言語化出来ていた訳ではなく、当時は直観的に始めていました。毎年毎年、七墓巡りを続けながら、また、いろんな人になぜ七墓巡りを?と説明を求められる中で、少しずつ整理されていったという感じです。
秋田住職が来られた時も、うわ!本職の人が来た!と思ってびっくりして(笑)。その時は七墓巡りの僕の狙いなどは拙い言葉でしか伝えられなかったと思うんですが、秋田住職からは「無縁大慈悲」という言葉を教えてもらいまして。つまり、七墓巡りのような無縁の人の供養こそが慈悲の本質であると、それを僧侶でもなんでもない、一市井の若者が始めようとしたことを面白がって頂いたんじゃないかなぁ?それで、その年の終わり頃に應典院に呼び出されて、来年のコモンズフェスタという総合芸術文化祭を應典院でやっているから、その企画実行委員をやって欲しいと。…ここまでが前置きです。長い!(笑)
※大阪七墓巡り:江戸時代からの風習で、お盆に七墓を夜通しかけて巡拝し、無縁仏を供養して功徳を得るというもの。七墓巡りするという大義名分で、夜通しまちを出歩くことが可能なので娯楽、遊興の一種として流行した。150年ほどの歴史があるが、文献はあまり残っていない。七墓巡りをきっかけに男女の関係となり、酔って喧嘩になるなど、風紀の乱れも多々問題とされたが、陸奥さん曰く、このような聖俗が入り交ざった歴史や文化に面白さを感じるという。
※チェスタトン:ギルバート・キース・チェスタトン(1874年5月29日 – 1936年6月14日)イギリスの作家、批評家、詩人、随筆家。
※コモンズフェスタ:1998年から2020年まで開催された、アートと社会活動のための総合芸術文化祭。互いの知恵や人脈を共有し、物事や出来事への認識と発想を豊かにする目的で、年次のテーマに即して企画されたトークイベント、演劇、展示、講演、ワークショップなどが多数開催された。

