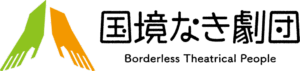【開催報告】あそびの精舎フォーラム 国境なき劇団 のと・かが「ボラまち」演劇プロジェクト『のとがたり』上映会
8月27日に国境なき劇団による、のと・かが「ボラまち」演劇プロジェクト『のとがたり』上映会が開催されました。
その開催報告レポートをお届けします。
演劇的手法を用いて被災地でのケアの在り方を模索する「国境なき劇団」
災害があったとき、救助隊は72時間以内の救命を目指す。
間もなく到着した国境なき医師団は現地で心身の治療をする。
やがて、どこからともなくやってくる国境なき劇団は、その後しばらく続く心のケアにあたる。
国境なき劇団は、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震を経て2021年4月に立ち上がった非営利の舞台芸術団体です。 上記をスローガンに掲げ、平時は過去の災害経験や立場を共有する取り組みを行いながら全国にネットワークを敷き、大規模災害が発生した際は、被災地域の要望をもとに、被災者の心のケアのために活動する演劇人を支援する活動を行っています。
《国境なき劇団》 https://borderless-theatrical-people.net/
▲阪神淡路大震災から25年目を迎えた2019年1月17日、アートと社会活動のための総合芸術文化祭「コモンズフェスタ」に参加し、国境なき劇団の前身である「TFAP」として初めてのワークショップを開催しました。
能登での活動
2024年1月1日の能登地震発災以降、国境なき劇団は、金沢の演劇人やアート関係者らと協働し、仮設住宅の集会所を定期的に訪れ、落語や二胡の演奏、絵本の読み語りを行うなど、被災された方々との交流を続けてきました。
金沢のアーティストたちが被災地で生活されている方々と交流し、関係を築いていく中で、度々「忘れられてしまう不安」を耳にすることがあったと言います。
「忘れられる」というのは、メディアで度々伝えられるような「地震の怖さ」や「悲惨な被災地の様子」のことではありません。その土地に古くから伝わる行事や習わし、食べ物、そしてそれらの中で培われた人々の繋がりや暮らしーそれらを私たちは文化と呼びますが、それらが瓦礫の撤去とともに失われてしまう。無かったことにされてしまう。ここに言いようのない感情がこみ上げるのだと、ぽつりぽつり口にされたというのです。
瓦礫が取り払われ、更地に新しい機能を備えたまちが再建されるだけでは、本当の復興とは言えないのではないか?復興は「まちの復興」と「心の復興」がセットで語られなければならないのではないか?そのために演劇で出来ることは何だろうか。私たちは日々、悶え続けています。
国境なき劇団は定期的に能登を訪れ、復興の経過を観察してきました。 同じポイントで撮った写真を撮り並べると、発災時からインフラはかなり復旧が進んでおり、「遅々として進んでいない」と批判するのは申し訳ないほど、現地の人たちのたゆまぬ努力と頑張りを続けて来られたことが分かると、代表の八巻寿文は話します。
他方、発災からちょうど1年経過した頃、仮設住宅に入居した方々に対して行われたアンケートによると「復旧・復興の進捗を感じていない」と回答した人が63%にものぼるという調査結果があったといいます。これは、目で確認できる復旧・復興と、心で感じる復旧・復興には乖離が生じているのかもしれない。私たちはそのような仮説を立て、その土地の文化や人々の暮らしの記憶について、演劇的アプローチで伝承・継承する取り組みを行うに至りました。
▲ボラ待ち櫓。現在は観光用のモニュメントとして残っています。
のと・かが「ボラまち」演劇プロジェクト「のとがたり」 「のとがたり」
のと・かが「ボラまち」演劇プロジェクトとは、穴水に伝わる日本最古の漁法「ボラまち」に、ボランティアの精神と「待ち」の姿勢を重ね、常に立ち返るべき原点と考えて活動を始めたプロジェクトです。能登に所縁のある方たちのところへ2人1組でインタビューに出向き、その方の言葉に耳を傾け、語られる物語の中から言葉を拾い、戯曲に書き起こしたひとり10分ほどの戯曲を、金沢の俳優ができるだけ正確に描写するーこうして生まれたノンフィクションの作品が「のとがたり」です。「のとがたり」は2025年3月30日に、石川県立図書館だんだん広場にて上演されました。ディレクションと構成・演出を担当したのは、発災後、珠洲市正院の仮設住宅の集会所で交流を続けている金沢の演劇ユニット、演芸列車「東西本線」。上演後は、現地での活動報告や、観客を交えての座談会を開催し、全国各地から、80名を超える方にお越しいただくことができました。
国境なき劇団 2025年3月30日 のと・かが「ボラまち」演劇プロジェクト『のとがたり』
https://borderless-theatrical-people.net/archives/1065
▲2025年3月30日、石川県立図書館だんだん広場にて上演(写真:フォトグラファーNOD野田啓)
應典院、気づきの広場での上映会
他地域でも能登に心を寄せられている方に「のとがたり」を観ていただきたいという思いから、8月27日(水)、應典院気づきの広場で開催することとなりました。冒頭は代表・八巻寿文より「国境なき劇団」はメンバーが演劇の創作・上演を目的とする団体ではなく、被災地での活動を重ねる中で意義が浮かび上がってくる理想のようなものであること、またそれを問い続ける集団であるという説明がありました。そして、東日本大震災時には支援を受ける側だったのが、支援をする側の立場になったことで初めて見えてくる景色があったと話がありました。
▲大阪上映会チラシ
演芸列車「東西本線」による金沢市民芸術村と珠洲市正院での活動
上映後は、「のとがたり」の作り手である演芸列車「東西本線」の東川清文さん、西本浩明さんらとオンラインで繋ぎ、「のとがたり」に至るまでのお話や、まちの復興状況や、今も毎月訪問されている仮設住宅の集会所でのコミュニティの有り様の変化についてのお話をいただきました。東川さんは、普段は介護福祉士としてのお仕事に従事されながら、金沢市民芸術村のドラマ工房の市民ディレクターも務められています。能登半島地震以降、発災後に金沢市内に開設された1.5次避難所(災害発生後、避難所〈1次避難所〉から避難先〈2次避難所〉へ移るまでの間、一時的に滞在する場所)に、介護福祉士としてボランティアに入られたことが関わりのきっかけだったそうです。
その後、国境なき劇団と出会うことになり、東日本大震災では避難所に人が集える場所(コミュニティ作り)が必要とされた話を伺い、金沢市民芸術村で「オープンサロン」を開催。避難されている方だけでなく、誰でも集える場所として現在も継続して開かれています。
▲金沢市民芸術村オープンサロンチラシ
後に、国境なき劇団メンバーと共にお見舞いとして能登の仮設住宅を訪問したことをきっかけに、珠洲市の正院の仮設住宅の集会所が機能していない(人が集まる仕組みがなければ安否の確認もできない)という状況を知り、その場で役者と落語をやっていることを伝えると、「じゃあ来月から何かやってよ」という話になり、毎月1回、西本さんと正院を訪問し、落語の催しをやることに繋がっていったそうです。「(隣の金沢の人たちですら)時間が経つと誰も来なくなる。次の約束があると安心する」という言葉を避難所で生活される人たちから聞き、今も継続して様々な芸術活動をされている方と訪問を続けられているそうです。
最近は避難所と仮設住宅と自宅に戻って暮らされている方々の間で起こる分断の話や、集会所と個宅の復旧の優先順位を、どのように折り合いをつけるのかという対立が起きている話などがあり、避難所や仮設住宅が抱えるメディアで報道される話(目に見える復興)と現地の人が感じていること(心の復興)に乖離があるのではないかという話がありました。
▲大阪上映会の様子
「のとがたり」の創作について
西本浩明さんは「のとがたり」の構成・演出を担当されました。このような、インタビューした内容をそのまま俳優が舞台で再現する、という取り組みは初めてだったそうで、「観に来た人に何を伝えれば良いのだろう?」という根底の部分で苦労があったと言います。
意識したことは、「敢えて震災のことを聞かない」ということです。こちらが欲しい言葉を聞くのではなく、その人の普段の暮らしの話を聞こうと。インタビューをしていると、結果として震災の話は出てくるが、その人たちの半生が見えてくる。その半生の中から「震災」という経験が浮かび上がってくるように思います。
インタビューは俳優が行い、その中から10分程度の話を俳優が選び上演されています。しかし、震災の大変さや心地の良い言葉を選ぶのではなく、ドキュメンタリーに近いけれどもドキュメンタリーとは言えない、その絶妙なバランスが難しい。手探りで稽古を進める中で、この取り組みは非常に面白く、やるべきものだしやる意味があるという手応えはあるが、それが観客にどう受け取られるのか。3月に上演し、質疑応答で様々な意見を客席からいただいたことで、そこで初めてホッとした、やろうとしたことが伝わったと実感できたと話されました。
お茶菓子をいただきながらの座談会
会場を円形に組み換え、お茶菓子をふるまいほっこりとした雰囲気に。参加者からも様々な感想や質問が上がりました。
・60代以上の方のインタビューが多かったのはなぜか
・美術が無い分、方言がとても魅力的でその土地がイメージ出来た
・稽古のプロセスについて詳しく聞かせて欲しい
・どれくらいの関係性でインタビューを実施したか?
・インタビューされた方の年齢や性別と近しい俳優が演じた方が良いと感じる理由はなぜか?(俳優は対象者に「なれる」と思って演じているのか「なれない」と思って演じているのか?)
これらの質問に対して、西本さんや東川さんは様々な可能性や方法を模索しながら、自分たちも手探りで明確な答えを持たずに取り組んだ部分があることや、インタビューした方に対して誠実であることを一番大切に取り組まれたと、言葉を選びながらひとつひとつ丁寧に答えられていました。
被災地で生活される方も、時間の経過と共に心境に変化が起こるので、今回だけでなく、1年後、3年後と「のとがたり」を継続させたい。新たに別の方にインタビューされるのも良いが、同じ方にインタビューを重ねることで見えてくることがあるかもしれない。
と、西本さんは今後の展望についても語られました。 今後も国境なき劇団と、演芸列車「東西本線」の取組みにご注目いただけますと幸いです。
大阪上映会を終えて。演芸列車「東西本線」西本浩明さんより
石川県を拠点に活動している演芸列車「東西本線」の西本浩明です。 この度、8月27日に應典院で上映された「のとがたり」の構成・演出を担当しております。
この作品は本年3月30日に石川県金沢市の石川県立図書館で初演を迎えました。 実在する方々にインタビューを行い、俳優がそのテキストを抜粋・構築した上でトレースするという形で行われるパフォーマンスは、一般的に想像される「演劇」とは異なる点も多いため、観客にどう受け止められるだろうかと心配だったことを今でも憶えています。
今回は被災地域以外での上映ですので――しかも、ライブパフォーマンスではなく映像での鑑賞ですので――やはり、どのような反応が返ってくるだろうと心配でした。
結果から述べると、その心配は杞憂に終わりました。 鑑賞後のトーク・座談会から私どもはリモートで参加して、会場のお客様とリアルタイムでお話しをしたのですが、そこから感じられたものは震災という出来事に現在進行形で向き合う人々への関心と共感です。
大阪は過去に震災を経験し、また関心の高い人が集って下さっているということも勿論あるでしょう。 しかし、当事者の声をありのまま伝えようと努力する俳優の姿勢があれば、ちゃんとその言葉は観客に届き、その先は観客が補完してくれるのだということを、二度の上演を経て実感します。 それは翻って演劇というものの本質を触るような作業なのかもしれません。
「のとがたり」は終わったわけではなく、インタビュー対象を広げたり、その後を追ったインタビューを行ったりと続いていくものです。 ゆっくりでも共に歩いて行きたいと思います。