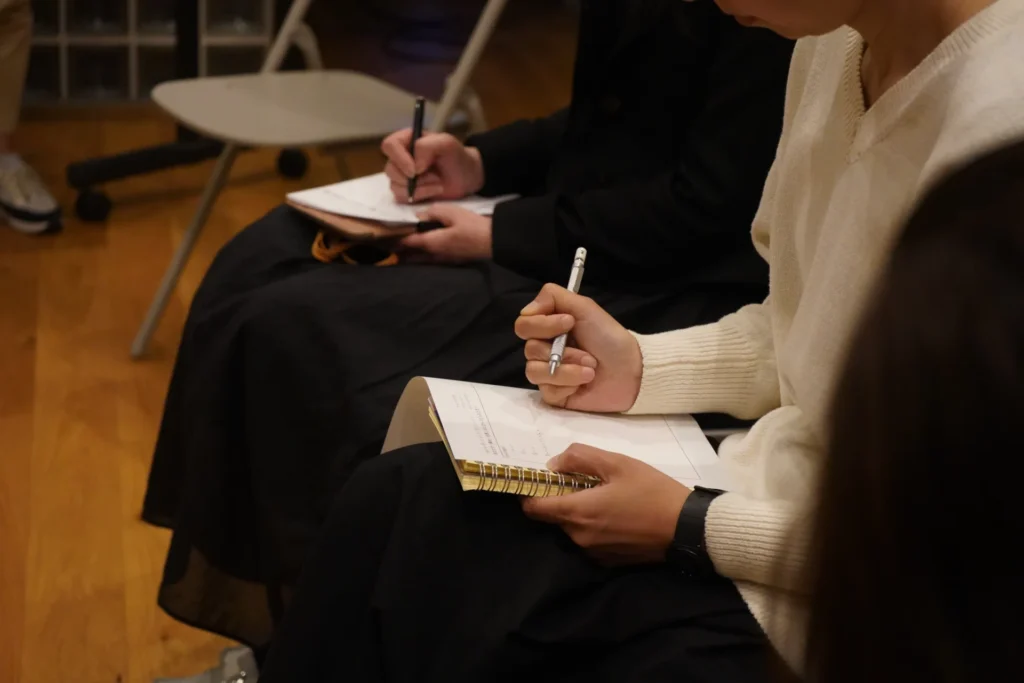【開催報告】西田 亮太朗 むぬトーク vol.2レポート:日常の小さなグリーフ=喪失に目を向ける
2025年5月12日、大阪・應典院にて「むぬトーク vol.2 『日常の中のちいさなグリーフ=喪失に、目を向ける』」を開催しました。
身近な人の死に向き合うとき、多死社会の訪れを感じる知らせを聞いたとき、自分のこれからを想像したとき、思い出の品を手放すとき——日々の暮らしで、私たちは様々な「終わり」に遭遇します。しかし、そこから生まれるもやもやと、じっくり向き合える機会はそう多くありません。人もいきものも文化も、「終わり」と隣り合わせの今。私たちは「終わり=死」から「これからの時代をどう生きるか」を考えることができるのではないか——「むぬトーク」は、そうした「生と死」にまつわる問いを分かち合う場です。
今回は、心理カウンセラー・袰岩奈々さんを迎え、「グリーフケア」を取り上げました。グリーフケアとは、一般的には死別ケア・遺族ケアとも呼ばれ、身近な人の死やペットロスなどによる深い悲しみや痛みに寄り添い、立ち直りを支援することを指しますが、一方で袰岩さんにとってのグリーフケアとは「日常の中に起こるちいさな痛み」に目を向けること。
私たちは生きる中で大小さまざまな「喪失の痛み」を抱えます。
私は呼ばれていないけど、友達が楽しそうにしているのをSNSで見かけてしまったとき、他人のささいな言動に心がちくっとしたとき… そんな人間関係の中だけでなく、自分より長い年月を生きてきた大木を切り倒さないといけないとき、釣った魚の命をいただくときなど、他のいきものとの関係の中でも痛みを感じるかもしれません。
今回は袰岩さんの実践を足がかりに、日常生活の中でつい見過ごしてしまいがちな喪失にまずは気づくこと、そして、参加者一人一人のそれぞれの痛みに向き合いながら、多死社会におけるこれからのケアを考えました。
本記事では、DeepCareLabインターンの西田が、「むぬトーク vol.2 『日常の中のちいさなグリーフ=喪失に、目を向ける』」のレポートをお届けします!
日常の中のちいさな喪失に気づくことからケアが始まる
はじめに、袰岩さんがグリーフケアに関わり始めたきっかけと、現在のグリーフ観を持つことになった経緯が語られました。
袰岩さんがグリーフという言葉に出会ったのは、東京で心理カウンセラーとして活動していた頃でした。きっかけは、ある友人から届いた一通のメール。「ステージ4のがんと診断され、5歳の子どもの行く先をどうするべきか悩んでいる」という相談でした。
そこから調べていく中で出会ったのが、アメリカ・オレゴン州にある「ダギーセンター(The Dougy Center)」という施設でした。ここは、家族を亡くした子どもたちのためのグリーフケアを行う施設として知られています。
そして、2011年の東日本大震災を機に、袰岩さんは日本でも活動を行っていたNPO「キッズ・ハート・トゥー・ハワイ」に出会います。この団体は、元々ダギーセンターで働いていたメンバーによって運営されており、袰岩さんは彼らのもとで本格的にグリーフについて学ぶことになります。
中でも、彼女に大きな影響を与えたのは、キッズ・ハート・トゥー・ハワイの創設者の一人、シンシアさんからの教えでした。
その教えとは、「グリーフは大きな死(喪失)ではなく、日常の中のちいさな喪失も含めたもの」であり、「傷つきに気がつくことからケアが始まる」というものです。
私たちは生きる中で大小さまざまな喪失の痛みを抱えます。
しかし、そうした感情は些細なこととして見過ごされたり、抑え込まれてしまうことが多いものです。
一般的に「グリーフケア」という言葉は、一般的には死別ケア・遺族ケアとも呼ばれ、身近な人の死やペットロスなどによる深い悲しみや痛みに寄り添い、立ち直りを支援することを指しますが、袰岩さんは、そうしたちいさな喪失をすくい上げることこそが、グリーフケアの出発点になるのではないかと語ります。
↑袰岩さん(左奥)がグリーフケアに関わり始めたきっかけを聞く参加者のみなさん
袰岩さんの話題提供を終え、ここからそうしたちいさな喪失をすくい上げるためのさまざまなワークに移っていきます。
WORK1:心の動きを言葉で捉え、自分の気持ちと向き合う
最初に行われたのは、「最近の出来事を感情とセットで語る」というワーク。参加者同士で二人組を作り、ここ数日間の出来事を思い出しながら、それに伴う気持ちを言葉にして語ります。このワークで重要なのは、「事実を上手く説明すること」ではなく、「そのとき、自分がどんな気持ちだったか」を添えて話すこと。例えば、「京都に行ってカフェに入ってコーヒーを飲んだ」だけではなく、「久しぶりに顔なじみの店主に会えて嬉しかった」「出かけるのが少し面倒だった」など、出来事に伴う心の動きを紡いでいきます。
感情を語ることへの抵抗感|参加者からのリフレクション
ワークを終えて、参加者からはさまざまな感覚がシェアされました。
「普段頭の中だけで考えていることを表に出すこと自体が新鮮に感じられた」
「相手との関係性がまだ浅いと、感情だけを語ることに抵抗がある。共感してもらうには、まず状況説明をしないといけないと感じた」
「感情を語るボキャブラリーが衰えていると感じた。「嬉しかった」「楽しかった」「辛かった」くらいしか言葉が出てこない」
「予定表を確認するなど、未来のことは考える機会は多いが、過去のことはあまり振り返らない傾向にあるので、まずここ数日間の出来事を思い出すこと自体が難しかった」
感情を伝えることに対して、構えてしまったり上手く言葉にできなかったりする——そんな苦手意識には、私も共感する部分が多くありました。
特に、「感情の表現は関係性が深まった相手でないと難しい」という声にはうなずく人も多く、多くの参加者が、感情を言語化することが特別な関係の中だけで許される行為だと捉えているように感じました。
誰が聞いても同じように受け取れる情報を優先し、曖昧でとりとめのない感情はつい後回しにされてしまう。「話すこと」と「感じること」の間にある大きな溝のようなものがこのワークを通じて見えてきました。
複層的で矛盾をはらんだ自分の気持ちとの付き合い方
無意識のうちに蓋をしていた感情を自覚する中で、ときにどう対処したらいいか分からない複雑な感情に出会うことがあります。私も、このワークを通じて日常生活を振り返りながら、「自分が悪いけど、少し悲しかった」「良い人だけど、何故か好きになれない」など、簡単に整理することができない複層的で矛盾をはらんだネガティブな感情が浮かび上がってきました。
そうしたネガティブな気持ちに対して、どう付き合っていくべきか。袰岩さんは、「気持ちと行動」「矛盾する気持ち」「抑圧されやすい感情」という三つの観点を意識して整理することが重要だと語ります。
気持ちと行動
感情自体に善悪はないと言われています。なので、ネガティブな感情を抱くこと自体は仕方がないものとして受け取っていくと、少し扱いやすくなります。ただ、それを行動に繋げてしまうのはダメ。たとえば不登校の子どもから「死にたい」という相談を受けるときも、「死にたい」という気持ち自体は否定しない。でも、それを「死ぬ」という行動に繋げるのは待ってほしいと彼らに伝えながら、どうにか別の方法で切り抜けられないかとともに模索しています。
矛盾する気持ち
矛盾する気持ちを持つことも当たり前のことです。「死にたい」と思いながら「生きたい」と思うこと、「あいつが嫌いだ」と言いながら、好きな気持ちもあること。不登校で、「学校に行きたくない」と思いながら「行けたらいいな」とも思うこと。そうした矛盾した気持ちがあっても、それ自体はおかしいことではないし、むしろ、よく起こっていることだと受け止めることが重要です。
特に、感情を誰かに伝えるときは、相手を混乱させたくないあまり、感情を単純化してしまうことがあるそうです。実際には、私たちの気持ちは複層的で、矛盾をはらんでいるのが当たり前。そうした感情が自分の中から湧き上がってきても、すぐに分かりやすい言葉で整理しようとせず、「そう感じている自分」をそのまま受け止めてみることができれば、少し楽になる気がします。
抑圧されやすい感情
怒り、落ち込み、嫉妬、親密感という四つの感情は特に抑圧されやすい感情だと言われています。なので、もやもやを感じたときは、この中のどれか、あるいはいくつかが同時に起こっているという可能性を考慮して日常生活を振り返ると、例えば、「あのとき、少し羨ましい気持ちがあったから、ついトゲトゲした口調になったのかな」というように気がつくことができます。
こうした手がかりを持っておくと、日常生活のなかで自分の正直な気持ちに気づきやすくなるだけでなく、それに蓋をせずに受け止めることができるようになり、そして、他者の気持ちも受け止める力に繋がっていくと、袰岩さんは語ります。
WORK2:喪失と再生のプロセスをなぞり、自分なりのグリーフケアを考える
傷ついたことに気づかない限り、ケアを始めることさえできません。
もしも傷を負っていることに気づかずに放っておいたり無意識のうちに感情を抑え込んでしまったりすると、それがいつの間にか大きな傷口になって、取り返しのつかない状態になっている可能性もあります。
日々生まれるちいさな傷に気づき、受け止め、回復する——このプロセスの繰り返しが、大きなグリーフが向き合うための土台を培っていくと、袰岩さんは語ります。
次に行われたのは、そのためのデモンストレーションとも言えるワーク。袰岩さんはこれを「ハートワーク」と呼んでいます。
ワークの手順は以下の通りです。
-
好きな折り紙を2枚選ぶ
-
片方をハート型に切り取る
-
自分が大事にしている人・モノ・コトをハート型の紙に五つ書く
-
ハート型の紙を破く
-
台紙の方に貼り合わせて再生させる
ワークの意図はあえて冒頭では説明されず、参加者は黙々と作業を進めていきます。全ての工程が終わったあと、袰岩さんからこのワークの背景が語られました。
↑折り紙を使って行った「ハートワーク」
袰岩さんによると、このワークは「象徴的にグリーフを体験する」ためのものだそうです。
ハート型に切り取った折り紙に、大事にしている人・モノ・コトを書き込み、その紙を破る。そして、台紙の上に、破れた断片をのりやテープで貼り合わせていく。
そうした一連の作業が、喪失と再生のプロセスをなぞるように構成されています。ワークを振り返りながら、例えば、「私にとってテープみたいな存在って何だろう?」と想像力を働かせることで、喪失感を持っているわけではないときでも、グリーフケアについて考えるきっかけを作ることができます。
袰岩さんによる説明のあと、参加者同士でグループに分かれて、ワークの感想をシェアします。
私の入ったグループでは、参加者の一人が、心込めて書いたものを破るということに強い葛藤を覚えたと語っていました。
一度目はまだ破れたが、二度目からは心がえぐられたとのこと。
もう一人の参加者も、全部が全部抵抗感があったわけではないが、書いたものによっては破れなかったと語っていました。特に、過去に既に失ったことがあるものは破れなかったが、まだ失ったことがないものは破ることができたと言います。私も似たような感覚を覚えました。
一方で、特に何も感じなかったと語る参加者もいました。「形のあるものはいつか壊れるから」と話し、喪失に対するある種の納得感を持っているようでした。ただ、ハート型の紙を再生させていく中で、作品としての愛着が湧いてきたとも語っていました。
ワークを通して、感情を強く揺さぶられたという人もいれば、距離を置いて受け止めていた人もいたようです。対象への思いの濃淡やこれまでの体験の違いによって、湧き上がる感情に個人差があったのかもしれません。
そうした感じ方に違いが生まれるのは自然なことで、このワークを通じて何を感じたか・感じられなかったかを手がかりにして、自分なりのグリーフケアについて考えることに、大きな意味があるように思います。
日々の暮らしの中で抱える喪失の数々。
気持ちが沈んでいるときにこそ、それらを冷静に受け止め、回復するための手立てを見つけることは難しいものです。
だからこそ、あらかじめこうしたワークを通して傷に向き合う練習をしておくことが、いざというときに自分を支える備えになるのかもしれません。
WORK3:自分の痛みのサインに気づくことから、コンパッションの感覚を育てる
三つ目のワークでは、心に痛みを感じているときのことを言語化することを通じて、自分の痛みのサインに向き合いました。
参加者は以下の項目について書き出し、二人組をなってシェアします。
-
痛みの中で感じること(3つ)
-
体の状態
-
やりたくなること
-
やりたくなくなること
私が入ったグループでは、ある参加者は心の痛みを感じると、「無力感・悲しみ・苛立ちを感じる」「集中力がなくなる」「仕事も何もかも放り出して歩きたくなる」と話していました。別の参加者は、「喋りたくなる」「読書ができなくなる」と語っていました。
↑痛みを感じているときのことを言語化する
袰岩さんは、このワークで書き出した内容が「逆側から自分の感情に気づくための手がかりになる」と語ります。
例えば、袰岩さん自身は、「怒っているときにキッチンを無性に磨きたくなる」のだそうで、無意識のうちにキッチンを磨き出すとき、「自分は今怒っているのかもしれない」と気づくことがあるそうです。
このように、自分の痛みのサインをあらかじめ知っておくと、感情そのものからではなく、ついやってしまう行動や体の変化から逆算するようにして、内なる感情に気づくことができるのです。
また、参加者同士のやり取りを通じて浮かび上がったのは、痛みの感じ方やサインは多様だということ。袰岩さんは、こうした痛みのバリエーションに触れながら、グリーフケアにおける「コンパッション(共感)」の難しさや心構えに言及しました。
誰かと似たように感じている部分は共感されやすいけれど、多くの人と違う感じ方をしている部分は共感されにくいものです。そういうとき、「そういうこともある」とあらかじめ知っておくだけで、共感してもらえないときにあまり焦らずに済みます。また、誰かのことを共感できなかったときにも、自分が分かってあげられないことに対して申し訳なくならないです。
最後に、参加者一人ひとりが、これまでに経験した心の痛みをどう乗り越えてきたのかを振り返り、そのとき自分を支えてくれたよりどころを順番にシェアしていきました。
印象的だったのは、それらの多くが日常的な営みに根ざしていたこと。
「落ち着くまで眠る」「好きなものをいっぱい食べて落ち着かせる」「妻に一生懸命喋る」「風呂(水に流す)」「ラジオの雑談を聴く」… 言葉にしてみて初めて、「身近な営みが実は自分なりのケアだったのかもしれない」と気づかされます。私たちは自覚できていないだけで、常に自分の傷を癒しながら暮らしているのかもしれません。
だからこそ、自分の心の痛みに対して「大したことない」と蓋をしてしまわないことが大事なのだと思います。
「ちいさな喪失を当たり前のこととして認めること」の繰り返しが、自分の痛みを和らげるだけでなく、他者の痛みに寄り添うためのまなざし──コンパッションの感覚を育てていくのだと、袰岩さんは語ってくれました。
↑参加者一人ひとりが、これまでに経験した心の痛みをどう乗り越えてきたのかを振り返る
おわりに:さまざまな網の目からこぼれ落ちる喪失に目をこらす
「むぬトーク」のテーマとして掲げている「死」という言葉。
その言葉を、私自身どこか遠い出来事のように感じてしまうときがあります。
「日常の中で喪失に出会うことなんてそうそうない」——そう思い込み、グリーフケアへの備えがないまま、大きな喪失を体験したり積もり積もった心の痛みに参ってしまったりする。
そんな事態が起こりうるのは、私たちの生きる現代社会に、ちいさな喪失をすくい上げる網の目がないからなのかもしれないと、袰岩さんのワークを通じて実感していきました。
日々生まれる小さな痛みを言葉にして、誰かと共有すること。それは、「ちゃんと感じる」「ちゃんと気づく」ための準備運動のようでした。
<私>の小さな痛みに目をこらし、声を与えていくことが、誰かの痛みに寄り添うための感覚を培っていくのだと感じます。
 あそびの精舎 note
あそびの精舎 note
子どもからお年寄り、また祖先や未来の世代が集い、ともに「あそぶ」ことで、いのちのつながりに気づき、今の生き方を見つめ、生まれ死ぬまでの、暮らしをともに支えていく「ライフコモンズ」の拠点 應典院とDeep Care Labで運営
https://note.com/asobi_outenin