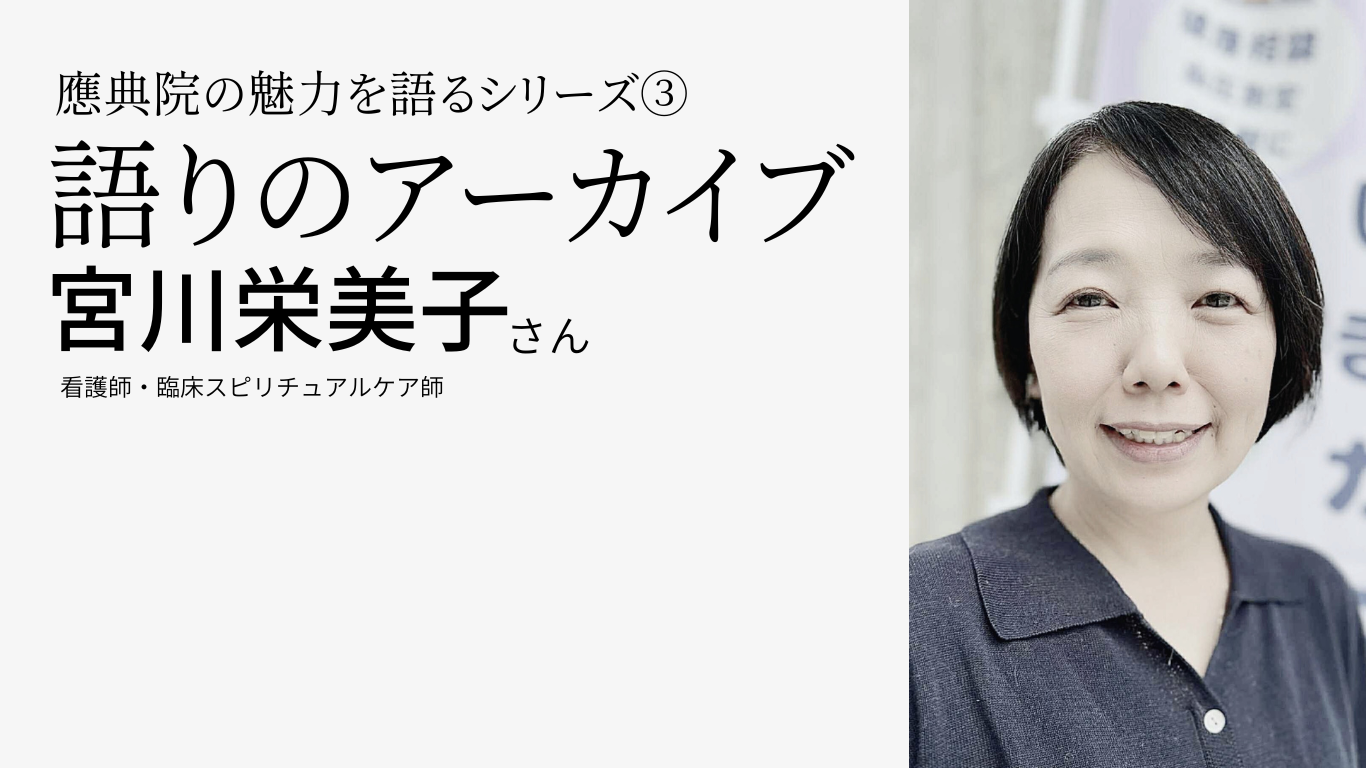
2025/7/27【語りのアーカイブ】應典院の魅力を語るシリーズ③宮川栄美子さんインタビュー
應典院のWEBサイトは現在、事業やイベントの告知のみならず、過去事業の開催報告などのアーカイブ、あそびの精舎としての取り組みや狙いを仏教の教えと共に伝えていくことを主な目的としています。情報の提供だけでなく、読み物としても充実したサイトになっていくことを目指して、この度、新たにインタビュー記事の連載を始めることにしました。應典院に縁のある方々から、これまでの應典院との関わりや、場所としての魅力や可能性について語って頂きます。
このたびは第3弾です。應典院の「おてらの保健室(まちの保健室)」は開室6年目に入りました。小さな場ですが、毎月コツコツ積み上がった保健室は、最近では地元の福祉や医療関係者も参加してくれるようになりました。そのコーディネーターが、看護師歴30年の宮川栄美子さん。病院にお勤めの傍ら、地域に開かれた看護を目指して、まちのケアセンターを一緒に育ててくれています。
そのご縁が広がり、いまはがん患者のサロンや子どもを亡くした親の集い、介護者カフェなどさまざまなケアの場所が生まれています。宮川さんにお話を伺いました。
(文責編集部)
宮川 栄美子(みやがわ えみこ)

宮川栄美子(看護師・臨床スピリチュアルケア師)
医療の現場、子育て、看護学校教員、大阪市平野区でのコミュニティナースの活動を経て、現在は臨床看護(入退院支援室)で勤務しながら、上智大学グリーフケア研究所、日本GRACE研究会にて「コンパッション」と「慈悲」について探求を続けている。「聴く」ことの可能性に魅了され活動中。應典院では「おてらの保健室&ともいきカフェ」を開いている。
ー應典院を最初に知ったきっかけは何でしたか。
グリーフを勉強しようと上智大学グリーフケア研究所大阪サテライト校に通っていたのですが、その時の同期の一人が、沖田都さんでした。沖田さんは大蓮寺・應典院の職員で、僧侶見習い中の素敵な人でした。それから意気投合したというか。初めて伺った時、なんとまぁスタイリッシュなお寺やなあと感心しましたが、改装されて、床の印象もすごく変わりましたね。色とりどりの蓮の中でお話ししている感じがします。
ーお世話していただいている應典院の「まちの保健室」はいかがですか。
私は、ケアと最初に出逢う場は病院や施設ではなく、暮らしの中にあってほしいと思っています。専門家と患者の関係だけでなく、多様な人たちがかかわりあうような。そのためにはコミュニティの場づくりがとても大切ですね。以前は、平野区でも同じようなことをしていたのですが、これも沖田さんのつながりで、2024年5月からこちらで活動することになりました。
應典院の「まち保」自体はコロナ初年の2020年から始まっています。もう6年目になりますね。寺町は生活エリアではないので、往来の人が立ち寄るという感じではないけれど、お馴染みの方もいらして、いい感じで続いています。檀家さんや幼稚園の保護者さんもふらりと来られる。人と人が温かく繋がれる場所になればいいなと思っています。
それと、(應典院のある)天王寺区は協力体制が充実していますね。社協(社会福祉協議会)さんや薬剤師会も入ってくださって、「多職種連携」が應典院の特徴です。地域のクリニックともつながりがあったり、可能性を感じます。
ー宮川さんが看護師を目指したきっかけは。
「女は仕事をすると嫁に行きそびれる」というような厳格な父に育てられ、その反発心から看護の専門学校へ行きました。別に憧れていたわけではないです(笑)。
神経難病に取り組んでいる国立病院に学生時代から含めて13年勤めました。いろんな患者さんに出会いましたが、療養がほとんどなので、若い私はお話を聞かせていただくばかりで。「家族でもない、病院の看護師でもない、あなただから話せるんだ」と。聴くことに目が開いたのはこの時の経験があります。
一般に看護師は必ずしも聞き上手ではありません。職場は時間との戦いなんですね。私も経験があるのですが、救急の前線では聞ける余裕はない。なので、今は京都の病院で、入退院支援室で多くは地域の高齢者さんですけど、もっぱら「聴くつなぐ仕事」についています。なので、家族との距離がすごく近いです。訪問看護の世界もそうだけど、家族ではない最も近い距離にいる第3者になりえる存在ですね。でも、家族になってはいけない。そのマインドに共感しています。
ー現在の應典院ではコンパッション・コミュニティについて、いろんな提案や発信を続けていますが、宮川さんはどうお考えですか。
お寺がコンパッション・コミュニティの中心になることは、理想ではないでしょうか。
仏教では「慈悲」を大切にしますね。私の尊敬するョアン・ハリファックス老師(米国の医療人類学者・僧侶)も、コンパッションは「共苦」ではなく「慈悲」と言われています。ケアすることは苦しみ疲れるものではない。潜在的に私たちのなかに存在しているよろこびそのものだと説明される。そのためには、家族だけでなく、多様な人たちが互いに見守り合い、まわりの力を借りて過ごしていくことが必要ではないでしょうか。そこでは専門職が専門職としてだけじゃなくて、ひとりの地域の人としてかかわっていく。だから施設でもない、家庭でもない、お寺という場所に魅力を感じます。
今年の2月から、隔月で「がん患者サロン」を始めました(次回8月10日)。緩和ケア医の森一郎さんが、まちに出ていく活動をされていたのですが、私がつないで、應典院で定期開催となりました。毎回、がんの患者さんやその家族らが20人くらい集まりますが、仏さまがいらしたり、お墓があったりする場所で、当事者の方々が話し合うこと自体が、コンパッションではないかと思います。
一つ一つが小さな細胞のようなコミュニティなんですね。ここでは哲学とかアート、まちづくりの場がたくさんありますよね。そういう場がつながって、應典院という細胞の塊となって、本体(人体)になればいいのかなと。
コンパッション・コミュニティを実現するためには、ひとつひとつの細胞(集うひとりひとり)をどれだけ大切にできるかということなのではないかと思います。
ー應典院あそびの精舎に期待されることがあればお願いします。
2024年のオープニングに参加しましたが、秋田住職がおっしゃった仏教の「遊戯(ゆげ)」のお話が好きです。あそびのなかにはやさしがあり、笑いがあり、やりたいという想いや、身体を動かすということがある。年齢にかかわらず、自分の欲求にどん欲に、思うがままにあることが、とても大切だと思います。一人でも多くのキラキラとした「あそび」の目(芽)を見つけられたらなと思っています。
