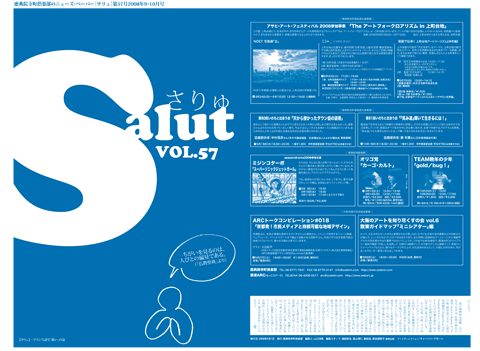
サリュ 第57号2008年9・10月号
目次
レポート 「第53回寺子屋トーク」
コラム 佐伯典彦さん(介護福祉士・介護支援専門委員)
インタビュー 山口洋典さん(浄土宗・應典院主幹)
編集後記
巻頭言
ちがいを見るのは、人びとの偏見である。
(「仏教聖典」)より
Report「艶」
未分なアートの価値について
生活の中に埋め込むアート
去る7月13日、恒例の「寺子屋トーク」第53回を開催いたしました。テーマは「生活の中にアートを取り戻す!」でした。加藤種男さん(アサヒビール芸術文化財団)をメインに、大谷燠さん(NPO法人DANCEBOX)、岡部太郎さん( 財団法人たんぽぽの家)、そしてセックスワーカーとしてまた性感染症に関するライターとして活動するタミヤリョウコさんの3名をゲストに迎えました。
1部は、加藤種男さんの基調講演。美術や演劇、音楽やダンスなど、表現形態からの観点ではなく、昔からの生活の知恵と「アート」の関連についてお話いただきました。「かつて祭りは生活の一部で、観客はなく全員が参加者だった。」この発言に象徴されるように、アートは観賞されるのみの存在ではなく、生活を営むあらゆる行為の中に埋め込まれた創造的な技術として捉えられるべきだ
と力説されています。
2部では、大谷さん、岡部さん、タミヤさんの順に、ご自身による実践報告があり、会場も巻きこんだディスカッションとなりました。それぞれが紹介した事例は、アートNPOやダンサーたちとともに新世界地域の盆踊りを復活させた「ビッグ盆!」、子どもたちが撮影した何気ない日常の写真をワークショップやインターネットを通じて幅広く共有する「世間遺産」プロジェクト、そして、性感染症予防啓発のためのリーフレットの編集発行についてでした。
芸術・生活双方の文化的発展
加藤さんの講演は、塩の話から始まりました。「工場にて製造されたNaClと、われわれが太古の時代より口にしてきた塩は別物ではないか」。そこから、純粋な要素だけで構成されたものがアー
トと呼べるのだろうか、という問題提起につながっていきました。
なお、今回2部で取り上げた事例は、すべて、実践家と参加者相互の関わりを重視した取り組みでした。「ビッグ盆」は、2006年に、今はなき「フェスティバルゲート」にて、途絶えていた盆踊
りを42年間ぶりに復活させたものです。そこには、アートに対する認識を「観賞」するものから「参加」するものへと変えるきっかけにしたいという当事者の思いが重ねられています。また「世界
遺産」ならぬ「世間遺産」は、子どもたちが100年後に遺したい風景を写真で切り取ってくるという取り組みですが、2004年当初から回を重ねる毎に、作品の中身よりも制作の過程を共有することが大事だと考えられるようになってきたとのこ未分なアートの価値についてとです。さらに、タミヤさんらによる「フーゾク利用者向けSTD(性感染症)パンフレット」は、仕事柄危険にさらされている風俗嬢に対してではなく、お客さんに対して普及啓発を行っている点に特徴があります。記事の内容を現役の風俗嬢が編集することで、男女間のよりよい関係性を見つめ直すことを狙っていると、関連するワークショップ等の取り組みと共に紹介がなされました。
後半は、これらの実践事例を議論の素材に、地域の文化的発展についての意見交換がなされました。アートに関する市民の「リテラシー」(選択眼)、多様な主体の連携を促進する「さばき手」としてのアーティストの役割、「みんな」で物事を決めるためには「待つ」ことが必要など、い
くつかのキーワードが出てきました。
これらの議論を通じて、「不快感や違和感をアートに見出すことで生きるためのヒントが見つかるのではないか」と、今回のテーマに対する一定の整理がなされました。いかにして芸術文化と生活文化の両側面を発展させていくことができるか、今後も議論と実践を重ねます。
小レポート
space×drama2008協働プロデュース公演突劇金魚「しまうまの毛」
昨年度の優秀劇団である突劇金魚が、應典院寺町倶楽部との協働プロデュースとして、さる7月2日~6日の日程でspace×drama 2008 のオープニングを飾った。当劇団を牽引するのは、代表であり作・演出のサリngROCK。ガールズロックと銘打つとおり、その作風は、女子に焦点をあてたものだ。今回の「しまうまの毛」も、女子寮と言う閉塞した空間で生きる女性たちを描き、彼女たちの屈折した価値観を表出させる。だが、サリngROCKはそれを自閉的に終わらせない。「あたしたち変態ですけどなにか?」と、人を喰ったような開き直りで、観る側へ逆に問いかけるのだ「あなたは、なにもの?」と。そのあっけらかんとした突き抜けた問いかけこそが、女性のみならず、男性からも高い支持を得る要因である。
突劇金魚は、今回、600名弱という過去のspace×dramaの中でも、最高に近い動員を記録した。これは、取りも直さず劇団側の努力の賜物という一面もあるが、space×dramaがこの10年積み上げてきた舞台芸術祭としての価値が評価された結果でもあろう。また、突劇金魚は、この12月に應典院からの推薦劇団として、芸術創造館での公演も決定し、各方面からの期待と注目が集まっている。
枠組みを一新したことで、若手の才能を見出し、育む場としての舞台芸術祭を如何に発展・進化させていくのかが問われる今年のspace×drama。突劇金魚の公演の成果は、その試金石となった。
小レポート
應典院コミュニティシネマシリーズvol.13「未来世紀ニシナリ」プレミア上映会
6月21日からの大阪劇場公開に先駆け、「未来世紀ニシナリ」のプレミア上映を行った今回のコミュニティシネマシリーズ。ロンドンへの取材を行うなど、そのメッセージ性に溢れた本編上映の後、釜ヶ崎で失業問題に取り組む「釜ヶ崎ふるさとの家」共同代表の本田哲郎神父から、実践者と宗教者の立場でお話をいただきました。また、その内容を深める場として、シンポジウムも併催。ゲストには、映画本編にも登場され、実際に西成で就労支援に取り組む佐々木敏明さん、福田久美子さん、そして本田神父。司会として本会事務局長の山口洋典が登し、それぞれの立場からの西成での取り組みを巡った議論が闘わされ、客席からも活発な意見が飛び出すなど、関心の高さを伺わせる密度の濃い
時間となりました。
小レポート
詩の学校お盆編 「それから」
8月4日、應典院の本寺である大蓮寺の本堂ならびに墓地にて、詩の学校お盆編「それから」が開催されました。2001年から應典院にて開催されている詩作のワークショップ「詩の学校」も、この時期だけは趣向を変えて、夕暮れの墓地で詩を作ります。そうした場に集った皆さんを、秋田光彦住職は、この春に亡くなった檀家さんに対して贈った、山尾三省の詩集で迎えました。あいにくの天気でしたが、詩作の時間には、なんとか雨も止みました。
「死と詩が同じ発音をもつのは、たんなる偶然ではないと思う」とは、「詩の学校」を主宰し、ファシリテーターを務める上田假奈代さんのことばです。今は傍にいない大切な人を、ことばの力を借りつつ思いを馳せる、そんな玄妙な時間が流れた一夜でした。
コラム「祀」
「皆んな味方」な南方呼吸するお寺・岡山版?
「葬式仏教の打破」「開かれたお寺の創造」に向けて、様々な展開をするお寺は應典院だけではない。この夏、休みをとって岡山のあるお寺で「復活する夏祭り」に参加した。
薬園山長泉寺は、岡山市の中心から2km、南方(みなみがた)という地域にある。開山は永世6年(1509年)6月で、平成21年に開山500年を迎える。このお寺は、京都の仁和寺の系列に連なる。薬師如来を奉り、今日まで篤い信仰に支えられてきた。
かつて長泉寺では年2回、お祭りが行われていた。しかし、現在は1つもなく寂しい限りとなっていた。「みんなが集まるお寺にしたい!」。現住職の宮本光研氏は開山500年を機に、地域の人々が集う寺へと復興させたいと考えた。そこで、地域で音楽を通じた福祉・教育・文化活動をされている、NPO法人「音楽の砦」理事長、松原徹氏に「マンダラ音頭~みンなみかた」と「奉讃 三宝賛歌」のCDと記念Tシャツ作成を依頼した。宮本光研氏は、仏教詩人としても世界的に活躍をされている。よって、作詞はご自身が手がけられた。
そして本年7月17日、寺で納涼祭を復活させた。この曲を使って、地元の小学生から20歳代の男女が「HIPHOP調の」創作盆踊りを2作(若者向と年配向?)を披露(いずれも少しテンポが速い?)。ヤングオールド合唱団が登場したり、地域に住む南米の方が、故郷の料理の模擬店を出店したり、地域の老若男女が寺に集った。祭りは大成功であった。地域の人々が寺に期待し、寺がその期待に応える気持ちの良い関係の成立。それは開かれたお寺の復活を意味する。さしずめ、呼吸する寺岡山版とでも言えよう。
ちなみに三重在住の私だが、毎年12月26日に應典院で開催されている「自分感謝祭」に参加している。1年を振り返り、次の1年を展望するよい機会だ。この場にも「祭」という文字が入っているのが興味深い。
以上、地域の人々が集う開かれた寺院の創造に向けての取り組みを取り上げた。長泉寺の、また「元祖」呼吸するお寺の應典院の今後に期待している。
岡山大学卒。放送大学大学院文化科学研究科修士課程政策経営プログラム(福祉政策)修了。應典院寺町倶楽部会員。市社会福祉協議会、専門学校専任教員、障害者施設・老人福祉施設職員、短大非常勤講師(兼務)等を経て、三重県伊賀市 社会福祉法人 青山福祉会 デイサービスセンターあおやま「百々」生活相談員(介護福祉士・介護支援専門員)。最近の主な研究は、「御詠歌・読経を用いた認知症高齢者への介護実践」(日本福祉文化学会『福祉文化研究』vol.17 2008年)。「老人デイサービス利用者への仏教介護的な相談・助言に関する試論」(『日本仏教社会福祉学会年報』第39号 2008年)。
Interview「力」
山口洋典さん (浄土宗・應典院主幹)
再建10周年を控えて着任した二代目主幹。
お寺で事業をプロデュースするにあたり、
自らを「僧侶B」と位置づけ、社会の問題解決に取り組む。
「秋田住職が市民僧と言っている概念を、私はあえて僧侶Bと言い換えました。半人前のB級僧侶という意味ではなく、葬儀などを行う人たちとは違う枠組みだということを訴えるためです。」
應典院主幹・山口洋典は、僧侶であることの自覚を語る。
應典院寺町倶楽部の事務局長を務めている山口は、浄土宗寺院・應典院の主幹でもある。主幹という肩書きは自治体では馴染みがあるが、お寺では希だ。いみじくも、東京・愛宕にある青松寺にて、
以前南直哉師が同じく主幹という肩書きを付していた。外に出て行く住職でもなく、内を固める執事でもない。カタカナ用語を用いてもよいなら、主幹とはさしずめ事業のプロデューサーと言える。
「僧侶として働くことに特に抵抗はありませんでした。ただ、秋田住職×應典院という条件でなかったら、僧侶にはなっていませんね。それは仏道に専心するために僧侶になったわけではないから
です。自分の理解者のもとで働きたいという思いを叶えるためには得度する必要があった、それだけです。」
應典院で働かないかと誘いを掛けたのは秋田光彦大蓮寺住職・應典院主幹(当時)であった。もっと悩むはずと思っていた秋田は、二つ返事で了承した山口に驚いたという。05年の夏のことであ
る。サラリーマンの家庭に育った山口は、大学関係に職を得て、社会人大学院生として應典院のある上町台地界隈のフィールドワークを通じて秋田との信頼関係を深めた。そして、06年度に應典院に着任し、時を同じくして突如として僧侶となった。
「僧侶Bという言葉は、環境問題の解決に必要な発想としてレスターブラウンという人が訴えた「プランB」が元ネタです。社会問題の解決に必要な発想は僧侶Bという具合で……」
山口の特徴は、秋田以上に言葉にこだわることだ。既に應典院で展開されている催しのいくつかで、山口がパソコンを駆使しつつ、瞬発力で文章を捻り出す風景を見た方も多いだろう。実は山口は
應典院に着任した同じ年、5年の任期で同志社大学の教員を兼職することとなった。実践の意味を言語化したいという欲求は、学究心からも駆られている。
「應典院はこの10年、秋田住職の人格・求心力・活動力・発信力を財産に、多方面から注目を集めてきました。その結果として、現在のリピーターやファンが存在し、かけがえのない財産となっています。だからこそ、今後は秋田住職とは違った「場としての應典院」の魅力を再提示していなければ、と思っています。」
應典院はお寺でありながら、多彩な事業を展開する。だからこそ事業プロデューサーが必要とされる。しかしお寺は他の文化施設などと異なり、予算の合理化が最重要とされることはない。その代わりに、それぞれの催しの意義が問われる。
「應典院はお寺としては風変わりな建築をしています。しかしれっきとしたお寺です。宗教空間にどのような時間を演出するのかがよいのか、常に事業プロデューサーには倫理観が問われていると思って、適度な緊張感を持ち続けていきたいですね。」
秋田住職と同じく、山口もまた、應典院が持つ場所の力に魅力を感じている。震災ボランティアという共通経験を持つ二人のリレーが、應典院という希有な力を放つ場を介してどのような輝きを放っていくことになるのか。目が離せない。
編集後記〈アトセツ〉
夏の應典院は演劇一色になる。まずは、恒例の舞台芸術祭「space×drama」だ。その後、蝉時雨のなか「大阪高校演劇祭﹇Highschool PlayFestival (HPF)﹈」で高校生たちの声が響き渡る。ゆえに、この時期の應典院を演劇の甲子園と呼ぶ人がいる。
そんな夏、先般、寺子屋トークにメインゲストとしてお招きした加藤種男さんの還暦の祝宴にお誘いを受けた。お盆前の東京とお盆明けの大阪のうち、大阪のみ参加させていただいた。ビール瓶を手にした乾杯の踊り、金粉ダンサーの祝いの踊り、全員での替え歌の合唱などの演出に、ご本人も「関西らしい」と笑みをこぼされていた。
会の終わりの加藤さんによるお礼のことばが印象的だった。播磨のご出身ゆえに、関西は故郷だと切り出し、東京での大学生活、町工場での仕事を経て、40歳を過ぎてからアサヒビールに入社したこと、などだ。そして、節目節目を通じて、多彩な仕組みをつくり、ネットワークが広がった、と。
人生が語られたことをライフヒストリーという。以前、ヒストリーという英単語は、his+storyに分解できるから、歴史とは彼の(his)物語(story)として第三者に語られてこそ成立する、という話を聞いた。例えば、この〈アトセツ〉も含めて、加藤さんが人生を語った場に居た私は、今後、その内容を他者に伝えていくこととなる。そうして、加藤さんが先達としてアートとNPOの関わり方を開拓してきた意味が見出され、歴史が刻まれていくのだろう。(編)
