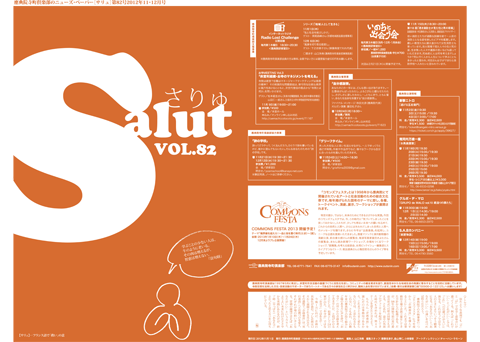
サリュ 第82号2012年11・12月号
目次
レポート「space×drama2012」
コラム 内山節さん(哲学者・立教大学教授/NPO法人・森づくりフォーラム代表)
インタビュー 河瀨直美さん(映画監督)
編集後記
巻頭言
自己に無益なことおよび不善のことは行いやすい。しかし有益なことおよび善はもっとも行いがたい
「ダンマパダ」
Report「競」
3年がかりの劇団にまつわる物語space×dramaにみるドラマ
15年続いてきたリレー
應典院では年間100程度の催しが展開されています。ただ、それらの中で、1997年の再建以来続いている事業はそれ程多くはありません。中でも、應典院寺町倶楽部による主催事業として取り組んでいるものとしては、寺子屋トークと舞台芸術祭「space × drama」だけです。そして、今年もまた、應典院にて7つの劇団による競演がなされました。
space × dramaの特徴は、既に「競演」と書いたとおり、参加劇団どうしが「優秀劇団」の座を競って7月から9月にかけて演劇公演を重ねていきます。ただ、当初は「舞台芸術祭」の名のとおりに、ダンスや音楽など、多様な表現形態による芸術祭でした。しかし、再建から5年を経た2003年に、設立5年以内の劇団による平日公演のみの演劇祭へとリニューアルされました。そして2009年には設立5年を越えた劇団による週末公演のエントリーも受け付け、現在の形に定まっています。
参加劇団の中から選ばれる「優秀劇団」が、翌年度の演劇祭にて、事務局(應典院寺町倶楽部)と劇場(應典院)との協働プロデュースによる公演を担い、年を越えて劇団間の思いがリレーされ、15年が経ちました。そもそも協働プロデュース公演とは、通常必要となる会場使用料の相当分を事務局側が負担することで、制作面の充実が図られるように、という企図があります。ですので、募集に対して応募する年、公演の年、そして協働の年と、3年にわたる関わりの中で、應典院が「ホームグランウンド」として愛着を深めてもらえれば、と願っています。もちろん、場への愛着だけでなく、劇団どうしが切磋琢磨しあっていく風土が生まれることも狙っており、そのため、演劇祭の半年前から「制作者会議」を重ねることにしています。
2つの冠に挟まれた夏
2012年度の space × drama は有史以来の特徴がありました。それは前年度に2劇団が優秀劇団として選出されたためです。具体的にはMayとMicro To Macroの2つが協働プロデュース公演を担うことで、開幕と閉幕を両劇団が飾り、制作者会議でも両劇団の経験知による貢献のもと、公演と演劇祭の活性化につながりました。特に、近現代における韓国人の生き方・働き方を常々取り上げてきたMayと、演劇とバンドの生演奏による音楽を効果的に織り交ぜた作品を重ねてきているMicro To Macroと、作風に特徴が際立つ劇団です。その結果か、それぞれの劇団の特色が一層際立つ年でした。
来場者数をはじめ、作家性、完成度、運営への貢献度、劇団や作品の社会性、今後の活動への期待度など、総合的な観点での審査の結果、来年度における協働プロデュースのパートナーには「劇団壱劇屋」が選出されました。緻密な展開と圧倒的な物量による舞台美術などは、審査員はもとより多くの鑑賞者の方々も感じ入ったところがあるのではないでしょうか。ただ、各劇団の創意工夫の中で、ともにょ企画、劇想からまわりえっちゃん、超人予備校、月曜劇団の皆さんは、それぞれに今の時代背景を作品に昇華させ、「自己と他者」の関係を問うていたように思います。また来年、どんな夏を迎えられるか、今から楽しみです。
小レポート
人と人以外とに寺が橋を架ける
去る10月12日、ものがたり観光行動学会との協力で、寺子屋トーク第65回「死者が大阪を賦活する時~宗教観光都市論」を開催いたしました。寺子屋トークで扱う話題は、應典院の再建時の理念に基づき、学びとケアとアートを基軸としながら、まちづくりやスピリチュアリティにも及んでいます。今回はその全てに橋を架け、糊付けして面となったテーマでした。
文字通り多面的な観点から議論が及ぶ話題を紐解くゲストが、思想家で武道家の内田樹さんと、思想家で人類学者の中沢新一さんでした。角川出版より共著で『日本の文脈』を上梓されたお二人の軽妙ながら奥深いトークに、日頃からの懇意な間柄と、博識な中の見識を、満場の参加者の皆さんと共に伺う機会となりました。「大阪のまちを賦活、すなわち活力を与えるのは、今の時代を生きる我々だけでなく、脈々と文化を創造・継承してきた死者と自然」とのご指摘、痛切に受け止めます。
小レポート
おもちゃの交換「かえっこ」
9月5日に美術家の藤浩志さんをお迎えして、使わなくなったおもちゃを交換するプロジェクト、「かえっこ」のしくみについてお話いただきました。藤さんが2000年に福岡で始められた「かえっこ」は、日本各地はもちろん海外でも開催され、教育、環境、地域活性化など幅広い分野で注目を集めています。
10月20日には、應典院を会場に、民族学博物館との共催で「かえっこ下寺町」が開催。当日は、かえるポイントとの交換に、にらめっこや肩たたきなどのゲームや遊びも用いられ、世代を超えた関係づくりの場となりました。
小レポート
異界との縁結び
9月には、<應典院協力>プログラムとして、超宗派の僧侶・在家の会である「スーパーサンガ」主催、「チベットを知り、祈ろう@大阪」が10日に開催され、約80人余りの方が、ラサ蜂起以来の犠牲者追悼法要、映画「チベットの少年オロ」上映と岩佐監督のトーク、ピースウォークに参加されました。
23日には、「数学の演奏会in Osaka」が行われ、新進気鋭の独立研究者、森田真生さんのお話を堪能しました。他団体と協力することで、新しい「縁」を結び、新たな関係が<つながる>ことを実感する一カ月となりました。
コラム「衆」
寺を取り戻す
大別すれば日本の寺には、三つの系統のものがつくられている。ひとつは天皇家や貴族、大名などがパトロンになるかたちで造られた寺で、もうひとつは宗門の本山として造られた寺であった。この本山としての寺は今日でいえば大学のような役割も果たしていて、各地から学僧たちが集まっていた。といっても数の上で圧倒的に多かったのは、地域の人たちが共有する、祈りの場として造られていった寺である。
私が暮らす群馬県の上野村には、観音堂や阿弥陀堂をもっている集落がいくつかある。それはたいてい十畳くらいの広さのお堂で、奥に観音様や阿弥陀様が安置されている。部屋の中央に囲炉裏が切られていて、ここは集落の人々の信仰の場であるとともに、ときに寄り合いの場であり、さらに旅人が夜露をしのぐ場所としても使われていた。こういうお堂が次第に整備されていって、いつしか僧侶が常駐するようになり、地域のお寺になっていったのが各地の民衆の寺である。そしてこの民衆の寺を勢力下に入れながら教線を延ばしていったのが教団であった。
いま仏教はどこに戻るべきなのかという問いを発したとき、最初に戻るべきところは仏教の原理でも、開祖の教えでもないと私は思っている。それは日本の風土のなかで民衆が仏教を取り込みながらつくりだした寺、地域の祈りや生活や苦しみや喜びをすべて飲み込んでいった日本の寺である。回復されなければいけないものは、仏教ではなく、寺なのである。
東日本大震災の後問われたことのひとつも、仏教は何ができるかではなく、寺は何ができるかだったのではないだろうか。それを「仏教は」と問うてしまうところに、仏教者の誠実なる傲慢があった。民衆が生きる場のなかにつくりだしていったものは、仏教ではなく寺だったのだということを、私たちはもう一度思い出してもいい。
1950年、東京生まれ。哲学者、立教大学教授。NPO法人・森づくりフォーラム代表理事など。群馬県の山村上野村と東京の二重生活をはじめて40年がたつ。最近の著書に『文明の災禍』、『共同体の基礎理論』、『ローカリズム原論』など。
近況・上野村で村人らしい暮らしをしているのが好きです。上野村は山岳信仰の強かった村でもあり、いまでも山のなかに500体を超える石仏が祀られています。専門は西洋哲学ですが、今日の現代哲学は東洋思想や日本思想などから学びながら研究がすすめられており、学生さんには日本思想が専門だと思われていたりすることもあります。
Interview「家」
河瀨直美さん(映画監督)
新作では最愛の養母宇乃さんの看取りを記録。
限りある時間の中での大切な人との日常、
その刹那を届ける作品「塵」のメッセージとは。
9月19日のコミュニティ・シネマ 19に新作「塵」を携えて登壇いただいた。昨年の「3.11 A Sense of Home films」に続く、河瀨監督登壇2回目の上映会。今作では、最愛の養母河瀨宇乃さん96歳の最期の姿にカメラは向けられた。
極限までのズームアップで露わとなる深いシワと虚ろなまなざし。パジャマ姿でベッドに横たわり、「プフゥ」と小さな吐息をたてる姿に眼差しが向けられる中、監督の子守唄が宇乃さんを包み込む。そこへ回想的に、カットインする若き日の姿。豆の木に水をやり、柔和な大和弁で「なおみちゃん、おばあちゃん好きぃ?」とチャーミングに問いかける宇乃さん。現実と記憶のループの中で、人間誰しもが避けて通れない、差し迫る「老い」が肉薄する。
幼くして両親が離婚した監督にとって、おばあちゃんであると同時におかあさんでもあった宇乃さん。同時に河瀨ファンにはお馴染みの「女優さん」でもあった。しかし、実はあまり自分自身のことを話せていなかったのだと監督はいう。「8ミリカメラのまなざしを通して目の前にいるおばあちゃんとの方が、よく話せてたんですね。でも何で撮ってんのやろう、こんなん超えてちゃんと『大好きやで』って言えばいいのに。」葛藤する客観性と衝動の対峙。それは初期の作品「かたつもり」の中で、宇乃さんを遠目に捉えていたカメラを突然置いて、急に駆け寄り、その頬を直接なでてしまうという突発的なシーンに体現されている。
自分を内職で育てあげてくれたおばあちゃん。最近ではその姿が、息子をもつ監督自身の心象心理と重なるようになってきた。「命の活力は自分自身のためだけにあるときと、家族なり血をわけた子に思いを託してるときがあって、託してる時の方が人間って力強いのかもしれない。」
今回、「塵」を撮るまでにも多くの葛藤があったという。「おばあちゃんの姿を撮影するということは、おばあちゃんの死を意味するという風にも思っていたので、ずっと撮りたくなくて。過ぎ行く時間の中でその人との時間は限りがあるって理解はできても心がついていかないんですね。でも無条件にこの人には幸せになってもらいたいと私は感じていて。その人が(施設に預けていて)家にいないという空虚感を記録しておきたいなと思ったんです。」
應典院での開催の折、あらためて「祈りを捧げる場」と「映画を観る空間」は似ていると感じたとのこと。「映画が個人にもたらすものは、記憶の回顧や亡くなったものとの出会いであって、それらは生きていくうえでの指針となります。」「過去は後悔とともに振り返れても、時間は戻せない。でも止められない時間を映画は記録し、記憶してくれているので、もう一度ここによみがえるんです。」
東日本大震災以降、「こんなに危うい奇跡的な瞬間を生きているのなら、どこで生きるのか誰と生きるのかをちゃんと考えて生きなきゃいけない。私は、家族となんでもない朝食を食べる日々を大切にしたいと思います」。
日本人の根源的な暮らしとそこに寄り添う生老病死を撮り続けてきた河瀬監督。最近畑づくりを始め、「次は米」と微笑んだ。日本の農業をカメラが追いかけていくようだ。次回作が待ち遠しい。
編集後記〈アトセツ〉
似たような表現でも「で」と「が」では全く意味合いが違ってくる。例えば「これでいい」と「これがいい」とでは、「これ」への位置づけが大いに異なる。これはモノではなく人のときによりいっそう顕著になる。「あなたでいい」と「あなたがいい」の違いを比べれば明らかだろう。
應典院での名物事業の一つ「コモンズフェスタ」に今年度から「企画委員」を導入することにした。これまでは事務局主導で企画立案をしてきた方針からの転換である。だが、98年の開始当初の実行委員会形式への原点回帰とも言える。ともあれ、途中の外部プロデューサーを起用してきた時代も含めれば、第4ステージを迎えたと言えよう。
もちろん「企画委員」を選んだのは事務局であるから、これまでと大きく変わらないのでは、と思われるかもしれない。ともあれ、この数年来の應典院での取り組みにご縁のある方に声を掛け、「お寺で」の何らかの企画を考えてみませんか、と投げかけることにした。結果として24の案が出た。「お寺が」ではなく「お寺で」ではあるが…。
今後1月に向け、企画の具体化が進む。プレ企画は12月から展開される見込みだ。その過程で「企画委員」は「実行委員」へと位置づけを変え、それぞれが場の担い手となる。冒頭の論理で言えば「あなたがいい」という方々と、よりよい未来に向けたささやかな実践にあたるのだが、終了時(やっぱり)「あなたで」よかったと思える日を心待ちにしている。 (編)
