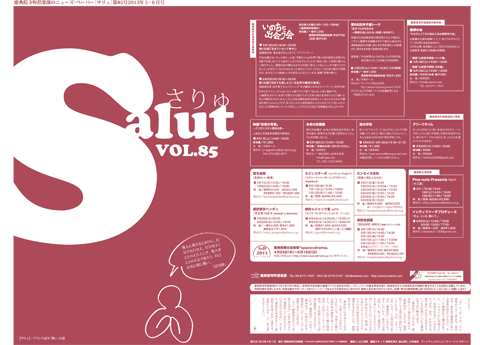
サリュ 第85号2013年5・6月号
目次
レポート「寺業再興」
コラム 根木山恒平さん(特定非営利活動法人碧いびわ湖・常務理事)
インタビュー 川浪剛さん(真宗大谷派僧侶)
編集後記
巻頭言
他人に教えるとおりに、 自分でも行なえ。 自分をよくととのえた人こそ、 他人をととのえるであろう。 自己は実に制し難い。
「法句経」
Report「聖」
「寺業再興」をテーマに、寺院の豊かな潜在力を見る。
「持続可能」な寺院運営
お寺のサバイバル、などという言葉をよく耳にするようになりました。伝統的な家族制度、地域共同体を基盤に運営されてきた寺院が、いま大きな危機に直面しています。少子高齢化、葬送の多様化、さらにメディアによる仏教バッシングも相次ぎ、寺院を取りまく環境は劇的に変化しているといえます。モデルなき時代において、いかにお寺を「持続可能」としていくのか、これまでになかった観点で、寺院の将来像を探るトークセッション「寺業再興~地域のいのちを支える『ソーシャルビジネス入門』」が3月1日、應典院で開催されました。
コミュニティと寺院
パネリストは浄土真宗本願寺派僧侶の松本紹圭さん、龍谷大学政策学部准教授の深尾晶峰さん、野村證券(株)金融公共公益法人部課長の塚嵜智志さん、そして当山の秋田光彦代表の4人。会場は全国から集まった100人以上の僧侶・市民の熱気に包まれました。
塚嵜さんは、人口動態から寺院を取り巻く環境について、「今後都市部は超高齢化に直面し、寺檀関係は劇的に変化する。住職は法人を運営するという意識を強く持ってほしい」と指摘、また秋田代表は「寺業」という言葉のイメージを、「官だけが公共ではない。寺業の原点は官が担う以前に寺院がになった学び(教育)、福祉(医療)、楽しみ(文化)にある。生老病死、命の全てのステージを支える役割が求められている」と語りました。
ウェブサイト・彼岸寺を設立し、「未来の住職塾」を開く松本氏は「僧侶は寺院の高いポテンシャルに気づいていない。現状を把握し、宗教によって地域や人をどのように変革するか、しっかりとした目的意識が必要」と意識改革を訴えました。
きょうとNPOセンター創立から現在まで運営の中心に関わり、現在は大学で教鞭も取る深尾さんは、寺院と地域社会との協働の視点から「絶えずイノベーションを起こしていたからこそ、今のお寺が存在している。寺院は地域コミュニティーの核として、民の力を結集する役割を果たしてほしい」と期待を寄せました。
「聖性」を問い直す
討議では松本さんの「事業を寺業となすには、『聖性』が必要」との問題提起を受けて、聖性についての議論が相次ぎました。聖性を松本さんは「目的あるいは使命感」、深尾さんは「異端やマイノリティーとどう向き合い包摂していくか。このあたりに聖性があるのでは」と表現、秋田代表は「弱者と共に生きることによってこぼれ落ちる輝きの中に聖性はある。聖性は寺業の営みからうまれるものであって、つくるものである」と締めくくりました。
教義でも宗教性でもない、曖昧ながら、そこに仏教と社会をつなぐ余白があるはずです。形態は宗教法人でもNPOでも企業でもいい。要は、何を聖性として作り出すかではないでしょうか。
お寺と経営、とりわけお金にまつわる話はタブーとされてきた中で、この主題を立てたことは実験的でもありましたが、どのスピーカーもモラルを維持しながら、実践的な観点からお寺という現場をとらえていたことが印象的でした。最後の30分には、フロアから前向きな質問や感想が相次ぎ、この日の議論への共感がうかがえました。
小レポート
1.17から3.11へ
供養・浄梵 コモンズフェスタ2013の一つの企画案として、「彼岸」にいる「あえなくなった、あの人へ」への手紙を募集し、二回にわたって應典院の一階ロビーに展示をいたしました。逢えなくなった人への思い、自分への誓い、そして感謝の気持ち、これらの大切な思いの詰まった手紙は、3月11日、本堂ホールの闇の中で満月動物園の俳優さんたちにより本堂で朗読された後、東日本大震災発生時刻には参加者すべてで梵鐘の時が持たれました。
そして、福島で被災された方のお手紙は大蓮寺にて福島県の形にかたどられたロープを前に、彗星マジックの俳優さんたちにより表現の一時が持たれました。両劇団の表現の素晴らしさには多くの方たちが胸を打たれ、参加された学生さんの「簡単な言葉に表せません」という感想に表されていたかと思います。最後には参加者で朗読された手紙を浄梵して、震災で亡くなられた方への深い祈りのときとなりました。
小レポート
本堂で「縁」が紡がれた一日
去る3月3日、應典院にて「びわ創・大縁日」なる催しが実施されました。「びわ創」とは「びわ湖・流域暮らしとなりわい創造会議」の略称で、1972年から97年に展開された国の総合開発の略称「琵琶総」への「あてこすり」でもあります。要は、改めて現代を生きる知恵を探る機会を探ろうという問題提起です。
滋賀県の琵琶湖は、法律上「川」とされています。若狭湾と大阪湾、それぞれの海へと注ぐ水と共に生きてきた各地の取り組みを紐解き、紡いできた縁を、多様な担い手と多彩な催しによって紡いだ一日でした。
小レポート
春に開催される演劇祭の交流会
夏から春へと開催が変更になった應典院舞台芸術祭space×drama2013。昨年の12月から制作者会議を重ね、3月25日に演劇祭参加劇団による交流会が気づきの広場にて開催されました。
今年の参加劇団は7劇団、協働プロデュース公演は、昨年選出された劇団壱劇屋。そして特別招致枠としてミジンコターボの参加も決定。交流会では、ロビーの装飾や劇団への応援メッセージボードを準備し、新たな試みとしてTwitterでライブ映像が発信出来るTwitCastigで参加劇団を紹介しました。初めての春開催となる應典院舞台芸術祭は6月16日まで開催しております。
コラム「芽」
滋賀と大阪のつながり
「いのちのつながり、門前のにぎわい、飛び地の入会地」を合い言葉に應典院にて開催させていただいた『大縁日』。朝イチ、本堂では京都からダンサーの森裕子さんに来てもらいワークショップが始まっていた。初めて出会う老若男女が輪になって隣の他人の足をもみほぐすという軽妙な光景を傍らに、場内には子どもがたくさんである。しばらくすると、かあちゃんのひとりがあわてて飛び出していった。勢い余った男の子が、ガラス戸に激突してタンコブをつくったとのこと。幸いにも應典院の山口さんに買ってきていただいた氷で冷やして事なきを得た。
昼前には、大蓮寺の山門を入ったところで、もちつきがはじまった。琵琶湖の西側に位置する南比良からやってきた若頭が、声を張り上げるのにあわせて場に活気がでた。音頭の合の手は、信楽からきたかあちゃんたち、もちの手返しはベテランかあちゃん。自転車でやってくる子連れ家族も多く、子どもやとうちゃんたちが代わる代わる杵をふり上げた。おでこに白いガーゼをつけて、もちをつく男の子の姿もあった。
終盤、本堂をぐるっと囲んだリレートークでは、若者の言葉が印象に残った。東北・関東からの親子を京都に迎える保養プログラムに取り組む20代。ちょうど3・11直後に卒業し1年間企業勤めをしていたが、「2ヶ月間休みなし」といった働き方に疑問をもち退職したという。いわく「働き方の枠組みを替えていかないと」。この1年間、滋賀から大縁日に参加した仲間との議論でも「働く場を地域の中にどうつくっていけるか?」は主要テーマであった。
滋賀から京都、大阪、兵庫へ。水の流れでつながる私たちは、都市でも田舎でも大きくはひとつの社会構造の中に暮らしている。大縁日でうまれたつながりの芽を育みながら、今後も、入り会える場(機会)をつくっていきたい。
特定非営利活動法人碧いびわ湖・常務理事。東京出身。舞台芸術企画制作業を経て、9年前に縁あって滋賀に移住。現在は、子育てのかたわら、碧いびわ湖で働いている。1978年にはじまった「琵琶湖のせっけん運動」を、<いのちを守る/住民自治による/暮らしを変える運動>として、いまの時代にどう継承できるのか、仲間とともに取り組む。今回は、上田洋平(滋賀県立大学)などとともに、滋賀から京阪神にかけてつながりをさぐる中で、應典院に出会い大縁日を開催するに至った。インターローカルなネットワーキングをとおして、地域を超えてあらたな規範が生まれることを期待している。
Interview「探」
川浪剛さん(真宗大谷派僧侶)
川浪剛さん(真宗大谷派僧侶)
仏教医学を読み解く「楊柳の会」を企画。
健やかであるとはどういうことか。
仏教が育んできた智慧の「蔵」を探訪する。
大阪市西成区の釜ヶ崎で、日雇い労働者やホームレスに寄り添い、葬送にも立ち会う活動を続けてきた。2010年には「社会的困窮者」の葬送に関わる「支縁のまちサンガ大阪」の発足会を應典院にて開催。さらに、宗教者が関わるたすけあいの場「支縁のまちネットワーク」を2011年を始めた。なぜ僧侶なのか、なぜ釜ヶ崎なのか。そこには育った環境や複雑なアイデンティティがあったという。
「もともと寺の子ではなかったのですが、育った家の前に真言宗のお寺があったので、まさに『門前の小僧』。仏教には幼い頃から親しみがありました。それと同時に、仏教専門の出版社に就職したいという思いが漠然とあって仏教を本格的に学ぶことにしたんです。」
平成元年に得度の後、ほどなくして瀬戸内海のとある島の寺に所属した。しかしそこで出会った地元のおばあちゃんから向けられたのは「足が痛い。年金が減る。何かないのあんたら。」という具体的な悩みだった。
「仏教者として、医療や福祉という、より実践的な勉強をしないといけないということを切実に感じた瞬間でした。」その後、社会福祉専門学校の門をくぐることに。その時胸に秘めていたのは「仏陀を背負いて街頭へ」という一節だったという。
さらに、人生を決定づけるある衝撃的な存在に出会う。「介護ヘルパーの免許を取りに行ったとき、たまたま講師をしていたナースの方が『病院の中にいるだけがナースじゃないのよ。歌って踊って笑いのとれるナースを育てたい』とおっしゃったんです。当時、まだ訪問介護や在宅ケアなど主流ではなかった時代、この言葉には大きな影響を受けました。今『単独僧』と呼んでもらうことがありますが、その原点はこの時にイメージできていましたね。」
釜ヶ崎に僧侶として関わり始めたのは2000年頃。「もともと父が釜ヶ崎の日雇い労働者だったこともあって、その世界から逃げたいと思って生きてきました。でも街中のホームレスが気になったり、専門学校の友人が路上生活者のための炊き出しをやっていたりという幾つかのきっかけがあって、いつの間にか『釜ヶ崎』という街に戻っていったんです。ブーメランみたいに。」
この4月からは應典院にて、新企画「からだとこころに染み入る仏教医学の会(楊柳の会)」を発足させる。「病気を治してくださる『楊柳観音』さんからお名前を戴きました。仏教寺院にはすばらしい智慧が眠っています。西洋からの借り物ではない、土着のものから支援や治療の原理がないかと考えたのが企画の始まりです。」
「楊柳の会」は、全シリーズ4年の應典院史上でも稀な長期構想型プロジェクトだ。まず一年目のテーマは「食」から入る。「中国の道教は不老不死を目指す宗教の一つですが、それをヒントに4つのテーマ『食』『薬』『呼吸法』『看護』を掲げました。人が健やかであるとはどういうことか。みんなで、お寺の経蔵から宝物を探してくるような学びの場にしたいですね。」実は、先頭に立つよりも裏方に徹する方が好きだという。「私は蔵の鍵を持っている人。ほこりをはらってみんなで奥へと進んでいくイメージ。『蔵から入る仏教入門』ですね」と期待を膨らませる。
編集後記〈アトセツ〉
「で」と「が」では、文の意味が大きく異なる。唐突だが、新年度の應典院における事業計画を立てる中で、そうした議論を行う機会があった。1997年に再建された「呼吸するお寺」で何をなすべきか。毎年、それまでを振り返り、それからを考える、いつもの時期のいつもの議論の席で出た観点である。
「應典院で」と言えば、應典院という場が取り扱われ、「應典院が」と言えば、應典院という主体が取り扱われることになる。今回、スタッフのあいだで、この間の取り組みが「應典院が」に囚われすぎていないかと、意見の交換が続いた。転じて「應典院で」を大事にしてくださる方々の思いに応えられているかの内省も重ねられた。無論、昨年度のコモンズフェスタが、久々の実行委員形式で企画運営がなされたことも、無関係ではない。
應典院には若者たちを中心に、年間3万人が訪れる、とされている。本堂での舞台公演が40本換算で約1万2千人、それに伴う稽古場使用が1回30人として1万人相当、その他催しで8千人程度の積算だ。言うまでもなく、これは「應典院が」ではなく「應典院で」の視点である。應典院は「が」より「で」が重要であることの証左だ。
よって、應典院がまちと「呼吸するお寺」であり続けるには、應典院「で」何かする方々の存在が欠かせない。そもそも「應典院が呼吸する」と「應典院が呼吸させる」は異なる。再建から16年。「で」を大事する年としたい。(編)
