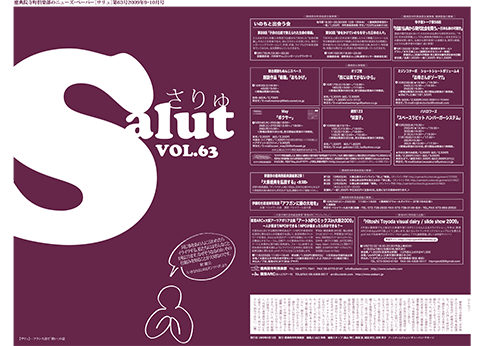
サリュ 第63号2009年9・10月号
目次
レポート「住み開きアートプロジェクト」
コラム 空庭さん(山内美陽子)
インタビュー 一瀬尚代さん(baghdad cafe’)
編集後記
巻頭言
同じ事をあの人に言われたら
イライラする、私たちにはそんなこと
が起こります。なぜそうなるのか。その
仕組みを知ることが大切なのです。
釈 徹宗
「いきなりはじめるダンマパダ」より
Report「集」
自分だけの場所を、
みんなのための場所へ。
5カ所を尋ねて、実験3回。
前号の告知欄でもお示ししたとおり、7月18日から8月30日にかけて、築港ARCプロジェクトの総力を結集し「住み開きアートプロジェクト」を展開いたしました。今回、自宅や個人事務所等、プライベートな空間の一部に、本来の用途以外のアイデアを盛り込み、多様な人々が集うパブリックな空間に変える活動や拠点に着目しました。まず、地域のこどもたちなどのために自宅を博物館に改装した元・大学教員である沢勳さんの「沢洞窟ハウス」、大手古本屋チェーンでの勤務の後に人と古本のより良い出会いの場を自宅にと考えた市川ヨウヘイさんの古本屋「メガネヤ」、本号のコラムを執筆いただいた造園プランナーの山内美陽子さんによる「谷町空庭」、此花区梅香エリアで地元不動産とタッグを組んで空物件の活用に取り組んでいるNPO「プラス・アーツ」の高林洋臣さんによるまちあるき、空倉庫を自宅兼ライブスペースとして開放している米子匡司さんの安治川倉庫「FLOAT」、この5カ所を訪れました。
それぞれに、場所を開いている皆さんの個性や姿勢を確認できたフィールドワークで、「住んでいるところを開いているか / 開いているところに住んでいるか」という視点を発見しました。プログラムが進むうちに、時間的・空間的にどれだけ開くのか、という点にも興味が向かいました。
併せて、美術、音楽、映像に関わる若手アーティスト3名によるプチ「住み開き」への挑戦として、一時的に自宅を表現の場所として開放いただきました。宮本博史さんは親子3世代が住み続けて来た阿倍野のマンションにて、家族にまつわる記録物(アルバム、日記、手紙、家計簿、8mmフィルム、等)を展示し、参加者と宮本さん並びにご両親が毎日、自分の記憶と重ね合わつつ、会話がなされました。また音楽家のakamar22!さんには、自宅近くを自らの「庭」と見立てて案内を頂き、四天王寺の境内等では即興での弾き語りが披露。公と私の領域が反転する場面に向き合いました。映画監督の平岡香純さんは、大正区の自宅にて、音楽家のプリミ恥部さんとの共作音楽映画「プリミ恥部な世界」を生演奏で上映。「住み開き」という条件によって表現が拡張され、鑑賞する参加者を映画の世界にに引きずり込んでいきました。
概念を紐解くキーワードとして
プログラムの中盤と終盤には、「住み開き」を始める方々を増やそうと、実践家・自治体職員・研究者らによるシンポジウムを2回開催いたしました。8月2日の第一弾では、既に当会ではお馴染みの花村周寛さんと小山田徹さん、そして過去に梅田で自宅カフェ「太陽2」を運営されていた社会学者の渡邊太さんが活動を報告し、参加者と共に意見交換が行われました。とりわけ「住み開き」に対するハードルを如何に下げていくかが論点となりました。
最終日に行われた第二弾では、会場となった住居用マンションの一室「208南森町」の共同運営者である岩淵拓郎さんが、ホームパーティから始める住み開きの方法を話題提供されました。続いて、本プログラムと同じく、アサヒ・アートフェスティバルに参加する青森県八戸市での商店街空店舗活用プロジェクトを、八戸市役所の今川和佳子さんが報告。こうして、各地での各種の取り組みを取り上げてきたのですが、シンポジウムの最後には、参加者からの「住み開きという言葉は都会的で、元来コミュニティが強固な郡部等では、概念先行で馴染まないのでは!?」との指摘により、新語の導入が孕む危険性を見つめるきっかけを得ました。勿論、既に家とまちとの良好な結びつきがある人々には、新語を実践に当てはめる必要はないのでしょうが、生活文化の中に潜む創造性に着目していく上では意味のある概念を提示できたと捉えています。
小レポート
「助け合う」経験を積むお寺の夏
サポーターと共につくる應典院でのHPF大阪高校演劇祭(HPF:High school play Festival)の参加22校のうち、7月18日から27日にかけて10校が應典院にて公演しました。元気よく「おはようございます」と笑顔を浮かべて入ってくる生徒、緊張がみなぎっている生徒、また今年の3月に應典院で開催された「space×wave」に参加した生徒など、多彩な顔を毎日見ていました。今年の統一テーマは「助け合い」だったとのこと。space×waveの講師も勤めたサポートスタッフたちは、その際の経験を活かし、どうすれば助け合いの輪が広がるかを心がけたようです。そして、生徒たちが自分たちで答えを出すことができるよう、答えを教えるのではなくヒントを出す立場として、高校生たちの舞台作りを丁寧に支えていました。
今年は、自分達で手掛けた脚本が多く、高校生の等身大の作品が上演されている事もあり、自分たちの考え、表現、使う言葉を着飾らず、各校がありのままの思いを客席にぶつけていました。限られた時間中での演劇活動であるものの、高校生たちは公演を通じて自分自身に向き合います。輝きに満ちた高校生たちにスタッフ陣も心が癒されたようです。
印象的だったのは、3年生たちが帰り際にスタッフたちにお礼を言っている姿でした。HPFの卒業生たちが應典院で公演をする事も徐々に増えて来ています。HPFの歴史と應典院の歴史が重なってきています。来夏もまた、多くの高校生が應典院で可能性や独創性があふれる作品を見せて欲しいと期待をしています。
小レポート
お盆、「言偏」に「寺」と書く「詩」で死者を想う
去る8月6日、好例の「詩の学校・お盆特別編」と應典院寺町倶楽部会員交流会「ビールでおBON」を併催いたしました。天気予報は生憎の雨模様でしたが、大蓮寺墓地での詩作と発表の時間は、なんとか傘をささずに行うことができました。今年は16名にご参加をいただきました。まずは慣例なりました、大蓮寺本堂での簡単な法要に任意でご参加いただき、続いて秋田光彦大蓮寺住職から「そもそもお盆とは」についての法話をいただきました。
そして、、大阪出身で東京の大学に行っている学生さんなど、普段は詩作をしていない方から、「詩の学校」の常連の皆さん、そして應典院寺町倶楽部の事務局長などが、死者を悼む詩をつくり、皆さんの前で発表。講師の上田假奈代さんは、曇り空ゆえ、まちの灯りが映っている空など、その場の雰囲気も見事に取り込んだ詩を披露されました。その後は参加者全員で研修室Bにて交流の場を楽しみました。
小レポート
特設ブログを通じ「人生の完成期」を考える
毎夏好例の應典院での「エンディングセミナー」が、7月18日の土曜日から3週連続で開催されました。各回とも多くの参加者を得て、好評のうちに終えることができました。
1年のブランクは、さしずめ充電期間と位置づけられ、少し枠組みも進化いたしました。とりわけ、終了後も更新が続けられているブログ「みとりびとは、行く」は、開催前には講師との事前打ち合わせの内容を、開催中は関連情報を、開催後は各回のレポートを、という具合に、セミナーを単発の学びの場に止めないための仕掛けとして位置づけました。
ブログの運用も含め、應典院寺町倶楽部の協力で進められた本セミナーの内容を、ぜひ特設ブログ「http://mitoribito.blogspot.com」にてご覧くださいませ。こうして、築港ARCにて展開してきた積極的な情報収集・発信・交流の仕掛けを、順次各種事業へと反映して参ります。
コラム「開」
住み開くということ。
誰かの家のような公園のような、場所
7月末の日曜日に行った「住み開き」イベントでは、参加者と空庭で日々していることの延長―日よけづくりや空畑(そらはた)の草むしりなどを行いました。イベントという名のもとでこんなことをしていいのかと自問自答しながらも、わきあいあいと不思議な感じでイベントはすすみました。第二部では空畑で取れた野菜料理を食べながら、それぞれ普段していることや意識していることを言葉にしました。
他の住み開いている方に比べ規模が大きかったようですが、谷町空庭は、週に2回は誰でも気軽に来れるカフェ、週末や夜には貸しスペース。そのため、たくさん人がやってくることに抵抗はありませんでした。
谷町空庭(はじめは“空庭カフェ”)をはじめたのは7年前。緑や花が人々にとってもっと身近な存在として感じられるような仕事がしたいと、友人と自宅(ビル)の屋上を手作りでとんかんしはじめたのがきっかけです。屋上の整備が完成する直前に、いろんな人がふらりと来て、空が近くて緑と親しめゆっくりできる場所があってもいいじゃないと考え、お茶の飲めるゆるいカフェとして“開く”ことをはじめました。
はじめは屋上だけを開いていたものの、階下の部屋が空いたことで、そちらも手作りで改装し、カフェだけでなく、もっとゆっくり空庭を楽しめるようにと貸しスペースにしています。使う人たち自身で空間をマネジメントできるようなイメージです。オーナーである私や家族(開くには家族の協力が必要です)も、“空庭の管理人”のような感覚でいます。
自宅の一部に人がしょっちゅう来るので、かっこつけてはいられません。掃除が行き届かなくても、花が咲いていなくても、頭ボサボサでも、それがこちらの精一杯。がんばってもボロがでるので、無理をするのはやめました。楽観的な性格でないと続かないのです。
場所を開く上では多分にそのオーナーの性格が出ます。参加された皆さんが空庭を住み開きの例にして頂けるなら、人を迎えることに抵抗感をなくすことが住み開きのヒントとなる、と胸に残ったでしょう。
空庭(山内 美陽子)
大阪市中央区、谷町四丁目在住。自宅の古いビルの屋上とその階下を「谷町空庭」(たにまちそらにわ)というスロースペース(カフェ&フリースペース)として開放。
http://www.soraniwa.net
本業は「都会で里山」をコンセプトに、まちなかでの土・緑・農のある暮らしを提案する造園プランナー。また、一昨年より、ベランダや屋上、周辺農地をみんなで耕すプチ自給農プロジェクト「空畑(そらはた)クラブ」を展開中。
http://www.soraniwa.net/sorahata/
Interview「琢」
一瀬 尚代さん (baghdad café代表)
劇団どうしが試行錯誤し、切磋琢磨して、演劇祭をつくる。
多数の選択肢の中から、どうすれば盛り上がるかを選ぶ、
その経験を、来年度に協働する機会に活かしていきたい。
今年の舞台芸術祭は、史上最多の8劇団による演劇祭であった。さしずめ若手劇団と旗揚げ5年以上の劇団による混合リレーとなり、アンカーを昨年の優秀劇団「特攻舞台Baku|団」が務めた。8月29日に開催されたクロージングトーク及び公式ブログでも発表されたとおり、第一走者としてバトンをつないだbaghdad caféが優秀劇団に選ばれた。
「クロージングトークでの優秀劇団発表の瞬間は本当にびっくりしました。しかし、同時にお芝居をやってきてよかったという喜びと、これからも頑張ろうという気力が湧いてきました。今後の劇団活動の自信に繋がります。本当にありがとうございます。」
劇団の看板女優であり代表でもある一瀬尚代さんは、発表から数時間後のインタビューにて、そう語った。今回のbaghdad caféの作品は、ノスタルジックで少し切なく優しいファンタジーであった。演劇祭のみならず、何事もトップバッターは緊張する。しかし、堂々と劇団のカラーを表現したことで、後続の劇団にも良い緊張感が生まれたように思う。コメディを得意とする劇団ガバメンツは、タクシーの中で繰り広げられる会話劇を展開した。今回が旗揚げ公演の劇凸アイデンティティは、横に長い舞台で、「欲」をテーマとした作品を創りあげた。特別招致枠の満月動物園は、性格の異なる2作品を上演。折り返し地点を過ぎ、應典院の高さと広さを活かした妄想プロデュースの作品は、逆に先輩劇団を圧倒させた部分もある。そして、実話であり秀作の「エレファントマン」を題材したカン劇cockpit、現代の若者を等身大で演じたZsystem、今回で劇団の歴史を閉じることと発達障害・精神障害の介護の問題を取り扱った特攻舞台Baku|団、それぞれに味のある群像劇であった。
「本当に勉強不足で、いつも手探りの状態で劇を作ってきたため、今回演劇祭に参加させていただき、とても勉強になりました。特に毎月の制作者会議では、劇団同士で触れ合いがあり、他劇団の代表や制作の方との議論を通じて経験の交流が出来ました。また、WEBやチラシと言った広報面の細かな所まで、互いに意見を出し合ったので、他人任せではなく「自分たちで」という意識が持て、やりがいがあったように感じます。」
最早伝統になっている月1回の制作者会議は、2月から半年かけて、参加者たちが自分たちの演劇祭に仕上げていく貴重な機会だ。伝統を守るだけでなく、例えば昨年から活用されているブログの運用方法などは、参加劇団の意向に委ねられる。
「劇評ブログでは多様な視点から意見が聞け、自分たちの作品を見つめ直す上で、とても参考になりました。一方で、私たちも他の劇団のお芝居を観させて頂き、リレーブログなどでも触れていくことで、ジャンルも年齢層も幅広い各劇団の特徴に興味や関心を深く向けていくことができましたね。」
審査対象となった6劇団は全て、應典院の演劇祭には初参加であった。会議のみならず劇団のリレーブログ等を通じ、劇団どうしが濃密な交流が図ることで、互いに切磋琢磨していた。次年度は優秀劇団の看板を掲げて演劇祭に望む。抱負を尋ねた。
「来年の協働プロデュース公演に向けて、劇団としての課題がたくさんあります。それらをクリアして、しっかり成長して帰ってきたいと思います。そして、今年のように各劇団が互いに刺激しあって高め合うという、理想的な関係が来年も築かれることを楽しみにしています。」
編集後記〈アトセツ〉
應典院では演劇や「住み開き」の2009年の夏、世は衆院選の結果を受け政権交代となった。「この国」と「我が国」と、論評する際の言葉の使い方に、変化への向き合い方が顕れていると思う。投票率も高かった。が、雑感ながら、今回の結果を見て、小選挙区比例代表並立制と、選挙権と被選挙権を得る年齢が違うことに対し、今後精密な検討がなされて欲しいと感じた。
ただ、お盆の頃の報道が、ほぼ芸能人の薬物使用問題で染まったことには閉口した。テレビやインターネットから離れた時には、伝えたいことと伝えるべきことに開きがある、などと懸念を抱く。しかし、いざスイッチを入れると、嫌でも情報が飛び込んでくるのだ。一部では、政治による報道へのコントロールが働いたとの見方もあるが、情報から価値を選び抜くリテラシーが益々問われていると実感した。
思えば米国でオバマ新政権が発足したのも今年だ。その際、単語のChange」が有名だが、その前にあった「We can」という語に関心を向けている。このフレーズを支持した「我々」とは誰か、そして「何を」変えるのか。そんな風に考えてみると、選ぶ側と選ばれる側のあいだに一線を引くことは妥当ではないのかもしれない。
誰かと共に何かをすることが重要となることは論を待たない。自治体や企業でも「協働」や「連携」はスローガンに留まるものではなくなってきた。とはいえ、他の組織との関係づくりだけではなく、内部の連帯感や団結心も必要だ。それこそ、我々のNPOも、例外ではない。 (編)
