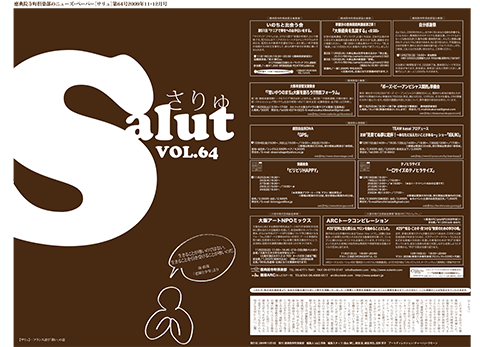
サリュ 第64号2009年11・12月号
目次
レポート「第56回寺子屋トーク」
コラム 伊藤伸二さん(日本吃音臨床研究会・会長)
インタビュー 服部隆志さん(自敬寺住職・アーユス関西事務局長)
編集後記
巻頭言
生きることが尊いのではない。
生きることを引き受けることが尊いのだ。
南 直哉
「老師と少年」より
Report「教」
お寺が時間の肌感覚を取り戻し、
社会に関わり、関わられるには…
碩学と新鋭の初顔合わせ
9月13日、應典院では久しぶりとなる「寺子屋トーク」が開催されました。年度当初には事業計画に含んでいませんでしたが、皆様からの要望等をもとに、仏典講座第二弾のプレ事業との位置づけを行い、企画いたしました。56回目を数える今回は「仏典から現代社会を問う〜日本仏教の可能性」と題し、今年度より東京大学より国際日本文化研究センター(京都市西京区)に移られた末木文美士先生と、應典院では最早お馴染みの釈徹宗先生による対論を行っていただきました。書店での広報協力や新聞報道を頂いたことで、開催1週間前より多数の予約を頂戴し、両者初対談の場となった本堂ホールは、約 140人という超満員になりました。
当日は第一部が末木先生の講演、第二部が対談と、二部構成を取りました。歴史を紐解きながら現代社会の問題を問いかけた第一部では、著作では伺い知ることのできない末木先生の人柄がにじみ出るお話となりました。とりわけ、目には見えないものを大切にするとはどういうことか、経典をいかに読むのか、これらの事柄について丁寧に言葉を選んで話される姿に、参加者の方々も意外な印象を受けられたようです。1時間の講演は、「擁護者のように思われているが、最早葬式仏教は期限切れだと思う」との指摘に続き、改めて死者との関係を取り結ぶ役割を担ってきた仏教を哲学的に考えてみてはどうか、との問題提起で締めくくられました。
伝統を守り文化を創造する
第二部は、進行役も兼ねていただいた釈先生のリードによって、初顔合わせながら軽妙に対談が進められていきました。冒頭、釈先生から、僧侶とは異物として場をゆらす「トリックスター」であると認識しているが、僧侶にこそ、その論が受け入れられない実感あると、論点が提示されました。そして末木先生に、中世や近世の時代と比べてみると、時間の身体感覚、肌感覚が変わってきた現代社会において、日本の仏教や寺院はどうあればよいのかが問いかけられました。すると末木先生は、江戸時代の寺檀制度によって全国の津々浦々にあったお寺が、この変化の時代においてワンパターンに伝統仏教を守ろうとしない方がいい、と返答されました。ただし、「社会参加仏教」という表現で外部の応援団がお寺の可能性を見出していくことには否定的だ、という見方が示されました。なぜなら、本来仏教では菩薩行の段階を経て仏陀になるとされているはずなのに、日本の仏教では修行を重ねていくという前提を飛び越えて、「死んだら仏になる」という独特な物語があるためだと仰います。ゆえに、タイの開発僧など上座部仏教を参考にして考えることも大切だが、一方で日本人の精神性を大事にしていってはどうか、と返答がなされました。
こうして、それぞれの意見が重ねられた対論の最後は、まず釈先生から、社会とお寺の関わりについて、社会参加仏教の視点から積極的に関係性を紡いでいくという「縁起の実践」と、維摩経における「関係性に捕らわれない」立場の両面が求められるとの整理がなされました。そして、誰でも参加して運営できるとした應典院は、全寺院に普遍的な在り方ではないかもしれないが、日本のお寺の機能や役割を見出す上での目安やモデルの1つになるとの評価を頂きました。一方、末木先生には、会場から頂いた3名の質問に答えるかたちで、改めてお寺が継承してきた儀礼の文化を大切にしていけば日本人の〈いのち〉の捉え方が変わる、と括られました。玄妙な議論の場の内容は、1月に小冊子「サリュ・スピリチュアル」にまとめるべく、準備中です。
小レポート
月例トークサロン、ラストスパート中。
「旅行者のために、わたしたちが出来ることを仕 事にする」
サポーターと共につくる應典院でのHPF大阪高校演劇祭(HPF:High school play Festival)の参加22校のうち、7月18日から27日にかけて10校が應典院にて公演しました。元気よく「おはようございます」と笑顔を浮かべて入ってくる生徒、緊張がみなぎっている生徒、また今年の3月に應典院で開催された「space×wave」に参加した生徒など、多彩な顔を毎日見ていました。今年の統一テーマは「助け合い」だったとのこと。space×waveの講師も勤めたサポートスタッフたちは、その際の経験を活かし、どうすれば助け合いの輪が広がるかを心がけたようです。そして、生徒たちが自分たちで答えを出すことができるよう、答えを教えるのではなくヒントを出す立場として、高校生たちの舞台作りを丁寧に支えていました。
今年は、自分達で手掛けた脚本が多く、高校生の等身大の作品が上演されている事もあり、自分たちの考え、表現、使う言葉を着飾らず、各校がありのままの思いを客席にぶつけていました。限られた時間中での演劇活動であるものの、高校生たちは公演を通じて自分自身に向き合います。輝きに満ちた高校生たちにスタッフ陣も心が癒されたようです。
印象的だったのは、3年生たちが帰り際にスタッフたちにお礼を言っている姿でした。HPFの卒業生たちが應典院で公演をする事も徐々に増えて来ています。HPFの歴史と應典院の歴史が重なってきています。来夏もまた、多くの高校生が應典院で可能性や独創性があふれる作品を見せて欲しいと期待をしています。
小レポート
ペシャワール会「伊藤和也君追悼写真展」開催
10月20日より25日まで、應典院の2階ロビー「気づきの広場」にて「アフガンに緑の大地を」と題した写真展が開催されました。この写真展は、2008年8月、アフガニスタンの復興支援のために農業指導の活動に取り組む中、31歳の若さでこの世を去った伊藤和也さんの遺作展でした。22日には静岡よりご両親も来られました。印象的だったのは、企画者(ペシャワール会)の方が、「展示の全てを通じて訴えかけてくる思いの重さを、お墓を眺めながら感想を書くことで、徐々に受け止めることができた」と仰ったことです。
この写真展は、この3月から福岡を皮切りに全国を巡回し、今後徳島、広島の福山、沖縄の那覇、兵庫の伊丹、そして東京の渋谷と続きます。ちなみに、お寺での開催は大阪のみ。今回、ご覧頂けなかった方には、4月に遺稿・追悼文集が、9月に写真集が刊行されていますので、手にとっていただき、故人に思いを馳せて頂ければ、と願います。
小レポート
「大阪市近代美術館あり方検討委員会」参加中
今年度、應典院寺町倶楽部より、山口事務局長が「大阪市近代美術館あり方検討委員会」に参加しています。同館は既に基本計画が1998年にまとめられたものの、財政状況の悪化等により事実上建設事業が停止されていました。今回委員として招かれたのは、今後の方向性について議論をするにあたり、市民参加やNPOとの協働といった新たな視点を交えることになったためです。
あまり知られていませんが、既に建設準備室では4000点を超える作品が収集され、その内3000点以上は寄贈によるものです。應典院にも馴染みのある加藤種男さんも委員の一人なのですが、曰く、大阪市の近美は「うさぎを追い抜けるかどうかの微妙な状況の亀」とのこと。会議資料や議事録、また開催案内は大阪市のwebで公開されていますので、どうぞ、ご関心くださいませ。
コラム「劈」
やすらぎと集中の中で
竹内敏晴さんが真のやすらぎへと旅立った日に
1999年2月11日、竹内敏晴さんのレッスンの旗揚げ講演(第15回寺子屋トーク「日本語のレッスン」:左写真)の日は、冷たい雪と雨が混じる悪天候。予想をはるかに超える185名が参加した。時代が竹内敏晴を求めているかのような人の波だった。それから10年間、應典院は、やすらぎと集中の場となった。
時、不況の真っ只中、社会の閉塞感は、人々に緊張を強い、人の「からだと、こころと、ことば」は悲鳴を上げていた。自分らしく生きるために自分を変えたいと願う人たちが、ことばによる説明や説得ではなく、自分自身のからだを通して、他者との関係において、自分で気づいていく。竹内レッスンはその気づきを提供する場だといえるだろう。
人が変わるには、まず自分に気づくことが必要だ。世間や他者に対してもつ身構え、あわせてしまうからだ。相手を拒否するからだとことばに、レッスンの場で気づいていく。
緊張の場では、人は気づけないし、変われない。緊張せずに、安心していられる場がまず必要だ。竹内レッスンでは、必ず二人組で、互いのからだを揺らし合い、やすらぐことから始める。心地よい、安心できる場には、常に大きな歌声と、大きな笑いがあった。
一方、他人の目を意識する緊張の場で、自分を支え、からだとことばで表現する場も必要だ。大勢の観衆の前でひとり舞台にたつ芝居は、たやすい課題ではない。「12人の怒れる男」「ゲド戦記」「銀河鉄道の夜」など数々の舞台で輝く多くの人を見てきた。
竹内敏晴さんは、6月に膀胱がんが見つかったが、手術を受けず、現役でレッスンを続けることを選んだ。7月の大阪のレッスンを行い、8月末の東京のオープンレッスンでは、車いす姿で見守った。9月7日、数人のレッスン生の歌う、竹内さんの大好きだった、「ぎんぎんぎらぎら夕日が沈む…」の歌声と共に、84歳の生涯の幕を下ろした。常に人に安らぎを与えてこられた竹内さん。今度はご自分がゆっくりとお休み下さい。
伊藤 伸二(日本吃音臨床研究会・会長)
大阪教育大学講師(言語障害児教育)を退職し、吃音研究者としてではなく、生活者、当事者として取り組む道を選び、カレー専門店を10年間経営。現在は大学や専門学校で非常勤講師として、吃音や、対人援助の理論と実際を教えている。1965年、どもる人のセルフヘルプグループを設立。1986年、第一回吃音世界大会を京都で開催。現在43か国が加盟する国際吃音連盟を設立し、3年ごとに世界大会を開催し、第8回大会がアルゼンチンで予定されている。現在應典院で、大阪吃音教室を毎週金曜日に開いている。
自分の体験をもとに、学童期、思春期の子どもに語りかけた『どもる君へ、いま伝えたいこと』(解放出版社)が11冊目の著作。
Interview「覚」
「アーユス」とはサンスクリット語で「いのち」。
己を見つめ、自分の存在を究め明らかにする「己事究明」を
出会う人々の〈いのち〉の物語に寄り添うことで実践する。
「菩薩行ですよ」。隠元禅師を開祖とする黄檗宗の自敬寺住職で、アーユス仏教国際協力ネットワークの関西事務局長を勤める服部さんは、「なぜ多彩な活動をしているのか」の問いに、ためらいなく答えた。
お寺に生まれ、小中学校の教員を兼職してきた父を見て育ってきた。本山での修行道場で開催された花祭りを体験、子ども会活動を始めるきっかけになった。学生時代にお世話になった、南太平洋友好協会の山田無文初代会長(元・花園大学学長)の誓願に感動し、サイパン島と日本の青少年交流をお寺で受け入れることが、国際的な活動への関心を深めるきっかけとなった。また、全国青少年教化協議会、関西NGO協議会など、ネットワーク組織との関わりが、発想と人脈の幅を広げたという。
「隠匿を積むという表現がありますが、お寺が表に出て『お寺もやってます』ということがあっていいと思っています。ただし『あの寺だからできる』となってしまうと、逃げる口実をつくってしまう。むしろ、特異性を動機付けとして『あそこは別』と思われないようにしないと。應典院もそうでしょう?」
秋田光彦大蓮寺住職・應典院代表とはアーユス関西でも活動を共にしており、互いに「きょうだいのような仲」と自認する。秋田住職が自敬寺の子ども会活動の取材をして以来、互いに親交を深めた。そして、阪神・淡路大震災でも共に被災地に赴いた。
「社会とどう関わるか、震災で目覚めました。救援物資を持って六甲アイランドまで駆けつけたのですが、マスコミの報道で逆に物があふれていました。何が出来るか考えていた私たちは、大阪の仏教8団体と協力し『仏教ボランティア大阪』を立ち上げました。そこでは『お話ボランティア』として被災者のお話を聞く活動をしていました。」
超宗派の僧侶らによるボランティア等の活動だけでなく、地域での活動を活発化する契機となったのもまた震災のときであった。中でも、お寺がある淀川区内に建設された「十八条仮設」への支援は、人々の〈いのち〉に寄り添う拠り所となった。
「淀川で、淀川から」のこだわりが、人々を結びつけた。特に95年6月17日の「さあ、はんしんは、あさ」と名付けられたフォーラムが、仮設の中と町の中とをつなげるきっかけとなったという。服部さんは地域のコミュニティ誌「ザ・淀川」の編集長の南野佳代子さんに生活支援情報を掲載することを提案し、その後4年間、最後の入居者が仮設住宅を出るまで同誌は届けられ続けた。
「あれから15年、一緒に活動した方々が次々に亡くなっています。『一芸・一座』など、当時の支援の輪で誕生した活動は今でも続けていますが、その原資は、皆さんからの寄付です。」
先般、9月18日に行われた南野さんの葬儀・告別式の祭壇にも、「NGO自敬寺」と書かれた花が置かれた。「NGO自敬寺」とは、自敬寺の一部門だ。十八条仮設で出会い、被災者の立場から生活再建支援法の成立に取り組んだ佐々木康哲さん(08年没)と、フラメンコダンサーの橋本美千子さん(00年没)、このご夫妻の願いと浄財をもとに、社会活動を進めていく看板として掲げられた。
「境内のお釈迦さんの隣にある摩尼車も、橋本さんの発願と浄財で建立しています。そこには引導の際に伝えた『慈しみの心は人々のこころに勇気を育む』ということばを刻ませていただきました。活動への参加や支援を通じて、人々が間接的に菩薩行をする、それがNGO自敬寺の発想です。」
編集後記〈アトセツ〉
この9月、休止中だった應典院のブログを再開した。きっかけは竹内敏晴先生の訃報を伝えるためだった。まさか次の投稿が南野佳代子さんへの追悼の思いを綴ることになるとは予想だにしなかった。今号ではコラムとインタビューで両名を取り上げ、應典院寺町倶楽部の追悼の念を込めている。
最早世に浸透しきったブログではあるが、今年はインターネット界で「Twitter(ついったー)」と呼ばれる米国発のサービスが爆発的に広まった。公式には「リアルタイム・ショートメッセージサービス」と位置づけているようだが、簡単に言えば140字のミニブログである。應典院も実名で登録し始めている。特徴は、いわゆる読者として「つぶやき」を追いかけやすい仕組みと仕掛けを織り込んでいることだ。
こうした新しいコミュニケーション・システムは、時代が要請しているのかもしれない。ただ、省みれば、冒頭で触れたお二人は、電気通信を通じて画面に表示される文字のやりとりとは対極にある取り組みを重ねてこられた。竹内先生は「発声」で、南野さんは「誌面」で、である。
今号では、伊藤和也さんの追悼写真展のことも伝えた。別れを惜しむ人は、それぞれに故人を物語る。「声の産婆」と呼ばれた竹内先生のことは多くの方がそれこそブログ等で悲しみを綴り、南野さんの葬儀で導師を勤めた服部さんは引導の際に「人と人とを数珠をつなぐように結び…」と万感を込めた。それぞれの人生で追究された「つながりの大切さ」を大切にしたい。 (編)
