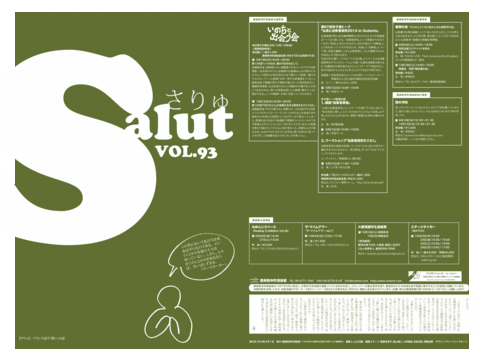
サリュ 第93号2014年9・10月号
目次
巻頭言
レポート「エンディングセミナー2014」
コラム 花岡正義さん(「やさしい日本語」有志の会代表)
インタビュー 坂本アンディさん(がっかりアバター代表)
アトセツ
レポート「エンディングセミナー2014」
コラム 花岡正義さん(「やさしい日本語」有志の会代表)
インタビュー 坂本アンディさん(がっかりアバター代表)
アトセツ
冒頭文
この世において私たちは死ぬはずのものである、ということわりを他の人々は知っていない。しかし、人々がこのことわりを知るならば、争いはしずまる。
『テーラガーター』
『テーラガーター』
report「契」 死後の不安に寄り添う
お寺とNPOの協働へ生前契約とはなにか
去る7月5日、お盆前の恒例となっている「エンディングセミナー」が、浄土宗大蓮寺で開催されました。「おひとりさま、最後の終活~お寺とNPOの『生前契約』~」と題した今回のセミナーでは、葬儀の執行、部屋の片づけ、年金や公共料金の処理など、自らの死後に必要となる事務を契約によって第三者に委託する「生前契約」を議論の中心に、「個人主義の時代、共助のためにどのような仕組みが必要なのか」が語り合われました。
冒頭の基調講演では、NPO法人りすシステム代表理事、杉山歩さんが約20年前から取り組んでいる、生前契約について学びました。「自分の生きた痕跡は自分で後始末をつけたいという自己決定も、実際に全うするには、死後に誰かの手を借りなければなりません。」以前は死後の整理は主に親族がその役割を引き受けていましたが、無縁社会と言われる今、単身者の方はもとより、安心して親族に頼ることができるとは限りません。そこで杉山さんたちは、死後の安心を法的に保障する「生前の委任契約」を通じて、本人の意志を実行にうつす「リビング・サポート・サービス・システム」(略称:LiSS)を立ち上げました。
りすシステムの特徴は、生前契約を死後事務のみにとどめず、生前事務や後見事務など、契約された方と生前から豊かな関わりを重ねていることです。例えば外出時の付き添い、入院時の保証人、平時の安否確認など、複数の第三者が日々の暮らしを支えることで、個別の支援者ではなく組織とのあいだの信頼関係が長期的かつ継続的に構築されていきます。杉山さんによれば、他人であることが逆に強みとなり、「親族には言いにくいことも相談できる」とおっしゃる方が多いそうです。死後の関わりは生前の関わりの延長にのみ成立すると実感できる取り組みです。
冒頭の基調講演では、NPO法人りすシステム代表理事、杉山歩さんが約20年前から取り組んでいる、生前契約について学びました。「自分の生きた痕跡は自分で後始末をつけたいという自己決定も、実際に全うするには、死後に誰かの手を借りなければなりません。」以前は死後の整理は主に親族がその役割を引き受けていましたが、無縁社会と言われる今、単身者の方はもとより、安心して親族に頼ることができるとは限りません。そこで杉山さんたちは、死後の安心を法的に保障する「生前の委任契約」を通じて、本人の意志を実行にうつす「リビング・サポート・サービス・システム」(略称:LiSS)を立ち上げました。
りすシステムの特徴は、生前契約を死後事務のみにとどめず、生前事務や後見事務など、契約された方と生前から豊かな関わりを重ねていることです。例えば外出時の付き添い、入院時の保証人、平時の安否確認など、複数の第三者が日々の暮らしを支えることで、個別の支援者ではなく組織とのあいだの信頼関係が長期的かつ継続的に構築されていきます。杉山さんによれば、他人であることが逆に強みとなり、「親族には言いにくいことも相談できる」とおっしゃる方が多いそうです。死後の関わりは生前の関わりの延長にのみ成立すると実感できる取り組みです。
契約と宗教は相容れない?
講演の後は、葬送アドバイザーの廣江輝夫さんと秋田光彦住職が加わり座談会となりました。実は、りすシステムと大蓮寺は今後協働して生前契約を導入する予定です。そこで、なぜお寺が生前契約に関わるのか、そこに生まれる課題は何かを深めました。
遺族サポート「ひだまりの会」に取り組まれている廣江さんは「生老病死の病と死のあいだが長くなってきた今、死については文書で遺す時代から行動に移す時代に変わってきた」といいます。そして「お寺も葬儀社も踏み込めない領域を、りすシステムがNPOの立場から補完してくれている印象がある」と活動を評価しつつ、「自己責任」の論理に則らない宗教的ケアの重要性を指摘されました。
また、秋田住職は「宗教儀礼を契約項目に盛り込み、火葬と埋葬を確実に行うのが、大蓮寺が関わる生前契約の特徴だ」と語り、契約者を「消費者」に留めぬよう、僧侶による生前からの教化が重要となるという姿勢を示しました。一方で、お寺が生前契約に関わることで「死の個人化」を促進してしまう恐れや、お布施の金額が商品のように契約で決められるなど、儀礼の制度化への抵抗感が吐露される場面もありました。
それに対し、杉山さんは「契約は必ずしもつながりを断ち切るものではなく、信頼関係構築の基盤となる約束事であり、個人が縁を結び合うきっかけにもなるはず」と応答し、大蓮寺の理念とは相反しないと主張されました。自己責任の時代に、弱さを核にしたつながりの構築に向け、課題と可能性が交錯する二時間半となりました。
遺族サポート「ひだまりの会」に取り組まれている廣江さんは「生老病死の病と死のあいだが長くなってきた今、死については文書で遺す時代から行動に移す時代に変わってきた」といいます。そして「お寺も葬儀社も踏み込めない領域を、りすシステムがNPOの立場から補完してくれている印象がある」と活動を評価しつつ、「自己責任」の論理に則らない宗教的ケアの重要性を指摘されました。
また、秋田住職は「宗教儀礼を契約項目に盛り込み、火葬と埋葬を確実に行うのが、大蓮寺が関わる生前契約の特徴だ」と語り、契約者を「消費者」に留めぬよう、僧侶による生前からの教化が重要となるという姿勢を示しました。一方で、お寺が生前契約に関わることで「死の個人化」を促進してしまう恐れや、お布施の金額が商品のように契約で決められるなど、儀礼の制度化への抵抗感が吐露される場面もありました。
それに対し、杉山さんは「契約は必ずしもつながりを断ち切るものではなく、信頼関係構築の基盤となる約束事であり、個人が縁を結び合うきっかけにもなるはず」と応答し、大蓮寺の理念とは相反しないと主張されました。自己責任の時代に、弱さを核にしたつながりの構築に向け、課題と可能性が交錯する二時間半となりました。
小レポート
土着の映画で
宗教文化に迫る
去る7月13日、コミュニティ・シネマ・シリーズの第21弾として、映画『波あとの明かし』の上映が行われました。岩手県宮古市出身の坂下清監督をお招きし、鑑賞者との対話の場が設けられました。また、英語の字幕入りの作品ゆえに、上映前には「やさしい日本語」有志の会と「東日本大震災復興サポート協会」との協働で、防災に関する体験学習も実施しました。さらに本シリーズ第20弾『僕らはココで生きていく』の上映の際にお世話になった「泉州てらこや」の協力により、東北の物産展も併催されました。
映画と講演を通じて、宮古では地区ごとに飾りや焚き方の形は違えど、市内一円で同じ日に開催して先祖を供養するという型は変わらず継承されてきた意味を深める機会となりました。「なぜするのか」は語られなくとも「続けることで忘れえない」風習として定着してきた豊かな文化に触れる一日でした。
映画と講演を通じて、宮古では地区ごとに飾りや焚き方の形は違えど、市内一円で同じ日に開催して先祖を供養するという型は変わらず継承されてきた意味を深める機会となりました。「なぜするのか」は語られなくとも「続けることで忘れえない」風習として定着してきた豊かな文化に触れる一日でした。
小レポート
キッズ・ミート・アート、今年も始まりました
昨年2日間にわたって、應典院、大蓮寺、パドマ幼稚園を会場として開催したキッズ・ミート・アート。今年度は連続企画として、小規模の催しを数回に分けて実施いたします。
本年度第一弾、子どもとおとなのためのクラフト・ワークショップ「タテイトのふしぎ、ヨコイトのまほう」が、7月21日に應典院で開催されました。講師に星ヶ丘洋裁学園のミヨシキミコさんとアーティストのBOMさんを迎え、33名の参加をいただきました。紐を組み合わせ、糸で縫い、バッチやTシャツに仕上がりました。次回は11月24日に駒川商店街ココロホールにて開催の予定です。
小レポート
想いを詩にのせる
8月4日、詩の学校お盆編「それから」が開催されました。この企画は、詩人の上田假奈代さんが毎月開催されている詩作と朗読の会を、大蓮寺本堂と墓地にて実施するものです。
今年は当会事務局長の山口洋典の講話、墓地での詩作と朗読、そして秋田光彦住職の法話という流れとなりました。今は亡き大切な人へ宛てた詩、自身の死へ向き合う詩などがあり、明るく詠む方から涙ながらに詠む方まで、様々な方の想いがうかがえました。終了後は会場を應典院に移しての交流会で、感想や詩に綴った想いを、それぞれが整理するように語り合われました。
今年は当会事務局長の山口洋典の講話、墓地での詩作と朗読、そして秋田光彦住職の法話という流れとなりました。今は亡き大切な人へ宛てた詩、自身の死へ向き合う詩などがあり、明るく詠む方から涙ながらに詠む方まで、様々な方の想いがうかがえました。終了後は会場を應典院に移しての交流会で、感想や詩に綴った想いを、それぞれが整理するように語り合われました。
コラム「易」
災害弱者(外国人)を救う
阪神・淡路大震災や東日本大震災で多くの人が被災したが、その中に多くの外国人がいたことはあまり知られていない。彼らが災害の知識に乏しく、特に災害時に使われる日本語が理解できないために、正確な情報を得ることができず被害が拡大した、ということが言われている。
また、国や自治体の「防災計画」にも災害時要援護者(または要支援者)という言葉があり、外国人も含まれているが、その理由は「災害の知識がなく、日本語が理解できない」ためとある。もし災害の知識があり、日本語が理解できたなら、多くの外国人の被害は少なくなったはずである。
阪神・淡路大震災の直後、弘前大学の佐藤和之教授らが「日本に住む外国人なら、簡単な日本語は理解できるはず」と、災害時の情報を出し始めたのが「やさしい日本語」のはじまりである。「文を短くして構造を簡単にする」「難しい言葉は使わない」「漢字やカタカナにはルビを振る」「カタカナ外来語は使わない」等のルールがある。使うには少しの訓練が必要だが、そんなに難しいものではない。災害時に日本人が「やさしい日本語」で、自分の身近にいる外国人に対してちょっと声を掛けてあげるだけで、多くの外国人が助かるのである。
最近では、この「やさしい日本語」が防災だけでなく各方面で注目され始めている。役所や自治体が出す文書を「やさしい日本語」にしようとする動きが始まっているし、ある地下鉄の車内放送でも使われ始めた。外国人の子供が多い学校でも、保護者向けの「お知らせ」に使われている。
今回、應典院での初めてのワークショップを行った。どんな人に参加してもらえるか全く見当がつかず、直前まで話す内容に苦労したが、今後の活動を考えるといろいろ勉強になった。仏教が人を救い、「やさしい日本語」が外国人を救う。こんなところでまとめとしたい。
また、国や自治体の「防災計画」にも災害時要援護者(または要支援者)という言葉があり、外国人も含まれているが、その理由は「災害の知識がなく、日本語が理解できない」ためとある。もし災害の知識があり、日本語が理解できたなら、多くの外国人の被害は少なくなったはずである。
阪神・淡路大震災の直後、弘前大学の佐藤和之教授らが「日本に住む外国人なら、簡単な日本語は理解できるはず」と、災害時の情報を出し始めたのが「やさしい日本語」のはじまりである。「文を短くして構造を簡単にする」「難しい言葉は使わない」「漢字やカタカナにはルビを振る」「カタカナ外来語は使わない」等のルールがある。使うには少しの訓練が必要だが、そんなに難しいものではない。災害時に日本人が「やさしい日本語」で、自分の身近にいる外国人に対してちょっと声を掛けてあげるだけで、多くの外国人が助かるのである。
最近では、この「やさしい日本語」が防災だけでなく各方面で注目され始めている。役所や自治体が出す文書を「やさしい日本語」にしようとする動きが始まっているし、ある地下鉄の車内放送でも使われ始めた。外国人の子供が多い学校でも、保護者向けの「お知らせ」に使われている。
今回、應典院での初めてのワークショップを行った。どんな人に参加してもらえるか全く見当がつかず、直前まで話す内容に苦労したが、今後の活動を考えるといろいろ勉強になった。仏教が人を救い、「やさしい日本語」が外国人を救う。こんなところでまとめとしたい。
花岡正義(「やさしい日本語」有志の会代表)
1946年生まれ。佐賀県出身、京都府京田辺市在住。会社を早期退職し、日本語学校へ。その後、京都YWCAで日本語ボランティアやさまざまなボランティア活動を経験。日本語ボランティアネットワーク「京都にほんごRings」事務局長の傍ら、5年前に自ら結成した「やさしい日本語」有志の会の代表を務める。外国人向け防災教育の教材開発や、各方面に向けたワークショップなどを行う。昨年から福島での活動も始めている。福島移住女性支援ネットワーク協力委員。
interview「才」坂本アンディさん
(がっかりアバター代表)
space×drama2014では優秀劇団に選出。
変容しつづける彼らの過去と現在、そして
今後に向けた展望を伺う。
劇団「がっかりアバター」は、應典院舞台芸術祭space×drama2014で上演された『あくまのとなり。』で優秀劇団に選出され、来年度の協働プロデュース公演を行うことが決定している。旗揚げ以降、全作品の作演出を務める代表の坂本アンディさんにお話を伺った。「喉から手が出るほど欲しいと思っていたので、優秀劇団が発表された時はでかい溜息が出ました。徐々に経験を積んできて、劇団として次のステップに進みたい時期だったので、賞を目指して必死で挑んだ結果です。お母さんも喜んでくれました。」
演劇を志したのは、中学生の頃にインターネットで「大人計画」の公演を目にしたことがきっかけだという。「学校にまともに行けてないような子どもだったので、世間的にやっちゃいけないことをやってるのに、認められている大人がいることが衝撃でした。本格的に演劇がやりたくて、エンターテイメントが学べる高校に進学したものの、稽古に人は集まらないわ、発表会ではお客さんに唖然とされるわ、地獄の日々でしたね。」
より多くの人に見てもらいたいと、高校の後輩たちと「がっかりアバター」を旗揚げするが、第一回公演が大失敗に終わる。その後、「性」を主題とした公演を重ねて評価を高めてきたが、『あくまのとなり。』の制作は更なる転機となった。「表現に対するこだわりはなくなりました。過激でセクシャルな表現にしばられていた時期もありましたが、僕は一貫したコンセプトを持っている作・演出家にはなれないし、A常に変わっていくほうが楽しいと気付いた。今は手数を増やしている最中なので、作風もどんどん変化していくはずです。」
これまでの活動を経て、坂本さんだけでなく他の劇団員たちにも変化があらわれているそうだ。「うちは劇団員が超マイノリティで、『今までよく生きてこれたな…』っていうくらい生きづらい人ばかりなんです。彼らが桁違いに不幸なので、僕が幸せにしてやらないといけないっていう変な責任感はあります。でも、最初の頃は演劇が彼らの鬱憤の捌け口になっていた印象ですが、最近は生活の一部に変わってきていると感じます。『僕のやりたいこと』が、自然に『彼らのやりたいこと』にもなっている。演劇について、あつい議論を交わすこともできるようになりました。」
来年度のspace×dramaをリードする立場として、かける意気込みは当然大きい。「年内は短編の公演が続きますが、そこで色々実験を積み重ねたいと思っています。来年の協働プロデュース公演は、この一年間の集大成と言えるものにしたい。そういえば、先ほど写真を撮るためにお墓の中を歩いて、シアトリカル應典院がお寺であることをはじめて意識しました。そのことも作品に影響してくるかもしれませんね。」
インタビューの最後、演劇をやっていて良かったことは?という問いにはこう答えてくれた。「自分のやりたいことに嘘をつかないで、正直にいられるようになったこと。つまり、自分らしく生きられるようになったってことですね……。って、カッコよく締めようかと思いましたが、結局僕はモテたいんですよ!女性ファンの方に『アンディさん、握手してください』って言われる瞬間が一番幸せです!」
演劇を志したのは、中学生の頃にインターネットで「大人計画」の公演を目にしたことがきっかけだという。「学校にまともに行けてないような子どもだったので、世間的にやっちゃいけないことをやってるのに、認められている大人がいることが衝撃でした。本格的に演劇がやりたくて、エンターテイメントが学べる高校に進学したものの、稽古に人は集まらないわ、発表会ではお客さんに唖然とされるわ、地獄の日々でしたね。」
より多くの人に見てもらいたいと、高校の後輩たちと「がっかりアバター」を旗揚げするが、第一回公演が大失敗に終わる。その後、「性」を主題とした公演を重ねて評価を高めてきたが、『あくまのとなり。』の制作は更なる転機となった。「表現に対するこだわりはなくなりました。過激でセクシャルな表現にしばられていた時期もありましたが、僕は一貫したコンセプトを持っている作・演出家にはなれないし、A常に変わっていくほうが楽しいと気付いた。今は手数を増やしている最中なので、作風もどんどん変化していくはずです。」
これまでの活動を経て、坂本さんだけでなく他の劇団員たちにも変化があらわれているそうだ。「うちは劇団員が超マイノリティで、『今までよく生きてこれたな…』っていうくらい生きづらい人ばかりなんです。彼らが桁違いに不幸なので、僕が幸せにしてやらないといけないっていう変な責任感はあります。でも、最初の頃は演劇が彼らの鬱憤の捌け口になっていた印象ですが、最近は生活の一部に変わってきていると感じます。『僕のやりたいこと』が、自然に『彼らのやりたいこと』にもなっている。演劇について、あつい議論を交わすこともできるようになりました。」
来年度のspace×dramaをリードする立場として、かける意気込みは当然大きい。「年内は短編の公演が続きますが、そこで色々実験を積み重ねたいと思っています。来年の協働プロデュース公演は、この一年間の集大成と言えるものにしたい。そういえば、先ほど写真を撮るためにお墓の中を歩いて、シアトリカル應典院がお寺であることをはじめて意識しました。そのことも作品に影響してくるかもしれませんね。」
インタビューの最後、演劇をやっていて良かったことは?という問いにはこう答えてくれた。「自分のやりたいことに嘘をつかないで、正直にいられるようになったこと。つまり、自分らしく生きられるようになったってことですね……。って、カッコよく締めようかと思いましたが、結局僕はモテたいんですよ!女性ファンの方に『アンディさん、握手してください』って言われる瞬間が一番幸せです!」
〈アトセツ〉
人はモノではない。先般、ある講演会でそんな問いをなげかけた。いや、人物という言い方があることは百も承知である。ただ、その講演会では持続可能な社会を目指すための教育がテーマとされていたこともあって、果たして人材育成という表現を使うのは適切か、と問題提起をさせていただいたのだ。
言葉にこだわりすぎているという批判もあろう。しかし、人を社会の「材料」として取り扱うことに対する関心を向けて欲しいというのが願いである。同じような視点で見つめる方も増えてきたためか、時折、表記をもじって、人材を「人財」と綴られる機会も増えてきた。人は材料ではなく財産である、そう見立てているのだろう。
夏の初め、佐世保の女子高生殺害事件が報じられた。報道によれば、加害者は「人を殺してみたかった」「解体してみたかった」などと供述したという。既に亡くなった被害者の方がその思いをどう受けとめることになったのかは不明だ。しかし、この残忍な行為は、加害者と被害者のあいだで互いに心が通い合った瞬間があったからこそ可能となったのではなかろうか。
この事件は対人関係における「人のモノ化」の象徴と捉えられる。ただ、殺す、解体する等の行為の前に、彼女らはその場に共にいる存在であったはずだ。人材を育成する行為、またその表現に抱く違和感は、する側とされる側の明確な区別の構図への反発でもある。実はそれが当事者研究への着目にも通じている。 (編)
言葉にこだわりすぎているという批判もあろう。しかし、人を社会の「材料」として取り扱うことに対する関心を向けて欲しいというのが願いである。同じような視点で見つめる方も増えてきたためか、時折、表記をもじって、人材を「人財」と綴られる機会も増えてきた。人は材料ではなく財産である、そう見立てているのだろう。
夏の初め、佐世保の女子高生殺害事件が報じられた。報道によれば、加害者は「人を殺してみたかった」「解体してみたかった」などと供述したという。既に亡くなった被害者の方がその思いをどう受けとめることになったのかは不明だ。しかし、この残忍な行為は、加害者と被害者のあいだで互いに心が通い合った瞬間があったからこそ可能となったのではなかろうか。
この事件は対人関係における「人のモノ化」の象徴と捉えられる。ただ、殺す、解体する等の行為の前に、彼女らはその場に共にいる存在であったはずだ。人材を育成する行為、またその表現に抱く違和感は、する側とされる側の明確な区別の構図への反発でもある。実はそれが当事者研究への着目にも通じている。 (編)
