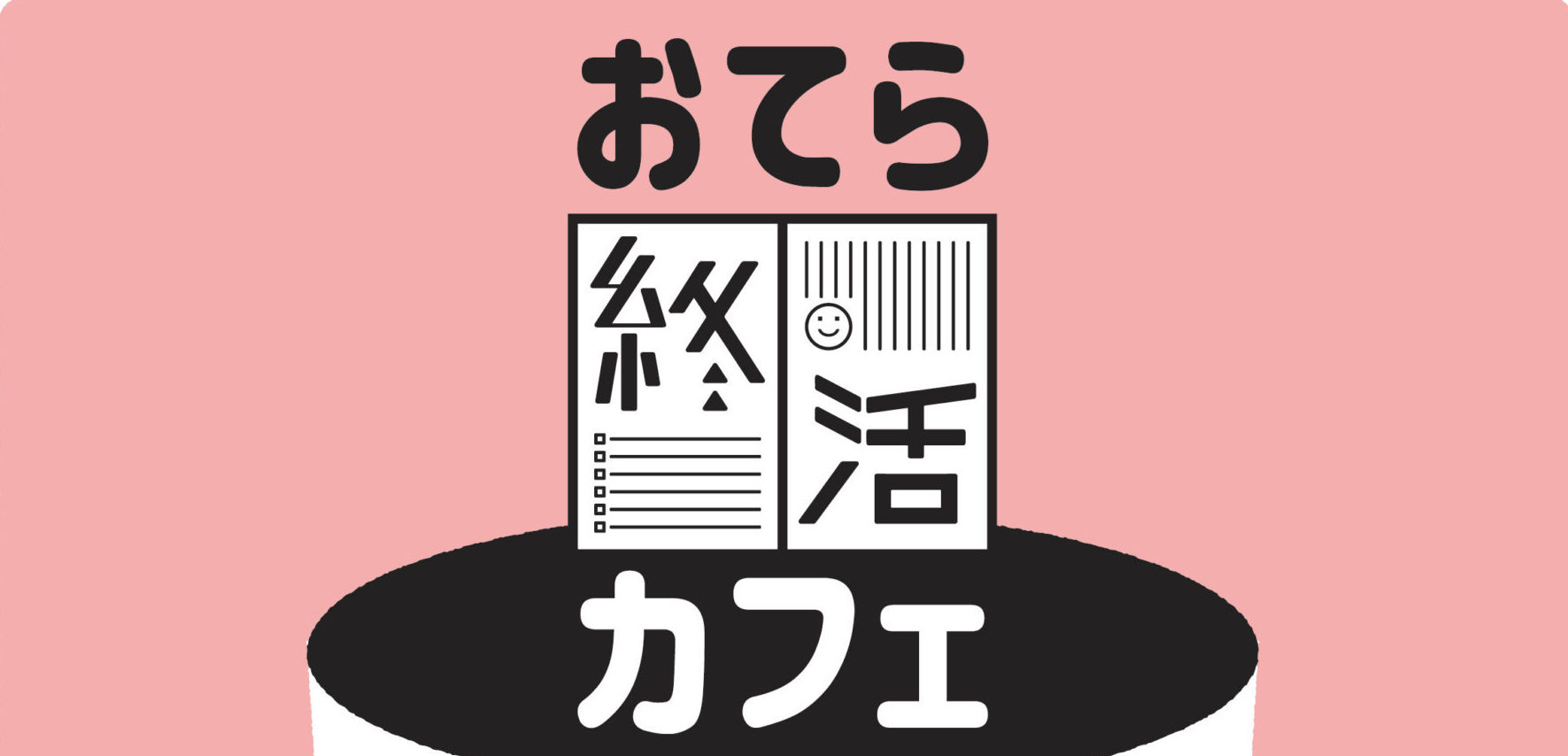
2025/3/28 「おてら終活カフェ/お坊さんに聴く」2024年度ふりかえり(前半)
2024年度も「おてら終活カフェ/お坊さんに聴く」において、多彩なゲストにお越しいただきました。終活に関する具体的な視点や行動を知り、自分の状況と照らし合わせると同時に、さまざまな分野で活躍されている実践者や、宗派を超えた僧侶の歩みを聞くことで、自身の内面や精神性に目を向け、周囲への有難さやお陰様の気持ちを考え、いまを生きる尊さを想うきっかけとなる時間を過ごすことができたように思います。
■4月16日(火)『介護職だからできる最期の関わり方』/田井大介(株式会社TRUST Relation)


高齢者福祉施設において、看取りやお墓のことまでを考えて実践しておられる場所は多くありません。ゲストの田井さんの運営されている施設では、利用者さんの気持ちを真っ向から受け止め、時には一緒に趣味に出かけたり、住み慣れた家に近づけるために、部屋の扉に実家の玄関の写真を大判で貼り付けたり、家具もできるだけ持ち込めるように試行したりと、一人ひとりを自分の家族のように受け入れています。そして最期のときまで施設みんなで看取り、さらに利用者さんを供養するためお墓も建立され、亡くなった後も繋がりつづけています。坊主頭で体格も大きな田井さんですが、胸に秘めた優しさの塊のような熱い思いが伝わってきて、こちらもエネルギーが漲ってくるようでした。またコロナ禍で食料を担保する意味も込めて、お米とお茶づくりをはじめた田井さん。理解あるスタッフのおかげだと言いながらも、着実に歩みをすすめていく姿に、周囲から信頼を寄せられていることが伝わりました。
田井さんは、高齢者施設と並行してBUDDY株式会社にて家財整理のお仕事もされており、そのつながりから應典院にて『家じまいを考える写真展「キオクノキロク」』を開催したことがあります。参考記事はこちら→https://www.outenin.com/article/article-17797/
■5月21日(火)『終活でやるべきこと5選』/長井俊行(⼀般社団法⼈つむぐ代表理事、相続⼿続⽀援センター関⻄所⻑)


過去2回、終活カフェにお呼びしている長井さん。「ザ・終活」といった実務的な事柄をわかりやすく面白くお話いただきました。自分の老いと死をどのように考え、整理していくのか、それにはまず、喪主の決定とお墓の決定や引継ぎ、介護が必要になったときのこと、財産の管理と死後の分与について、これらが大切だとお話されました。ただし一人ひとりのご状況は全く違うので、信頼できる専門家に相談しながら進めていくことが大切です。財産については、そんなにないからと放置するのではなく、遺言書や公正証書にまとめておくことで、死後の事務が格段にスムーズになり、遺されたご家族の負担が減ります。ただし、お墓にしても介護にしても、一方的に自分で決めつけるのではなく、やはり家族と相談し、想いを伝えあうことが肝心。ですが、家族は思うようにいかないのも現実。いかに生きるかはいかに死ぬかに直結します。終活は実務的な要素が大きいですが、同等に、想いや生き様、思想が見えるものです。長井さんは、終活にかかわる細やかなところまでフォローできるよう、スタッフのみなさんとともに駆け回っておられ、参加者のみなさんからも多くの質問や関心が寄せられました。
■6月18日(火)『お坊さんに聴く~修験の道 看護の道』/中川龍伽(竜王山宝池寺住職、訪問看護ステーションれんげ庵代表取締役)


明るいお声とお天道様のような笑顔の中川さんに、ご自身の歩みをお話いただきました。中川さんは、子どもの頃から僧侶へ憧れを抱いておられたそうです。しかしあまりそれを表に出すことはなく、社会人になって会社員になったものの、当時は女性の活躍に大きな壁があり、そこから看護師へ転職されました。看護師の仕事はとても肌に合い、長く勤めていましたが、どこかでずっと仏教や僧侶の生き方が脳裏をかすめておられたそうです。ある時、いのちを助ける看護師と人生を守る仏教(とくに不動明王)の在り方の重なりの気づき、やはり自分は僧侶になりたいという想いが溢れてきたそうです。そこからは、不思議なご縁に導かれるように、師僧と出逢い、厳しい修行を幾度も経験し、現在は竜王山宝池寺のご住職として寺を守っておられます。またご自身で訪問看護ステーションを立ち上げ、さらに「自死に向きあう関西僧侶の会」の会長もなさっておられ、身体と心の両面からサポートされています。中川さんの、己の心と身体で感じ、進むという凛々しくも包み込まれるような姿に励まされるような時間でした。法螺貝の音色も聞かせていただき、あっという間の時間でした。
■7月16日(火)『お坊さんに聴く~ともに生きる』/大西龍心(高野山真言宗 観音院住職)


猛暑のなかの開催でしたが、大西さんの軽快で朗らかなお話に、心やすまる時間でした。観音院は、行基菩薩に由来する、西高野街道が間近にとおる古刹。祖父様が守られていたお寺でしたが、大西さんがぽつりと「自分が継ごうか」と言ったことで直ぐに(半ば強引に‥)進んだそうです。そのころ、幼少中と同級生だった奥様と学生結婚をされ、大学在学中に僧侶資格をとられるなど多忙の日々を過ごされました。奥様との日々のお話や子育てのお話も楽しくお聞かせいただき、幾度となく笑いに包まれました。特に、次のようなお話が印象的でした。「お寺は守るものではなく、御本尊に守られていると感じる。そして僧侶もどんな住職がよいのか、その時代の状況に合わせて御本尊が選んでるんじゃないかと思うことがある」「亡くなった方が残した言葉は、応援にもなるし呪いにもなる。それは表裏一体で自分自身を省みる言葉として残るもの。」「やりたいことが常に尽きない妻だったから、120歳まで生きてもずっとやりたいことを言っていたと思う」。大西さんの微笑みや澄んだ声から、生きるということと死ぬということ、時が進むということ、愛おしさと苦しさ辛さの不可分など、さまざまな想いや事柄が浮かび、参加された方も一人ひとりがそれぞれに想いを受けとめておられるようでした。
<8月はおやすみです>
■9月17日(火)『FPと考えるお金と保険』/福永聖(ファイナンシャルプランナー)


冒頭は、人生で必要なお金を「生活費・住宅費・教育費・老後費・夢や楽しみ費」に分類し、具体的にそれぞれどのくらいを使うのかワークをしながら具体的に考えました。福永さんは「夢・楽しみ」の部分をいかに作るかがFPとしてのやりがいだと言われ、そのためにどのような工夫ができるのか、様々な状況に合わせた相続プランや、保険をはさんだ相続方法などの役立つ情報を、クイズも交えながらご紹介くださいました。参加者からは、家を買うか借りるかや税についての質問や、「お金を残すことばかり考えずに、死ぬまでしっかり使って生きて、死ぬときにはあんまり残ってなくてもいいと思う」というコメントもありました。人生お金だけではない、けれどお金は大切。良くも悪くも、その人の生き方が死に方に表れるともいえるかもしれません。いかに生きるかを考えるためには、自分や家族との生活設計を考え、同時に信頼できる専門家を見つけておくことはやはり重要です。また自分の幸せだけでなく、いまあるおかげに感謝し、他者との結びつきや命の循環、未来のことも思いながら、感謝と畏敬を軸とした「夢・楽しみ」も見つけていきたいものです。
<10月は諸事情によりおやすみです>


後半のふりかえりはこちらへ →https://www.outenin.com/article/article-19701/
