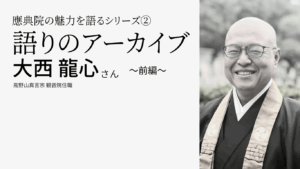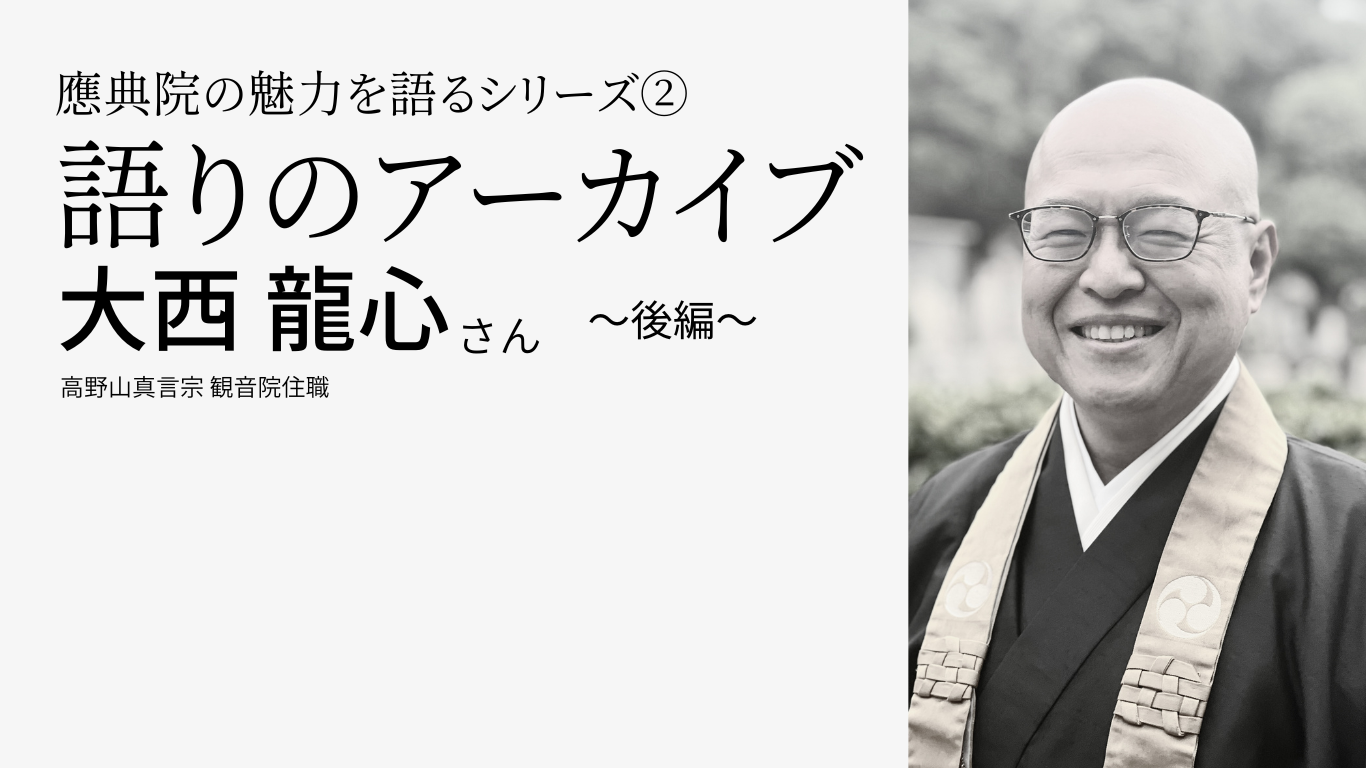
2025/7/4【語りのアーカイブ】應典院の魅力を語るシリーズ②大西龍心さんインタビュー(後編)
應典院のWEBサイトは現在、事業やイベントの告知のみならず、過去事業の開催報告などのアーカイブ、あそびの精舎としての取り組みや狙いを仏教の教えと共に伝えていくことを主な目的としています。情報の提供だけでなく、読み物としても充実したサイトになっていくことを目指して、この度、新たにインタビュー記事の連載を始めることにしました。應典院に縁のある方々から、これまでの應典院との関わりや、場所としての魅力や可能性について語って頂きます。
第2弾は、長く應典院の活動に参加・観察されてきた、真言宗僧侶大西龍心さんにお話を伺いました。今回はその後編です。
インタビュアー/齋藤佳津子
大西龍心(おおにし りゅうしん)
昭和41(1966)年大阪市内の在家に生まれる。小中高はカトリックの学校に通い、神戸大学文学部在学中に母方の祖父のお寺を継ぐことを決意。大学を休学して高野山専修学院に入学、一年の修行の後僧籍を取得して大学院に進学する。平成9(1997)年小学校の同級生であった妻と結婚。平成13年(2001)より観音院住職を拝命し、翌年の祖父の遷化に伴い妻と二人でお寺の運営を行う。一男の父。お寺以外では人権擁護委員や保護司を務める。
ー直近では、3月の「むぬトーク」にもご参加いただきましたね。
今回の内容が「動植物の供養」でして、非常に関心がありました。人間が他の生き物の供養をするようになった歴史から、いろいろな動植物供養の実例、また供養される動植物に見られる特質とかそこの至る動機の問題とか、私のいまいる環境ともすごく共振するものがありました。観音院は天野街道の北端にあるお寺で、祖父が樹木をこよなく愛していましたし、草木塔を建立したり、自然に近いのですね。「草木成仏」が身近に感じられる。そう言いながら、日常的に草をむしり、木を伐採せざるを得ない。供養とは、これによって生きていくことの「やましさ」と、それによって生活を支えてもらっている「感謝」と、もっととりたい「願い」の3つが相まって成り立っていくのだなと。深く考える時間になりました。
ちなみに、この時、参加者もたくさん来ていましたが、中にずっと会いたかった「空師」(高木に登って伐採や枝払いをする職人)の方がいてびっくりしました。これも應典院ならでは、の体験です。
ーそれにしても大西さん、應典院に限らずいろんな場所に参加しておられますね。
いろんな講演やワークに出かけていくことが多いですね。人の語りが非常に好きなんですね。語りのリズムね。私、オンラインが苦手なんです。飽きてしまう。映画館とビデオの違いというか、途中で止められるものはリズムが見えない。生の講演とかは、講師の方のリズムに出会える楽しみがあります。應典院もそうですね。
自分は若い頃は語りの苦手意識がありましたが、40歳の時に自分のリズムで語りをやろうと決意して、以来18年間、毎月の観音講で檀家さんに話を続けています。近頃は、自分が應典院などで学んできたものを伝えているんですが、語ると自分の中に落ちる。得心がいく。それと、檀家さんの興味のきっかけづくりという側面もありますね。
ー最後に、これからの應典院にどんな関心や期待をお持ちですか。
私たちの世代の僧侶によって、刺激的で、エポックメイキングな場所であったことは間違いありません。しかし、今の20代、30代の世代がどう見えているか私にはわかりません。親子ほど世代が違えば、意識や価値観が違って当然です。秋田さんも27年間やってこられて、多分、その辺りの認識があったんではないでしょうか。
最近、ディープケアラボの川地さんたちと新しいコラボを立ち上げられた。30代の若い彼らにイニシアティブを委ねるというスタンスですよね、そこは先見の明がある。昔の應典院に比べて、いま座談形式のセッションとか対話が増えていますね。場のあり方が変化してきていると感じます。應典院が、時代を見ながら最適のやり方をチューニングされている。それを27年間続けてこられたわけですね。
今度「仏契機(ホットケーキ)の会」がありますね(5月26日実施済)。秋田光軌さんや釈徹宗先生のご子息の大智さんがでますね。さっき申し上げたように、私には何を考えているか完全にはわからないが、若い人がどんなところへ向かっていくかそこは期待しているんです。
應典院にはそういう世代を超えた人々が集う「場の力」がある。27年間、耕してきた畑は豊かな土壌となっていると思います。