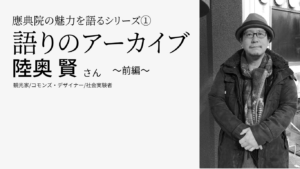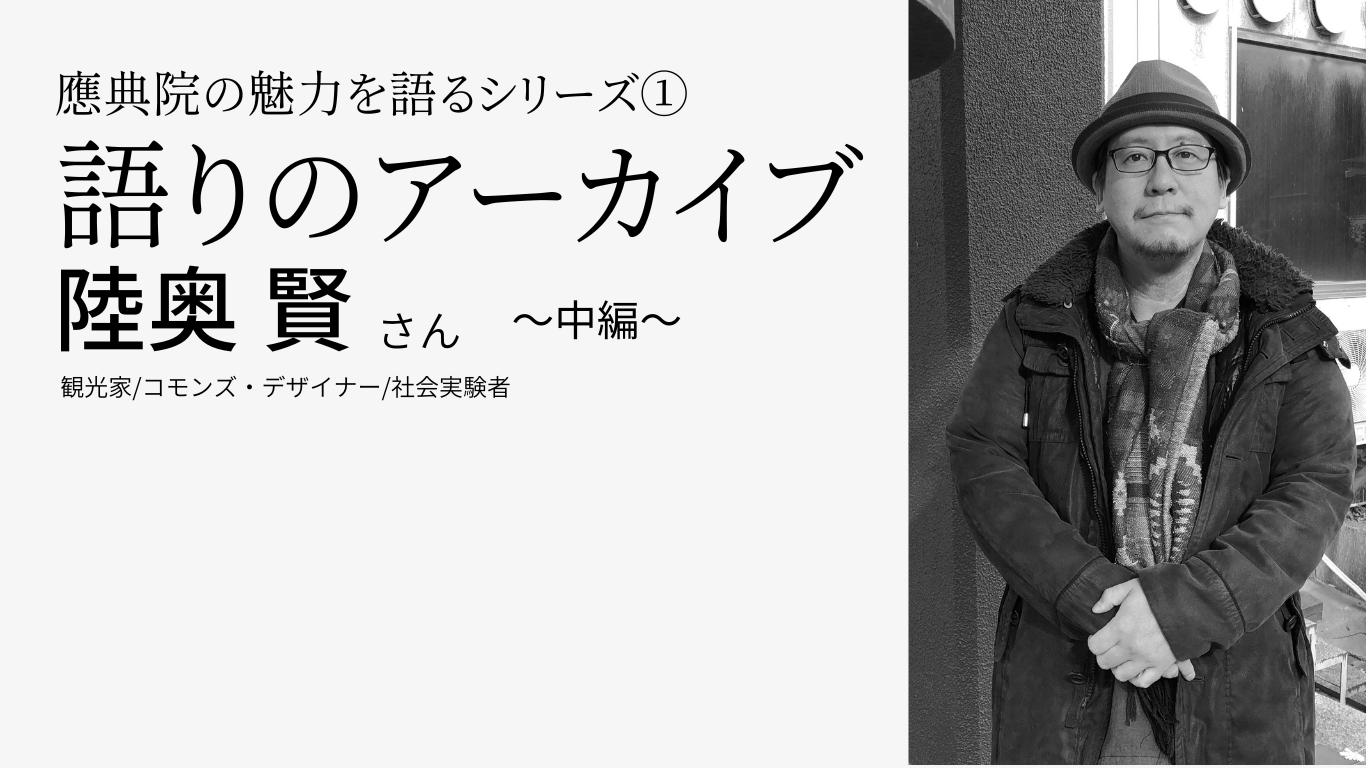
2025/3/13【語りのアーカイブ】應典院の魅力を語るシリーズ①陸奥賢さんインタビュー(中編)
應典院のWEBサイトは現在、事業やイベントの告知のみならず、過去事業の開催報告などのアーカイブ、あそびの精舎としての取り組みや狙いを仏教の教えと共に伝えていくことを主な目的としています。情報の提供だけでなく、読み物としても充実したサイトになっていくことを目指して、この度、新たにインタビュー記事の連載を始めることにしました。應典院に縁のある方々から、これまでの應典院との関わりや、場所としての魅力や可能性について語って頂きます。
第1弾は、これまでに應典院で様々な企画を実践され、應典院を長らく外側から見つめて来られた陸奥賢さんにお話を伺いました!今回は中編です。
インタビュアー/中嶋悠紀子
陸奥 賢(むつ さとし)
観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。1978年大阪・住吉生まれ、堺育ち。最終学歴は中卒。15歳から30歳まではフリーター、放送作家&リサーチャー、ライター&エディター、生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)の大阪ガイドなどを経験。2007年に地元・堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞(主催・堺商工会議所)。2008年10月から2013年1月まで「大阪あそ歩」(2012年、観光庁長官表彰受賞)プロデューサー。2011年から「大阪七墓巡り復活プロジェクト」「まわしよみ新聞」(読売教育賞最優秀賞受賞)「直観讀みブックマーカー」「当事者研究スゴロク」「演劇シチュエーションカード 劇札」「歌垣風呂」(京都文化ベンチャーコンペティション企業賞受賞)「死生観光トランプ」などの一連のコモンズ・デザイン・プロジェクトを企画・立案・主宰している。大阪まち歩き大学学長。著書に『まわしよみ新聞をつくろう!』(創元社)。2024年4月から日本初のコミュニティ・サイクル・ツーリズム「いわき時空散走」のプロデューサーに就任。
コモンズフェスタで生まれた「まわしよみ新聞」と「如是我聞」
―ここでようやく應典院の話になるのですが、コモンズフェスタの企画委員となってから、どのような関わりをされていたのでしょうか?
企画委員として何をしようかと話しているうちに「まわしよみ新聞」を思いつきました。お寺ってそもそもコモンズ(共有地、共有財産)だよねという前提があって。そして実際に應典院は色んな人が来る場所で、多様な人が入り乱れる場なんですが、もっと、そういう場や時間を作りたいと思いまして。そこで、いろんな人たちに呼びかけて、いろんな新聞を應典院に持ってきてもらって、それをみんなで回し読んで気になった記事をはさみで切って、それについて話をしたり、雑談したりしたあとに、切り取った記事を一枚の壁新聞にして貼っていくっていうメディア遊びをやったら、意外に面白くて妙に大ヒットしまして…。ワークショップにも著作権などがあるそうですが、「まわしよみ新聞」はコモンズだから敢えてそういう権利は主張せずに、とりあえずホームページだけ作ってやり方を載せておくので、いつでも、どこでも、だれでも自由に勝手にやってくださいということにしました。すると口コミでどんどん知れ渡って、僕自身も色んな場所に呼んで頂いてやることになって、あっというまに日本全国各地に広まっていきました。特に喜ばれたのが新聞業界ですが、教育業界、ビジネス、まちづくり、アート、福祉関係にも使われています。特に誰かと話すことには演劇の要素もあって、まわしよみ新聞をやった後に即興劇をやる企画などもありました。
應典院では「まわしよみ新聞」の他にも「如是我聞」※という24時間トークイベントなんかもやりました。毎年12月24日~25日に一日中應典院を開いて、来た人のとりとめのない話を24時間、不眠不休で聞き続けるという苦行みたいな企画です(笑)5~6年やりましたかね。これが毎年大盛況で、クリスマスの日に独り身の人がわんさかやって来るんですよ(笑)
「如是我聞」って実は、お経の最初に出ている言葉で、「このように私は聞いた」という意味です。お釈迦さんって、生前、その教えを文字や書物では全く残さずに、全部、弟子たちには口頭で伝えたという不立文字(ふりゅうもんじ)の人で、経本なども文字化したのは全部、弟子たちです。また、お釈迦さんは全員に同じようなことを教えるのではなく、弟子の特性、人柄、性格、向き不向きなどに合わせて仏に至る道を教えていったようなところがありまして。そしてそれを基に、それぞれの弟子が悟りを開いて、いろんな教団を作ったりしていったんですが、100年くらい経つと「あれ?うちの教団の教えは、他の教団の教えとなんか違うぞ?」というような話もでてきたりして。それでいろんな教団が集まって、お互いが聞いたことを照合したのですが、そのさいに「かくのごとくわれきけり(如是我聞)」という言葉から、それぞれの教えを語ったといいます。そういう教えが纏められて、やがて「ダンマパダ」「スッタニパーダ」という初期の仏教経典が誕生していったとか。人によって掛ける言葉を変えるというのは、これが、しかし、お釈迦さんの凄いところ、深いところで。「お前は掃除をしなさい」とか「お前は人の話をよく聞きなさい」とか「拈華微笑」(花をもって微笑む)とか。それで弟子たちが、それぞれちゃんと悟ったりしますから。お釈迦さんが、いろんな方法や手段を駆使したから、多様な仏教の解釈が生まれて、多様な宗派が生まれることになったように思います。真の教育者は、その人、その瞬間に、最も必要とされる言葉や態度で、相手を導いていく。どのような人にも対応するような方法論が無数に用意されていて、卓越した救済の技法が仏教にはあって、それがまた奥深いなぁと思っています。
▲應典院で開催された「如是我聞」の様子。
社会実験と演劇
―陸奥さんご自身の企画だけでなく、企画委員として様々な方との調整役も担っていたかと思われます。当時はコモンズフェスタとは別で賞レース型の演劇祭「space×drama」(通称:スぺドラ)をやっていたこともあり、演劇関係者も多かったように思います。どのような連携があったのでしょうか?
当時のコモンズフェスタは、本堂が劇場仕様になっていたこともあって、演劇関係の参加者もたくさんいました。でも非常に残念なことですが應典院を単なる劇場利用が出来る貸小屋ぐらいにしか見ていない人も少なくなかったように思います。実は、それは應典院側の問題意識としてもあったようで、お寺で演劇をやる意味や意義、価値。何故、ここでやるのか?ということをもっと演劇人には問うて欲しいと思っていました。演劇をやる人にもっとお寺という場所の在り方に関心を持って欲しかったし、関わって欲しかった。コモンズフェスタの開催は、そういった演劇人に対するサイン、メッセージも込められていたと思います。僕は企画委員として関心を寄せてくれた一部の演劇人たちと協働で、演劇とかアートとかの垣根を越えて越境する場づくりをやった方だと思います。そういう企画を僕自身は「社会実験」と呼んでいましたね。演劇とかアートとかいうと、結構、ややこしい人が出てくるので(笑)「実験」という言葉が良くて。果敢にチャレンジすることが出来ました。
―少し話は逸れますが、演劇を歓迎しながらも、お寺が目指す場にはなっていかなかった。陸奥さんから見て、そこにはどのようなズレがあったと思いますか?
僕自身は十代の頃に演劇をやっていて、大阪の小劇場にどっぷりハマった時期がありました。中島らもさんや新幹線、そとばこまちなど面白い役者さん、劇団がたくさんいた時代で。でもそういう人たちは東京に進出したり、テレビ業界で活躍するようになっていった。それから十年以上経って、2012年頃、大阪の小演劇を見た時に、僕が若い頃に観ていた90年代の劇団の構造やシステムとあまり変わっていないように見えて驚きました。東京進出とかテレビ出演みたいなものが、まだ劇団や役者のゴールや夢に設定されていて、それは應典院の目指す場とは相いれない部分があったように思います。
でも、最近になって次の世代が出てきたようにも思います。僕は、演劇には期待してるんです。教育と演劇、福祉と演劇、老いと演劇、当事者と演劇などなど。時代の中で、社会の中で、演劇がやれることはたくさんあると感じています。もちろん仏教と演劇というテーマも当然、ありえるし、面白いい動きが起こればいいなと。そのときに應典院の過去の取り組みが良いモチーフになると思っています。
※まわしよみ新聞:オープンソースで「いつでも、どこでも、だれでもできる」が合言葉!むつさとし(観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者)が考案した大阪(應典院生まれ・釜ヶ崎育ち)発信の「メディア遊び」。 2017年、読売教育賞 NIE部門最優秀賞受賞。三省堂高校国語教科書『明解国語総合』(平成29年度版)採択。NIE・NIB・アクティブラーニングに恰好のツールとしても注目されている。(http://www.mawashiyomishinbun.info/)
※如是我聞:24時間、不眠不休で多様なゲストや参加者と、取り留めのない四方山話をする企画。コモンズフェスタ2013から2018年まで、計6回実施された。(https://www.outenin.com/article/article-10537/)