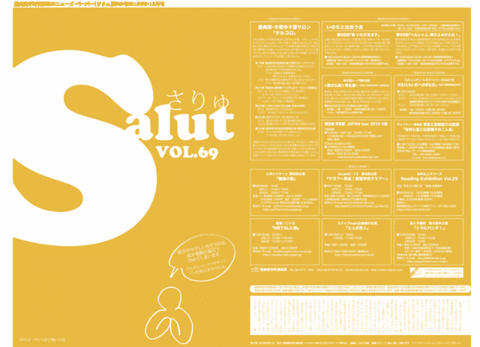
サリュ 第69号2010年9・10月号
目次
レポート「エンディングセミナー2010」
コラム 大林輝さん(NPO法人環境情報ステーションpico代表)
インタビュー 蓮行さん(劇団衛星代表/大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任講師)
編集後記
巻頭言
相手がやさしいかどうかは、
私が独断と偏見で
決めてしまいます。
アルボムッレ・スマナサーラ
「ブッダが教えた本当のやさしさ」
Report「葬」
感情や行動を抑え込まず、社会の常識や通念を疑ってみる。
お墓が縁のコミュニティ
應典院の夏には「演劇祭」と「エンディングセミナー」が並行して展開される、これが慣例となってきました。97年の再建以来、舞台芸術祭space ×dramaは、特に若手劇団が切磋琢磨する機会となっています。一方、エンディングセミナーは比較的年配の方からのご関心が寄せられるのではないか、と受け止められるのではないかと思っています。しかし、特に今年のセミナーは、3回ともに、幅広い年齢層かつ広範な地域からご参加をいただきました。
今年のエンディングセミナーには「『遺族』をどう支えるか〜グリーフサポートとしての葬送を考える」というテーマを掲げました。これは、年間114万人が亡くなる現代が「多死社会」であると捉え、そうした時代を生きる私たちは多くのグリーフ(死別の悲しみ)を背負っている、という前提に立ったためです。そこには少子化が加速して、人と人のつながりが分断し、また孤独死、無縁死も急増する中、死者と遺族の関係にも大きな変化が押し寄せているという背景があります。そこで、多彩なゲストをお招きし、このテーマに接近いたしました。
7月10日、3回連続の1回目には「NPO法人エンディングセンター」の井上治代代表をお招きしました。おなじみの「寺子屋トーク」の枠組みにて開催し、満場の本堂ホールにおいて「墓友」というキーワードで議論が進みました。井上さんは90年代から血縁に代わる新たな結縁型の永代供養墓や、桜葬や樹木葬など、自然志向の非継承墓の普及など、市民中心の新しい葬送の試みを通じて、社会的な関心を集めてきました。当日はNPO法人遺族支え愛ネットの出口久美さんの進行のもと、「『就活』ならぬ『終活』という『死』を自分でデザインする時代、お墓のコミュニティに生まれる血縁だけではない新たな人間関係が大切になってきている」など、刺激的な意見交換がなされていきました。
味方になることの見方
演劇祭まっただ中のエンディングセミナー、今年は2回目と3回目が大蓮寺にて開催されました。7月18日には、テレビドラマやコミック「死化粧師」のモデルとして知られる「株式会社ジーエスアイ」の橋爪謙一郎代表取締役を招き、数多くの死別を見つめてきた立場から、「死」をきっかけに人間どうしのつながりを再生させる「グリーフサポート」の観点についてお話を伺いました。また7月25日には「自殺対策に取り組む僧侶の会」の藤澤克己代表をお招きし、自殺念慮者との手紙相談や自死遺族の分かち合い、追悼法要などを通じて、人間の回復力を信じ、「何かしてあげる」支援ではない「見守り」と「伴走」としての活動をご紹介いただきました。こうして、看取り・見送り・供養の制度や様式の変化が余儀なくされる時代の新たな葬送の文化に接近していきました。
3回通じてご参加の方の感想の中にあった「私には、支えてくれる人がいた」ということばが印象的でした。自身も含め、生きていれば必ず死が訪れます。しかし、個人主義と経済合理化の中で、喪失の悲しみに向き合い、浸る間がシステムにより奪われてしまうことがあります。今回のセミナーでは、相手の「味方」として寄り添っていくことが、大きな支えになることを実感させられることとなりました。
なお、7月10日には開会に先立ち、大蓮寺の生前個人墓「自然」を契機とした、第1回自然賞贈呈式が実施され、秋田住職から井上さんに贈呈されました。今後、お寺がNPOに独自の資金援助を行う画期的な仕組みとして注目が集まることでしょう。末筆ながら本事業には、公益財団法人JR西日本あんしん社会財団より助成を得ております。ご支援を賜りましたことに対し、記して謝意を表します。
小レポート
應典院のお盆の風物詩…詩の学校特別篇「それから」
8月4日、「詩の学校」特別篇「それから」が開催されました。既にお盆前の恒例となっていますが、主宰する詩人の上田假奈代さんと参加者のみなさんが、この1年で触れた死にまつわる出来事を振り返る機会となっています。例年どおり、まずは大蓮寺にて秋田光彦住職による法要と法話の後、墓地にて詩作と朗読が行われました。続いて、所々に蝋燭あかりが灯された墓地にて、40分ほどの時間をかけて、思いをことばに重ねていきます。 その後、それぞれによって紡がれたことばが、懐中電灯の手元あかりの中で発表されました。それは思いを寄せられた死者からのメッセージのようでもあり、墓地に響く朗読の声が、時に読む人にも聞く人にも涙を誘っていました。朗読の最後は上田さんが務め、「生まれて死にゆく人よ 死んで生まれてくる人よ」と題した詩が披露されました。 同じ「シ」と発音する「死」と「詩」。詩を通じて死、さらに生に向き合うひとときでした。
小レポート
「はたらく」を考える「ミニ大阪」開催
8月21日・22日にかけて「ミニ大阪2010」が開催されました。これは20年以上にわたってドイツのミュンヘンで展開されている「ミニ・ミュンヘン」を範としているものです。この1月、コモンズフェスタの一環で開催された「ミニ★シティであそぼう」が記憶に新しいところでしょう。 今回は2007年から「ミニ大阪」を毎年開催しているNPO法人こども盆栽が主催。7月末から4回にわたる「こども会議」により、演劇ワークショップなどを通じて「どんなまちにしたいか」を考えた上で本番が迎えられました。また、両日とも13時より中崎町のR-Cafe店主の店主、藤井有美さんを招いた「大人まなび」プログラムも実施され、世代を超えて働く、遊ぶ、遊ぶ場が生まれました。
小レポート
高校生・スタッフ・劇場の成長機会・HPF
23校が参加した今年の大阪高校演劇祭「High school Play Festival(HPF)」。その中の9校が應典院で公演しました。7月19日から9日間、今年のテーマ「芝居たろか・演劇夏の陣〜学生一揆〜」を体現するかのように、各校それぞれに非常に力強いお芝居が展開されました。 今年は舞台の仕込みをサポートをするスタッフの参加も多く、連日活気にあふれていました。中でもHPFの参加経験のある大学生たちが、OB・OGとしての距離感ではなく、サポートスタッフの一員として活躍する姿も見られました。8月21日の閉幕セレモニーには全参加校が集う中、関西小劇場で活躍する演出家や役者らが講評。褒めるだけではなく、厳しい意見も寄せられる中で、高校生たちは熱心にメモに取り、真剣に耳を傾けていました。来年も楽しみです。
コラム「公」
“生物多様性”って何? あなたにとっての繋がりをみつめて
今年は、国連の国際生物多様性年だ。10月には名古屋で、生物多様性条約の第10回締約国会議(COP10)が開催される。
生物多様性を一言で言ってしまえば、「いろいろな生き物が、繋がっていること」と言えると思う。様々な生き物が、親と子という時間の中で、その地域という場の中で、しっかり繋がっている。この「様々(種)」「時間(遺伝子)」「場(生態系)」の3つの多様性こそが、この地球に命を溢れさせたキーワードだ。
さて、COP10では、生物多様性の保全はもちろんなのだが、どうやって各国の人間から文句が出ることなく、生き物を資源として継続的に利用できるかを話し合う。あーあ、大切にされている生き物は人間だけなのだ。そうか、条約は人間同士の約束事だったのだと、あらためて納得。
日本人は、「自然からの恵み」「自然に感謝」などという言葉が大好き!生き物を“生物資源”“遺伝資源”などと言われると、ちょっと落ち着かない。どこか心の奥のほうで、人間も自然の一部だと思っているからに違いない。そういえば不思議なことに、このまま環境がどんどん悪化して、人類が滅んでも、仕方がない。と、思っている人に時々出合う。そういう私もその一人なのだが。
生物多様性では、生物が誕生してから今までの40億年という時間軸も多様性の要素だと考える。だから、生物が自然の中で影響しあって、自由に進化や絶滅していくことも阻害されてはならない。人類が滅ぶことも受け入れる。それもやはり、人もこの地球上の数ある生き物の一つに過ぎないと、どこかで思っているからだろうか。
ところで、生物多様性が私たち人間に与える機能として、レクリエーションや文化など精神的な効能も大きい。ここで、「自然」でなく「生物多様性」と言うのがミソ。つまり、生物多様性は繋がりだからだ。この地球上で様々にほかの生命と多様な形で繋がっている自分。自分にとっての生物多様性をみつけることが、この地球上の、多くのいのちを守ることにほかならないと思う。
大林 輝 (NPO法人環境情報ステーションpico代表)
1954年生まれ。主婦をしている時、食器を洗ったこの洗剤はどこへ流れていくのかと思った。やっぱり石鹸の方がいいのだろうか?そんな、身近な疑問を解決するのが高じ、ぜひ皆にも伝えたいと環境情報誌を発行。「本」の発行は、考えていたより大変だったが、仲間に恵まれた。 この道15年。いまや世間はインターネットの時代、しかも環境もエコも当たり前になった。今こそ、次の一手を!!と日夜考える日々である。 2010年度より應典院寺町倶楽部専門委員(環境担当)
NPO法人環境情報ステーションpico http://www.pico-jp.net
Interview「劇」
蓮行さん
劇団衛星代表・大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任講師
それは、若い演劇人が、貧乏でもいいから、
プロでできる環境づくりに劇場が取り組んで欲しい。
「芸術的な才能を発揮する人は、何か表現したいという衝動だけで始めるわけではないと思うんです。」高校、大学と軽音楽部の蓮行さんは、女の子に「モテたい」との一心から大学1回生のときに演劇界に入った。「とある学生劇団に入ったのですが、既にほぼ解散が決まっている状態でした。そこで今後も継続して活動する仲間と共に総合芸術集団潔癖青年文化団(現:劇団ケッペキ)を結成しました。」
その後、全国的にも珍しいプロの演劇集団として劇団衛星を設立。大学4回生のときだった。「他の『劇団を大きくする』と抽象的な夢を語っている人たちもアルバイトを掛け持ちしながら公演していました。そこで社是ならぬ団是としてプロ化を掲げ、事務所を借り、専任スタッフを雇い、経営者として『ショットガン方式』で外部資金を獲得していくことにしたんです。」
蓮行さん曰く「小劇場演劇界ではプロの劇団は皆無」。そんな中で「プロの劇団を創った」ことが付加価値として意味を持つと考えた。そのためにはリスクを取らないと動いていけない。そこで蓮行さんは演劇人が持っているスキルやプレゼンス(存在感)を供給し続けられる「小さいながらもゼネコン」として、どのような価値が提供できるかを愚直に追究した。時間、能力を何に使えるかを考え、ゲームのシナリオや、テレビの構成作家、撮影モデルなど、手当たり次第で多くの仕事を引き受けた。が、借金ばかりが増えていったという。
2つの場が転機となった。1つは2004年、京都の宇治にある平盛小学校の5年生を対象にした、1年間にわたる特別授業『演劇で算数』だ。「糸井登先生(現・立命館小学校)と千葉大学の藤川大祐先生に『そこまで演劇が何かの役立つのか』と教えていただきました。」もう1つは劇作家・演出家の平田オリザさんが「演劇による教育」に「コミュニケーションティーチング」と名付けたのを知ったことである。 「これまで演劇人は身柄、時間、若さが、社会の中で最も安いレートで交換されてきました。ただ、演劇のためにバイトして1000円稼ぐよりは学校で何かをする機会を得た方が芝居のスキルが上がる。実際、うちの劇団員は劇的に変わりました。」
こうした学校や自治体での劇団による取り組みは外部資金が支えた。「行政の文化予算ではなく、子どもゆめ基金や日本財団など、多ジャンルの活動支援している助成団体からの支援を得ました。その結果、環境、介護施設、IT企業、防災、防犯へと、分野も広がりました。」「答え無き問いを立てる力」こそが演劇を通じて培われていく、とは平田オリザさんの言。「答え無き問いへの答えを、上下関係がない中で、みんなで一つにまとめていくこと、それが演劇ではできるんです。」と蓮行さんは言う。
蓮行さんは昨年、平田オリザさんと共著で『コミュニケーション力を引き出す』(PHP新書)を上梓した。「今年度から文部科学省が『児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験事業』を始めました。こうして演劇への入り口が変わる、増えることで、興味を持たない人をつくらないことが大事だと思っています。そうしていかないと、演劇という手段の話ばかり終始して、内容や展開方法の善し悪しの議論には至らないはずだからです。」
経営的な手腕とリソース(資源)をもって、プロの劇団ならではの事業を展開してきた蓮行さん。今後は「アーティストとしてのバリューが高まる」展開を図っていくとのこと。「この7月、京都の新町高辻にKAIKAという劇場をつくりました。戯曲賞を狙うだけではなく、劇場というビジネスモデルをきちんと創り、演劇のアートとしての評価を得たいと思っています。100席規模の民間の劇場どうし、應典院ともパートナーシップを取れるといいですね。」
編集後記〈アトセツ〉
酷暑である。その中で駆け抜けた、大阪市西区の二幼児死体遺棄事件と、所在不明高齢者と年金不正受給問題の相次ぐ報道には驚かされた。そこには、個人主義と合理化が浸透した今の時代でも、大切な人の死を悼むことが大事だという倫理観の問いかけがあった。そして「孤独死」を放っておいてお金だけを受け取るのは親への冒涜だ、といった具合に、世相に対する静かな怒りを見て取った。
いみじくも、この夏、大蓮寺・應典院の連携により、應典院寺町倶楽部では「グリーフ(悲嘆)」をテーマにしたセミナーを展開した。当然、死は悲しいものであり、その悲しみがあるこそ、生に慈しみの念が抱かれる、このことを深く考える3回の学びの場であった。そして大切なのは「悲しみ」や「慈しみ」など、名詞で捉えられる概念ではなく、「悲しむ」や「慈しむ」など、動詞で捉えられる行動であることに思いを馳せた。
問題が複雑に絡んだ現代社会である。自力だけではどうしようもないことも多い。果たして、頼れる他者が自分にどれだけいるか。この問いを常に引き受けていくことこそ、個人の時代を生き抜く手がかりであるように思う。
他者を信じて頼ること、それが信頼である。信頼こそ関係の問題であり、どんな関係を他者と持つのかは、いつ相手から何を頼りにされるかによって定まっていく問題だ。自らの至らなさに誠実になるということ、それこそ浄土宗の劈頭宣言の一節「愚者の自覚」に他ならない。まずは周りの他者を頼ってみようではないか。(編)
