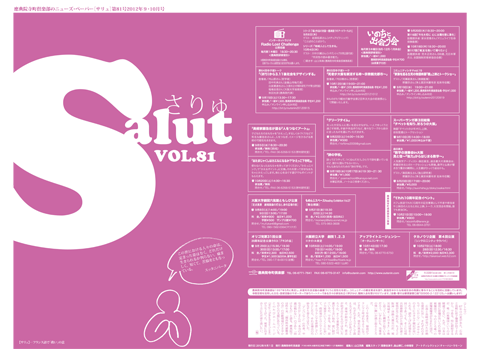
サリュ 第81号2012年9・10月号
目次
レポート エンディングセミナー2012
コラム 中下大樹(真宗大谷派僧侶)
インタビュー 山口育子(ささえあい医療人権センターCOML理事長)
編集後記
巻頭言
この世における人々の命は、定まった姿はなく、どれだけ生きられるか判らない。痛ましく、短くて、苦悩をともなっている。
「スッタニパータ」
Report「看」
看取りの場面から見つめる生き方の〈しまいじたく〉
医療・福祉・宗教の3点で
夏の應典院は、さしずめ「演劇の甲子園」のごとくに、若者たちによる熱闘の演劇祭が続くことで知られていますが、お盆を迎える前に、もう一つ、特徴的な事業があります。それがエンディングセミナーです。2005年以来、應典院の本寺である大蓮寺と共に展開される連続講演会。毎年、固有のテーマを掲げて実施しています。
今年のエンディングセミナーのテーマは「『看取り』から地域を支える」でした。長寿社会、転じて少子高齢社会を迎える中、今、日本は死にまつわる事柄が社会問題として顕著にあらわれるようになってきました。「無縁社会」が叫ばれた2010年には年金不正受給問題として報道されつつも、親族の死が放置された事件は、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。そして身よりがなく生きる人々が「孤族」と呼ばれ、よりよい人生の最期を迎えるための準備が「終活」と名付けられるなど、新たな言葉も生まれてきました。
そこで今回は、病院死が圧倒的多数となる現代において、見送りの意味を看取りの場面から考えることにしました。逆に言えば、どこか懐かしい風景とも言える看取りの行為を大切にする実践から、改めて地域に生きることの意義、また他者と共に生き抜くことの価値について目を向けていこうという問題提起も、このテーマには込められています。そこで、3回連続のセミナーでは、医療、福祉、宗教の3つの現場からの声を伺いました。
生き方が逝き方を左右する
7月8日はNPO法人ささえあい医療人権センターCOMLの山口育子理事長をお迎えしました。「『納得』のサイゴ~その人らしく生きるとは~」と題してのお話では、「賢い患者」になるための知恵を、設立者である辻本好子さんとご自身双方の患者体験から紐解かれることになりました。医療者とのコミュニケーションをどのように重ねることが、医療サービスに対する「賢さ」を当事者と支援者が携えられるかに迫られました。
7月14日はNPO法人つどい場さくらちゃんの丸尾多重子代表をお迎えしました。「『まじくる』って?~つどい場での日常からみえるもの」と題してのお話では、ご親族の看取りの経験をもとに、公的介護保険制度を使わない場づくりで実感したという、地域での生き方・暮らし方が紐解かれました。「まじくる」とは丸尾さんが活動の中でえた実感から生み出した表現で、「いろいろな方が混ざりあって、食事をしながら話し、聞き、学びあう関係」のこと。そのため、日々の生活のよいリズムを生み出すため「施設の利用者」のみならず「場の参加者」に開かれた空間づくりに取り組んでおられます。
そして7月21日には真宗大谷派僧侶の中下大樹さんをお迎えしました。朝日新聞出版から刊行されているご自身の著書名と同じ「悲しむ力」と題したお話では、副題の「死生観なき時代を生きる」上で、いかに生老病死の営みを送るかに迫られました。お寺に身を置かず、一人の僧侶として2000人以上の生活困窮者の見送りに関わってきた中下さん。3回シリーズの締めくくりに、自己肯定感の低さが指摘される時代、他者に関心を向ける主体性が自らの逝き方を左右する、と示されました。
仏教界のエディターとして
後半は小池さんから釈先生へ問いかけがなされました。具体的には3点が投げかけられました。一つ目は宗教学者であり社会福祉法人の経営者であり浄土真宗本願寺派の僧侶で住職でもあるという立場ゆえ「宗教界における仏教の特徴は?」。二つ目は「輪廻転生を信じているか?」。三つ目は「宗教における善悪と社会における道徳との関係は?」です。
いずれの問いも、YesとNoで済まされるものではなく、深い対話となりました。まずは仏教には自他の連続性が根差されているという特徴を確認。そして日本仏教は、伝来以前から土着に根差していた信仰と相まって地域に浸透していったために、輪廻や往生を論理的な説明だけでは万人に納得いく解釈を示すことができないことを互いに深め合いました。そして最後はニーチェなどの西洋哲学も織り交ぜながら、善の押しつけが「べき」論を生み、自分を優位に立たせようとすることによって生み出される「煩悩」的な側面が明らかとされました。
小池さんをして「仏教界のエディター」と言わせしめた釈先生。上記の外にも幅広いお話が。例えば「グレるお坊さんの話」などです。次回を切に期待する次第です。
小レポート
死者を想う一時
應典院開設当時から始まり、今年で15年目を迎える詩人上田假奈代さん主催の「詩の学校」。毎月一回研修室Bにて開催される詩の朗読会が、毎年お盆には特別編を実施しています。大蓮寺での秋田住職による法要と法話に始まり、辺りが薄暗くなった頃、墓地に移って、各々蝋燭を手に詩作。その後集まってつくった詩を披露します。
ぼんやり光る蝋燭が方々にゆらめく中、時折生國魂神社から吹き降ろす風を背に、それぞれ故人に思いを重ねた詩を朗読。亡くなった母の歳を今年超えるという2児の母、引き取り手のない友人のお骨を奉納した女性、そしてお墓に腰をおろしながら其々のストーリーに耳を傾ける参加者。都会のど真ん中にある墓地で、目に見えない存在や死者に思いを馳せる空間は、不思議と非常に心地よい。同じ時代を生きる他者との横軸の関係と、先史から脈々とつながる死者との縦軸の関係を改めて体現した場となりました。
小レポート
高校生のこだわりが凝縮のHPF
今年のHPF(Highschool Play Festival)は、参加校が非常に多く、総勢28校の参加があり、應典院を会場とする高校、13校が7月20日から29日そして、8月9日から12日とお盆直前までの開催となりました。年々、お客様も増え、ちらほらと小劇場をよく観劇している方も目にするようになりました。満席になる高校も多く、サポートスタッフはそれぞれに、知恵を出し合って、客席を作っていました。近年應典院にて、会場下見見学会と技術講習会が行われている事もあり、今年は舞台美術にこだわりを持つ高校生も増え、裏方から役者まで精一杯作品を届けていました。
小レポート
日常に立ちはだかる〈ぬりかべ〉に迫る
7月30日、毎年恒例となってきました神戸女学院大学の「アート・マネジメントコース」の学生の皆さんによる自主企画が今年も應典院で開催されました。昨年は「食と農」でしたが、今年は「妖怪と日常」。夏休み間もないこどもたちを対象に、ちょっといつもとは違った夜をお寺で過ごしてみよう、という仕掛けでした。
前半は京都で活躍する妖怪創作家の河野準也さんが、幽霊と妖怪は何が違うのかなどを、ふんだんな資料から解明。後半は参加者全員で日常生活に潜む妖怪を絵で表現。個々が描いた妖怪は、今後、学生らが「図鑑」にまとめる予定です。
コラム「関」
第四の縁としてのお寺
東日本大震災から一年が過ぎ、被災地に関する報道が減ったと感じるのは私だけであろうか?「もっと被災地の事を取材して、番組で報道してよ」と、友人のテレビディレクターへ注文をつけた。すると彼は「被災地の話は、もう視聴率が取れないんです。多くの人々は東北の被災地の話を好まないのです」と言う。それを聞いて私は愕然としてしまった。大衆の興味に迎合してしまうメディアも問題だが、問題はもっと根深い。つまり私たち一般市民側の「無関心」も問題なのだ。マザーテレサは愛の反対は憎しみではなく無関心と述べた。私たちはどうしたら「無関心」から脱することが出来るのであろうか?
社会には様々な問題が溢れている。しかし、それらを「自分達の問題」として考えることは難しい。現代人は時間的・経済的に余裕がない。余裕がないから考える余裕もない。だが、誰にとっても無視できない問題がある。それは「死」の問題である。誰にとっても死は避けることのできないテーマであるにも関わらず、私たちは「死」について考えることは苦手である。
先日、大蓮寺エンディングセミナー2012に講師として招待いただいた。テーマは「看取り」。家族・地域・会社という縁が機能不全に陥った結果、ひとり誰にも看取られない「孤立死」問題も社会問題化している。家族・地域・会社に代わる新しい第四の縁を構築する必要があると私は述べた。また看取りを通じて、看取られる者、看取る者がともに死から学び、成熟する必要があるとも述べた。
セミナー終了後は座談会を開催し、参加者それぞれの思いを語り合った。お寺は「死」について安心して語れる場だ。第四の縁の一つとして「お寺」をぜひ活用していただきたい。應典院はその先駆けであろう。様々な人的ネットワークを通じて、人々を結びつける役割を果たす應典院のような試みが全国に広まることを願ってやまない。
真宗大谷派僧侶。500名以上の末期がん患者を病院・在宅で看取り、生活困窮者を中心に2000名以上の葬儀に立ち会ってきた。東北の被災地支援・自殺・貧困・孤立死問題にも積極的に取り組んでいる。著書「悲しむ力(朝日新聞出版)」
Interview「琢」
山口育子さん
(ささえあい医療人権センターCOML(コムル)理事長)
患者の主体的医療参加を促進されてきたCOML。
その創始者である辻本好子さんの最期を看取る。
看取り看取られる人間関係の本質に迫る。
夏のエンディングセミナー2012の第一回ゲストとして「『納得』のサイゴ」についてお話いただいた。「賢い患者になりましょう」をモットーに長年患者の自立を支えてきたCOMLの理事長に2011年就任。それまでには、自身のガン患者体験と敬愛する辻本好子さんとの出会いがあった。
25歳を間近に控えた22年前、卵巣ガンを発症。3年生きる確率は20%という医師の判断のもと、当時の過酷な化学療法を経験する。「まだ副作用を抑える有効な薬が認可されていなかった時代で、頻繁な嘔吐に苦しんでいるのに、本当の病状は知らされないかったんです。当時、病名を伝えるかどうかの主導権は、すべて主治医が握っていました。」結局、副作用の一つである脱毛を機に自身で「真実を知りたい」と看護師に申し出て主治医以外の医師から告知を受けた。「ようやくこれで自分の真実の一端を知れた。ずっと疑っていたからか、ショックというよりほっとしたんです。」しかし、一度隠されると医師を信じられなくなる。外出許可が出る度に専門書を買いに行き、ガンについて調べあげた。
勉強するにつれて「ガンも私の細胞の一部であって、悪魔が住みついたわけではないと思いました。こんな元気な身体でよく10 にまで育ったもんだと逆に愛おしさをも感じ始めたんです。」と語る。さらに「死を身近に感じていたとき、自然に対して震えるほど感動したことが何度かありました。みずみずしい若葉や小さな生き物の姿にかけがえのないいのちを感じて涙が出そうになる。今生きている素晴らしさを20代で実感できたことは幸せでした」と付け加える。そして「(ガンになったのが)自分でよかった。死ぬときまで精一杯生きよう」と前を向く。
入退院を繰り返す中で、「死ぬ瞬間に自分に恥ずかしくない生き方をしたい」と強く思いながらも、「自分を十分に生かす道はないか」と感じていたとき、COML1周年を綴った新聞記事を手にした。1ヶ月後、辻本さんに手紙を送付。すぐに「ガン患者さんからの手紙を読んでこんなにワクワクしたのは初めて」という電話を受けたのが辻本さんとの最初の出会いだった。そして「あなたと一緒に仕事がしたいの」という誘いに「この人となら真剣に生きられる」と直感し、二つ返事でCOMLのスタッフとなる。それ以降「生涯ナンバー2に徹するナンバー2」として、2人3脚を続けてきたという。しかし、2010年、COML20周年を迎えた1ヵ月後、辻本さんに末期ガンが発覚。あと1年という余命告知にも立ち会う。「最後まであきらめず治療を受けたい」と、病院と自宅を行き来していた辻本さん。その一言一句、表情、些細なわがまま、すべてを愛おしそうに回想する姿に、単なる上司と部下でもない、家族でも親友でもない、緊張感がありつつも深く、そして絶妙なバランスの人間関係が垣間見える。「無縁社会」「孤族」など湿り気のない人間関係が問題視される現代社会、これだけ密に看取り、看取られる関係は稀有な例なのかもしれない。それでも「本当の信頼関係はたゆまぬ努力」と付け加える山口さん。「人生の最期、誰があなたに寄り添うのか」という問いかけは、「日々をどう丁寧に生きるか」を明示しているのかもしれない。
編集後記〈アトセツ〉
67年目の夏が来た。広島と長崎に原子爆弾が投下されから、である。時に錯綜するが、唯一の被爆国というのは精確ではない。ただ、日本は最初に原爆が用いられた戦争被爆国で、今のところ唯一の原爆被爆者が生まれた国だ。
広島と長崎が受けた壮絶な被害に対し、それぞれのまちで「ヒロシマ」「ナガサキ」のようにカタカナ標記が用いられる。読み上げれば地名と同じであっても、そこには核兵器廃絶に向けた強い決意と覚悟が見て取れる。ちょうど阪神・淡路大震災の折、被災地域を「KOBE」と称し語っていた構図と似ているだろう。いずれにも、当事者の強い願いが感じ取るところだ。
この1年あまり、福島がフクシマと呼ばれるようになってきた。ただ、地名の異表記は、わざわざそうでもして訴えるべきメッセージがあってこそ、意味が創出され、意志が紡ぎ出されるのではないだろうか。そこで重要なのは、誰がそう言い始め、使い続けているか、である。仮に、原子力被害というくくりにおいて、政府等がヒロシマとナガサキとフクシマを併置していたとしたら、それは論点の巧妙なすり替えではないか。
「アンパンマン」の作者、やなせたかしさんは「本当の正義は戦わない」のであり「助けるもの」と語る。應典院では昨年来、「関西県外避難者の会」の活動環境のささやかながらの支援にあたっている。このたびホームページ(http://fukushima-f.com)が立ち上がった。被害に向き合う方にただ寄り添いたい。(編)
